お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております

社会保険調査とは?チェックされる内容も解説
今回は社会保険調査について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=4Oz-CxWh_9g 社会保険調査とは 社会保険調査とは厚生年金と健康保険に関する調査のことで、年金事務所が会社や事業所に対して実施する社会保険の適用と保険料納付の正確性を確認するために行われます。 主に以下の3つがあります。 社会保険適用時の調査 1つ目は新しく社会保険に加入したような会社に被保険者資格の取得漏れや標準報酬月額の設定に不備がないかなどが確認されます。こちらは新規で社会保険に加入してから3ヶ月ほど経つと高い確率で行われます。 目的は被保険者(従業員)の資格取得の漏れがないかや、社会保険料は基本的には給料の金額に応じて決まりますが、最初に設定した給料の金額(標準報酬月額)に間違いがないかが確認されます。 標準報酬月額の設定の不備というのは、例えば通勤手当が含まれておらず設定されていたり、6ヶ月分の定期券などは6ヶ月に6等分して毎月の給料に足すところを支払った時だけ計上していて加入時には加算していなかったなどのパターンがあります。また、例えば週30時間働いていて社会保険加入義務がある方でも働き方が自由な場合、そのような方の標準報酬月額の算定方法が、採用時は35時間だったところを実際は40時間働いていたなどのケースもあります。 加入後の定期調査 こちらが一番多いパターンになります。3〜5年に1回程度の頻度で実施され、給与額に応じた適切な保険料が支払われているかなどが確認されます。毎年7月に算定基礎届を提出する際に一緒に行われます。算定基礎届は通常郵送や電子申請で提出しますが、定期調査がある際は年金事務所にきてくださいという案内がきます。 こちらも先ほどと同様に従業員がきちんと資格取得しているか、給与の金額に応じた標準報酬月額がきちんと設定されているかなどが確認されます。 社会保険未加入事業所への加入勧奨 法律上社会保険の適用が必要にも関わらず、手続きを行っていない事業所に対して加入を促す目的で実施されます。 社会保険調査の頻度 社会保険にすでに入っている会社の場合は、先ほどもお伝えしたように算定基礎届の提出の際に社会保険事務所に呼ばれてチェックされる形となります。そのため、定期的な調査があるという印象です。作成した算定基礎届の内容や賃金台帳をみて社会保険に加入すべき方が漏れていないかなどが確認されます。事業規模にもよりますが、時間としては15〜30分程度で終わる内容のことが多いです。 調査時に見られるポイント 役員の加入漏れ 社会保険に加入すべきところを加入していなかったという加入漏れです。この指摘が多く、指摘されると社会保険料が過去2年分に遡って会社と従業員から徴収されます。 加入漏れで一番多いと感じるのが役員の方です。代表取締役以外の役員の方が報酬を受けているにも関わらず未加入というケースは特に家族経営や同族会社の場合、見受けられます。その他、複数の会社の役員になっている場合、片方の会社で報酬を多く受け取っていてもう片方では少ないので、1つの会社でしか社会保険に加入していないパターンも指摘されます。 もし、非常勤役員の場合は社会保険加入義務はありません。取締役でも非常勤役員ということはあり得ます。非常勤役員で報酬が例えば5万円の場合は社会保険加入義務はありませんが、代表取締役の場合はどちらかの会社で非常勤だといっても代表取締役はそもそも非常勤役員ではないという考えとなり両方の会社で加入が必要となるため注意が必要です。 例えば片方の会社で30万円、もう片方で10万円の給料をもらっている場合、その方の標準報酬月額は40万円という考え方になります。そこで30万円の会社の方では40分の30の社会保険を払い、40分の10をもう片方の会社で払うという形になります。 パート・アルバイトの加入漏れ 次に多いのがパートやアルバイトの方の加入漏れです。フルタイムの正社員以外の方でも社会保険に加入しなければいけない方もいます。 現在は週20時間以上勤務していて、月の給料が8万8,000円以上、最初から2ヶ月を超える雇用見込みなどの場合は短時間労働者の被保険者の要件を満たしているため、社会保険に加入しなければいけません。ただ、この要件は、現在は従業員規模(厚生年金の加入者数)が51人以上の事業所に勤めている場合です。そのため、51人未満の会社の場合は、週20時間働いていても社会保険に加入義務はありません。 この従業員規模51人以上というのは2024年10月からで、それ以前は従業員数が101人以上でした。段階的にこの従業員要件というのは下がってきており、2027年10月以降は従業員数50人以下の会社も段階的に対象となることが既に決まっています。そのため、将来的には週20時間以上働いている方は基本的には社会保険加入の義務がどの会社にも出てくるということになります。 現在は51人未満の会社は、会社の所定労働時間(フルタイムの方が働く時間)の4分の3以上働いていなければ社会保険の加入義務はないという考え方となります。 社会保険についてのご相談もお任せください 今回は社会保険調査について解説いたしました。次回も調査時に見られるポイントの続きを解説いたします。 弊社では、社会保険に関するご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 関連記事:【解説】社会保険はいつまでに手続きをしたらよいのか?
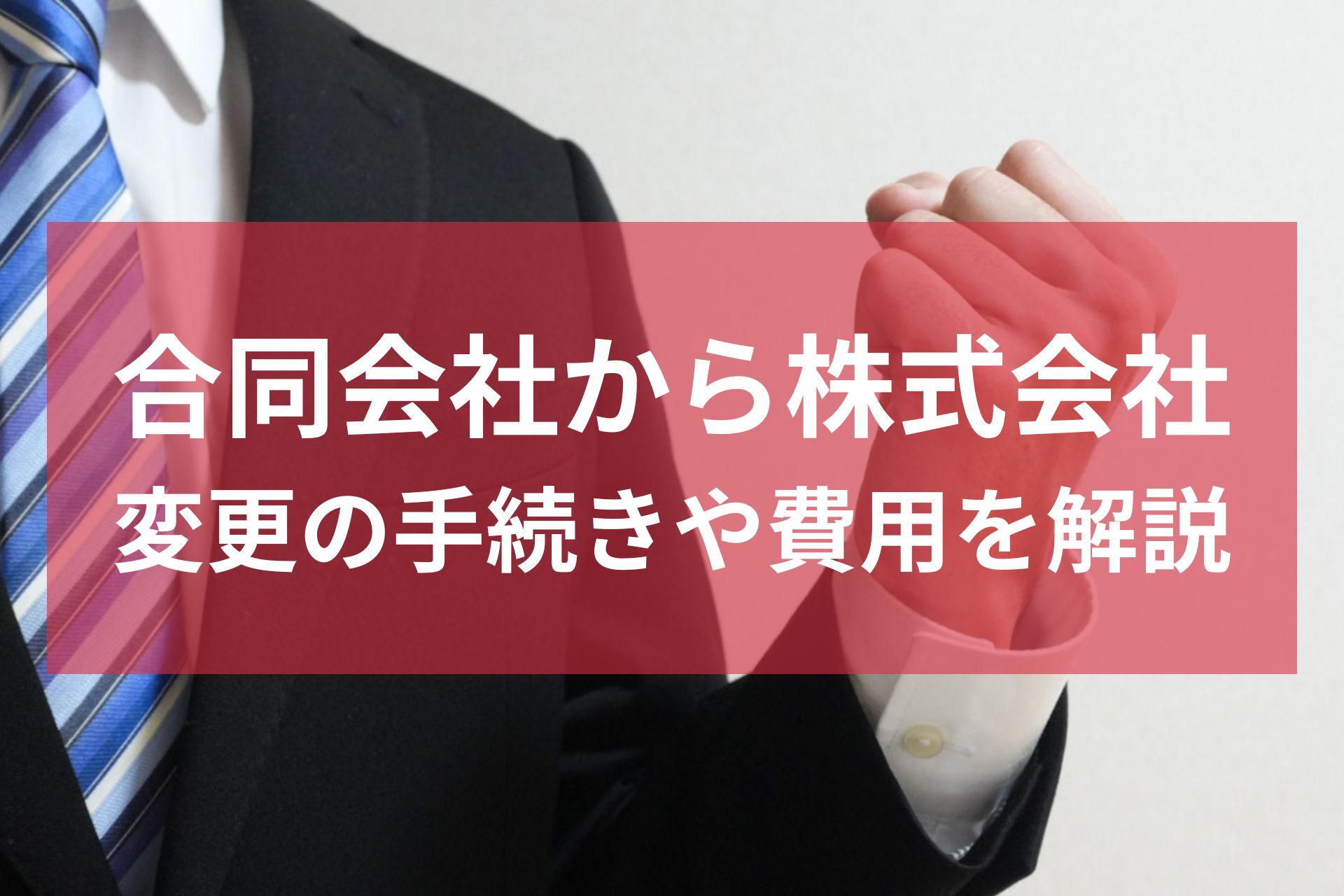
合同会社から株式会社へ|変更の手続きや費用を解説
現在、合同会社を経営されている方で、最初はコストを抑えて合同会社にしたけれど、今後組織拡大して大きくするために株式会社へ変更を検討しているという方もいらっしゃるかと思います。 今回は合同会社から株式会社へ変更する手続きや費用について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=WJxVT1KiWv8 合同会社から株式会社に変更の際の必要な手続き 官報への公告 官報に載せ、合同会社から株式会社に変わりましたということを公告をして会社の関係者(取引先等)にお知らせする手続きが必要です。これによって債権者や利害関係者に周知し、一定期間後に申し立て等がなければ問題なしとして法務局が手続きを進める形となります。 登記申請 合同会社から株式会社に変えるには、登記が必要となります。合同会社から株式会社に変えた旨を法務局に申請して、申請が通れば株式会社に変わることになるため、その変更の手続きに対して準備をする必要があります。 その他行うべきこと 会社の名前が変わることになるため、通帳の名前の変更や契約の名義も変更する必要があります。 また、税務署や県、自治体に名前が変わった旨の届出を出します。その他、ホームページや名刺の変更、取引先への連絡なども必要になります。 発生する費用 費用に関しては、手続き上は以下となります。 登録免許税:6万円 官報への公告:約3万円 合計:約9万円 これに追加して、登記の手続きのため司法書士に依頼する場合はその費用もかかります。 変更までの期間 官報の公告をすると1ヶ月は待たなくてはいけません。これは、1日で良いというわけではなく、それなりに期間を空けて何も問題がなければという趣旨のためです。官報に申し込む時点で1週間ほどかかり、そこから1ヶ月あけてその後登記の申請となります。登記の申請も1週間はかかるので、それを踏まえるとかかる期間としては1ヶ月半〜50日ほどとなります。 変更時の注意点 合同会社で複数人出資者がいる場合には、全員が同意しないと変更することができません。株式会社の場合は株の持ち合いで権利の強さが決まりますが、合同会社はそうではなく1人1票となります。あまり強硬に反対されることはないかと思いますが、全員の同意が必要ということには注意しておきましょう。 株式会社へ変更のメリット 1番のメリットは、対外的に信用度が上がるという点かと思います。 例えば、取引を行うにあたって信用の関係上個人事業主とは取引しない、という会社もあったりします。合同会社の場合は、会社なのですが形態としては個人事業主に近いです。そうなると取引先も個人事業主のような会社である、と見ることがあります。そのため取引上、大きい会社と取引しようということであれば、ネックとなるかもしれません。また、人を採用する際、株式会社ではなく合同会社だと一般の方は「なんだろう」と思ってしまう可能性もあります。 これらのことから信用度としてはやはり株式会社の方が上であるため、それが1番のメリットだと言えるでしょう。 株式会社への変更のご相談もお任せください 状況に応じてですが、事業を拡大していきたい場合は株式会社の方がやりやすい面は多いかと思います。 現在、合同会社で株式会社に変更しようか検討されている方で、事業拡大を目標にされているのであれば変更されることをおすすめします。 弊社でもご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 関連記事:株式会社と合同会社って何が違う?メリット・デメリットを比較 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
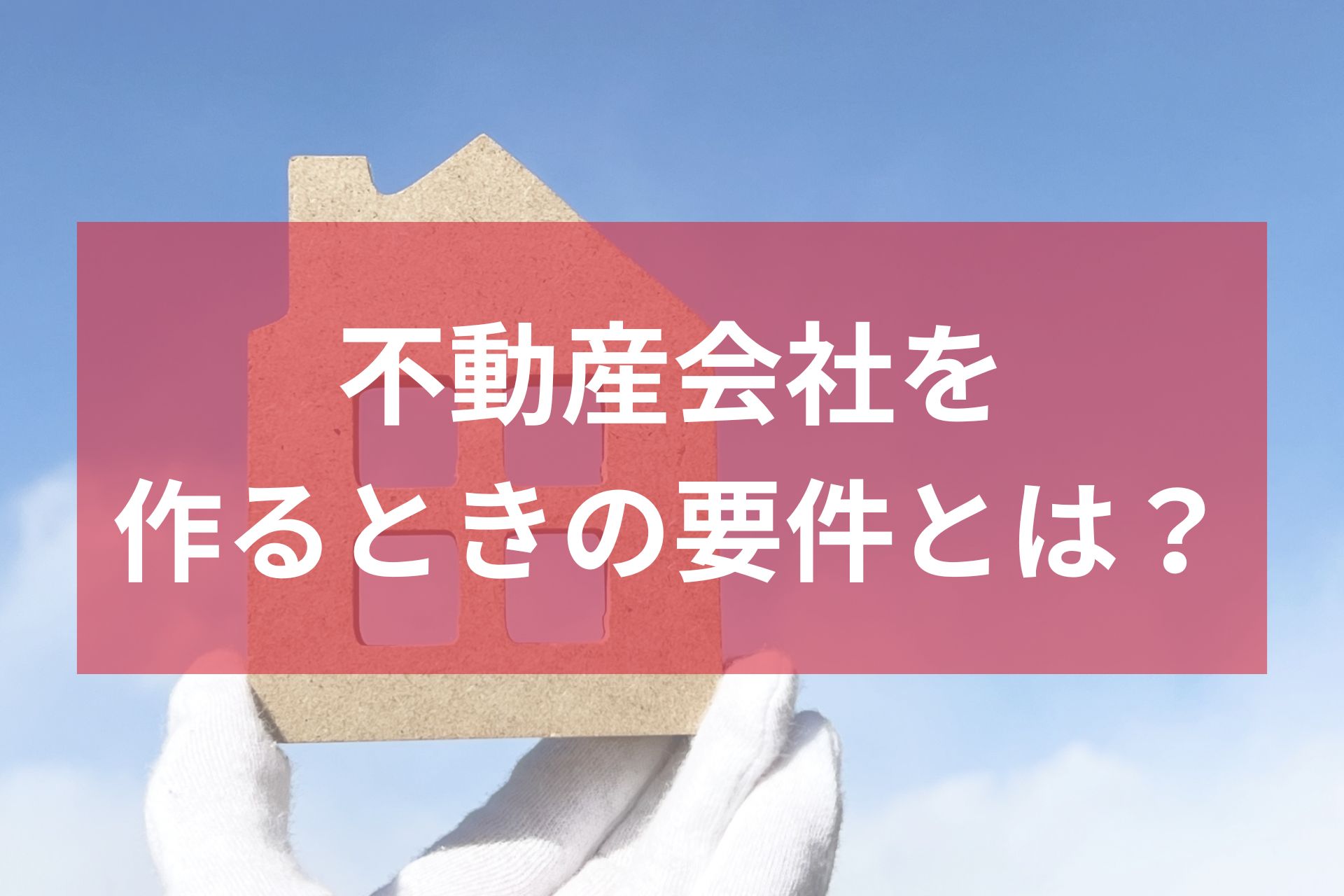
不動産会社を作るときの要件とは?費用や流れも解説
今回は不動産業で会社設立をお考えの方に向けて、会社設立の要件や発生する費用、手続きの流れなどについて解説いたします。 https://www.youtube.com/watch?v=xu0Ar6yzhjM 不動産業の会社設立要件 宅地建物取引業免許の申請 不動産業をするにあたっては、まずは宅地建物取引士試験に受かっている必要があります。いわゆる宅建の試験に受かった後に実際に不動産業に従事する場合は宅地建物取引業免許が必要です。行政に申請をして宅建業者として登録をするという手続きを行います。宅建業の許可がないと不動産業は始められません。 専任の宅地建物取引士の設置 代表者が宅建免許を持っていなくても、宅建業に専従する資格者を配置すれば良いです。 事務所の設置 宅建業をするにあたって事務所を設置しなければいけません。事務所にも要件があり、その要件に従った事務所を構えておく必要があります。 事務所設置に必要な設備はデスク・チェア、応接場所、固定電話、コピー機などです。事務所として最低限要件を備えていることが求められます。きちんと事務所を用意して申請することが望ましいでしょう。 標識の掲示 事務所に宅建取引業者票などを掲示しておく必要があります。 報酬額の掲示 「こういうことをしたらこのような報酬額です」ということを掲示しなければいけません。 これらの他に、通常の帳簿や従業員名簿などを備え付けることなどは通常の会社と同様です。 協会への加入は任意? 宅建協会や全宅保証などの団体への加入は任意ですが、ほぼ加入されているかと思います。なぜなら、不動産売買などの取引は高額で、その仲介をするということで取引者に損をさせることがないように、保証金として事務所を建てる時に供託をしなければなりません。その金額が原則的には本店は1,000万円、支店(1店舗)は500万円となります。このお金は会社のお金として使うことはできません。つまり、会社のお金+1,000万円必要ということになります。ただ協会に入ることで、本店60万円、支店(1店舗)で30万円で済む形になります。そのため、協会に入らないでやるという方はあまりいないと思われます。 不動産会社設立の流れ まず、事務所などを借りて、法人の設立をします。そしてその後に法人名義で許可申請をするという流れになります。その許可が下りたら営業開始です。途中までは一般的な会社設立の流れと同様です。 設立までの期間と開業費用 設立するまでの期間としては登記申請から設立まで1ヶ月かからないくらいでしょう。それから宅建業の許可を取る準備に入ることになります。大体、申請してから2ヶ月以上はかかります。何もなければ設立してからおおよそ2ヶ月後に営業する形になります。 また、諸費用は、協会に所属する形での設立を念頭に置くと、地域差はありますが、協会への加入金や供託金なども含めておおよそ130万円〜180万円ほどとなります。 開業計画はきちんと立てましょう 建設業と同様に不動産業も許可がないと営業できないため、前もって仕事の段取りはきちんとしておくことが大切です。開業の計画を立てる際は念頭に置いておきましょう。 不動産業は1人でもできるという意味では独立もしやすいかと思います。法人化をお考えの方は是非ご相談ください。 関連記事:会社設立時の資本金、いくら用意するべき? 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう!
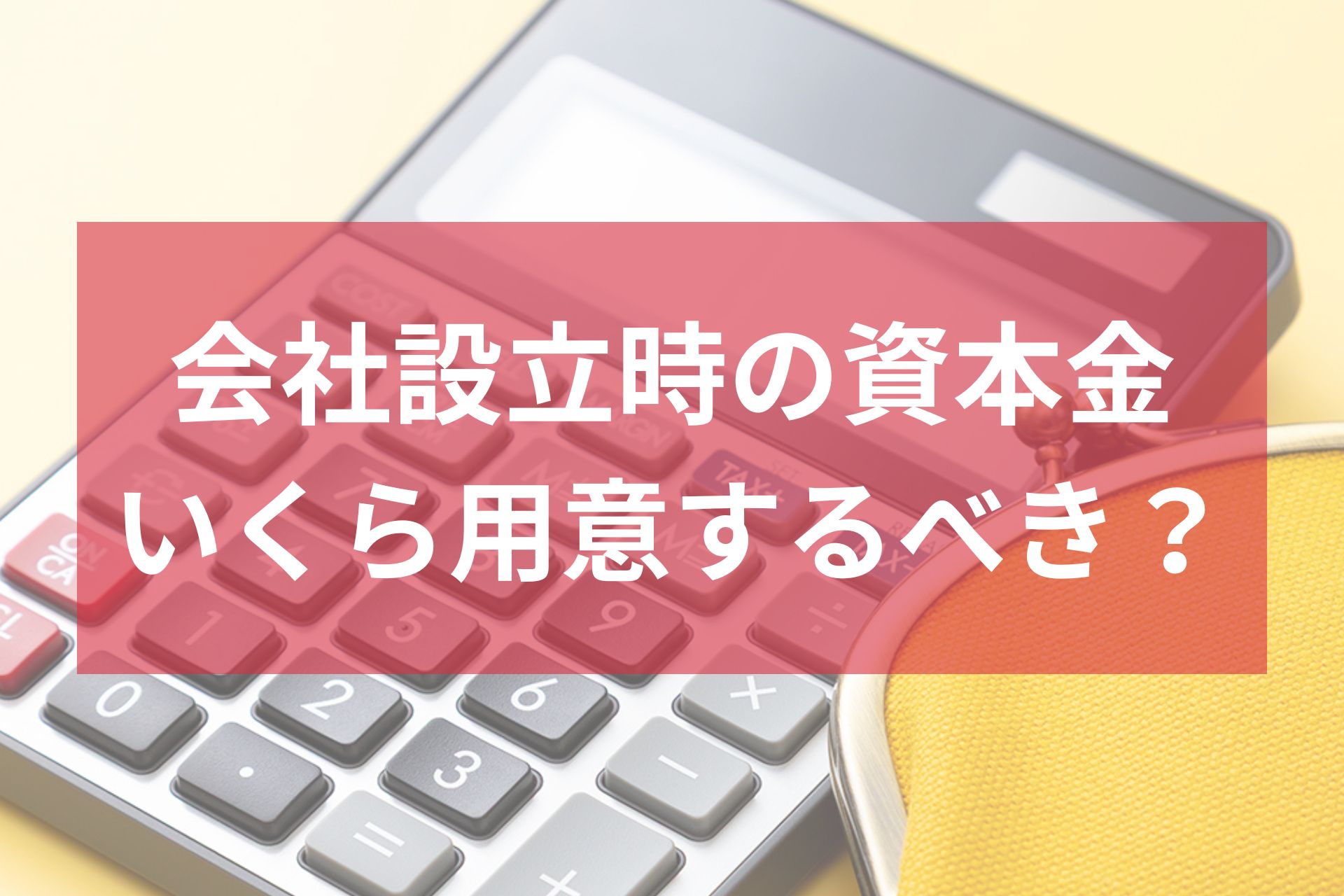
会社設立時の資本金、いくら用意するべき?
これから法人化をお考えの方に向けて、今回は、会社設立時の資本金はいくら用意するべきかを解説していきます。 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて https://www.youtube.com/watch?v=GD6QoQHHUvA 資本金は会社の運転資金? 資本金は設立時に会社に入れるお金となり、そこから経費などを支払ったり、会社に必要なものを買ったりすることになります。そのため、運転資金という認識を持っていただいて良いでしょう。 会社設立時に借り入れをする方も多く、基本的には資本金と借入金で会社を運営していくイメージです。 1円で会社を設立した事例はある? 1円で会社を設立した事例は、私は見たことはありません。法律の改正によってできるようになったのですが、その改正当時は1円で設立してみましたというような方もいらっしゃったのではと思います。 ただ、資本金が極端に少ない場合は信用度合いといったものはほぼないということになってしまいます。例えば資本金1円で借り入れをしようとしても難しいでしょう。少額の資本金でお金を借りるということはハードルが高くなります。また、資本金の金額は登記簿に載るため、取引先の会社にも見られる可能性があり、取引に影響を及ぼす恐れもあります。 また、合同会社でも株式会社でも資本金の考え方は同じです。 金融機関の資本金の捉え方 基本的には、個人事業主がお金を借りる時と同様で「自己資金はいくらか?」という視点で見られることになります。つまり、資本金の額は自己資金の額ということになり、金融機関からは自己資金をきちんと作ってきた人なのか、あるいは作れなかった人なのかという見方をされるでしょう。例えば100万円をきちんと貯めて作れる人は、「事業を始めても堅実に管理をして貯めていける」「利益を出していける」など管理面ではある程度実績がある人だという見られ方をします。逆に自己資金がつくれないとすれば、「お金を管理するのが苦手な人」と思われる可能性があります。 資本金は借入額の何割用意すべき? 望ましいのは借入額の2〜3割ほどは自己資金を用意しておいた方が良いと思います。自己資金が多ければ多いほど借り入れは通りやすくなり、銀行側としても安心でしょう。仮に3割用意できない場合でも、例えば1割ほどは最低限用意していただいた方が良いです。 税法上の資本金の考え方 税法上は資本金が多いと税金が増えるというケースがあります。これは大まかにいうと、資本金の金額が1億円を基準に中小企業か大企業かというラインが引かれている形です。1億円を超えると使えない特例があったり、中小企業ではないのでという条件ができたりなどします。例えば、交際費は中小企業は法人で年間800万円経費にできますが、1億円超えると大きい企業なので800万円という枠がなくなります。また、今は中小企業は、法人税は800万円までは税率は低いですが、それも1億円を超えるとなくなってしまいます。 このように、1億円というラインで受けられなくなる特例などが多数あるため、仕組み上税金が増えてしまうことがあります。 また、会社設立時の資本金が1,000万円以上の会社は消費税を必ず納めなくてはなりません。消費税は基本的に2年前の売上が1,000万円あれば納税義務者になります。会社設立時は2年前の売上がないため、本来は消費税を納めなくて良いのですが、1,000万円以上の資本金がある場合は消費税を納めることになります。(今はインボイスが始まっていて、設立時から消費税を納めることが多いため、消費税について資本金がいくらというのはあまり関係がなくなってきている感じもありますが、一応そのような規定があります。) 最低限用意すべき資本金額 資本金がいくら必要かというのはケースバイケースです。 例えば我々の税理士業で言えば、税理士を個人事業として持って、税理士業以外の保険の代理店やコンサルティング業務のようなことをやる場合、合同会社を設立しその法人に売上を上げるとします。その場合、特に借入をするわけではなく取引先も税理士としてその方自身を見るため、会社の信用などはあまり関係ありません。そのため資本金は少ない金額でスタートしても問題はないでしょう。 逆にご自身の会社として仕事をしていく場合は、信用は大事になり、資本金はある程度用意すべきでしょう。 その他、建設業などは資本金の制限があるのでそれを満たす必要があります。 会社設立に関するご相談もお任せください 今回は会社設立時の資本金について解説いたしました。 先ほどのように事業を行うにあたっての資本金のラインがない場合はいくらでも良いのですが、最低でも100万円ほどはあった方が事業の本気度は見せられるでしょう。 弊社でも会社設立に関するサポートをさせていただいています。今後会社設立をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。 関連記事:建設業で会社設立!必要な許可やその要件を解説 関連記事:運送会社を設立!運送業許可の要件とは? 関連記事:不動産会社を作るときの要件とは?費用や流れも解説
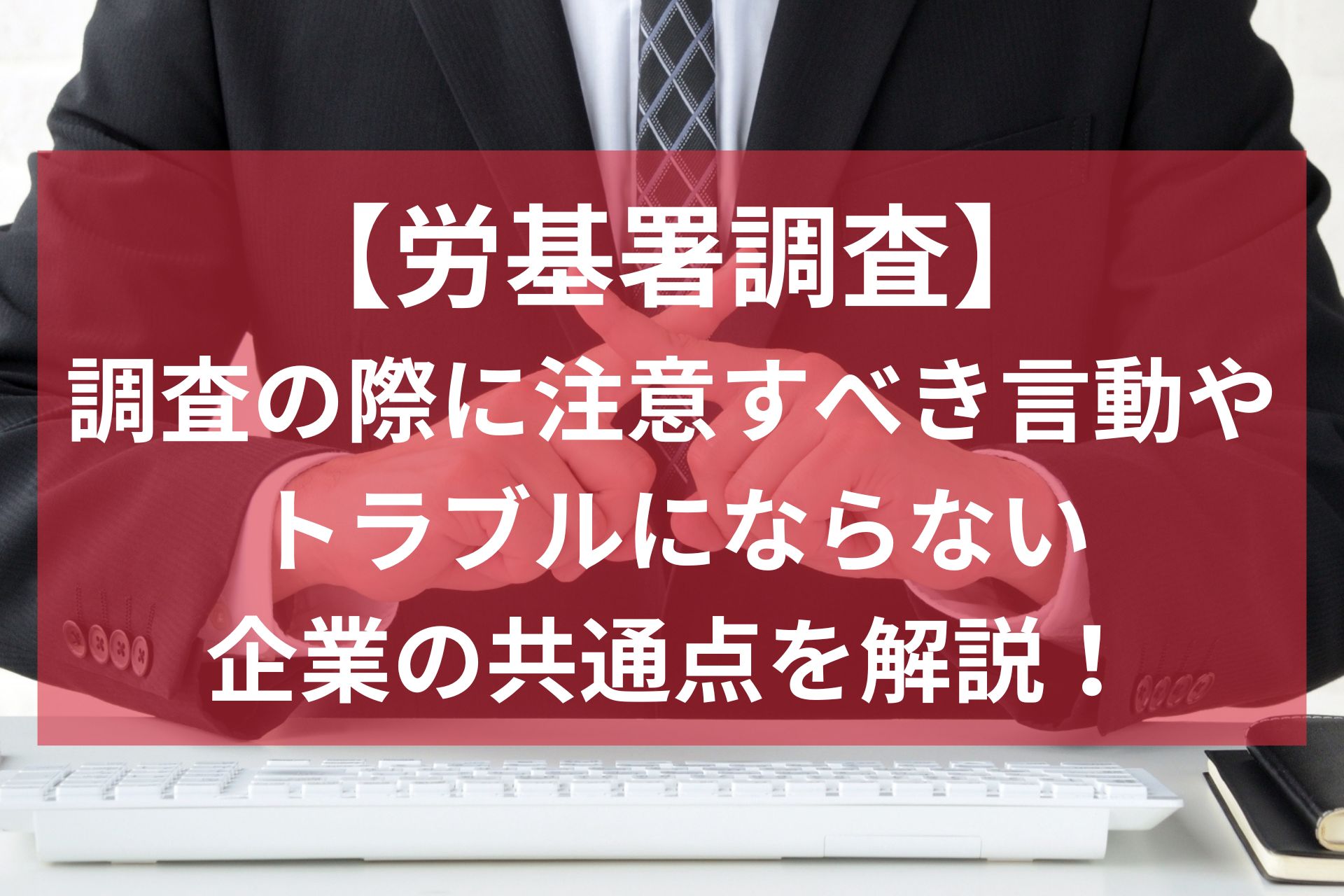
【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
今回は労基署調査の際に注意すべき言動や調査結果の通知方法、労基署調査でトラブルにならない企業の共通点などについて解説していきます。 関連記事:【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説! https://www.youtube.com/watch?v=0x2DAdilcMk 労基署調査時に注意すべき言動 税務調査と同様ですが、聞かれていないことを話さないということはとても重要です。 例えば、経営者が労務管理の実務などを総務部長などに全て任せていて労働法などをあまり分かっていないような状況で「昔はサービス残業が当たり前だった」「最近は有休を取るやつが多い」などと口走ってしまうと労働法に関するリテラシーが低い経営者だと思われてしまいます。必要なこと以上の話をしないということは重要です。 また、労基署の監督官も人です。そのため最初の印象でその後の調査の深さが変わることもあります。敵対的、防御的な態度をとってしまうとマイナスになることが多いため、冷静で協力的な姿勢を見せることが大切です。 さらに、監督官からの質問に対して即答しないことも重要です。例えば「給与計算は正しくされていますか?」と質問があり、「もちろんしています。残業代もきちんと払っています」と答えたとしても計算方法が法律に従っておらず間違っているケースもあります。そのため、即答するのではなく、記録や書類などで裏付けて答えるということが非常に重要です。口頭で不用意に答えてしまうことで後から書類と違うと指摘されてしまう原因にもなるため、「分かりません」ではなく「確認してお答えします」という形で対応するようにしましょう。 労基署調査の立ち会い依頼はできる? 労基署調査の場合は無予告が多いため、労基署調査の立ち会いをきっかけにではなく、是正勧告書が出されてその対応方法が分からないということでご依頼いただくことが多いです。 ただ、もし事前に通知があり、労基署調査に立ち会って欲しいということであれば立ち会うことは可能ですが、あまりそのようなご連絡をいただいたことはありません。 税務調査のように税法の解釈に違いがでやすいといったこととは異なり、労基署調査の場合は書類の整備や残業代の計算方法など法律を遵守しているかどうかが問題となります。そのため、調査に立ち会うというニーズは税務調査と比べると少ないです。 調査結果の通知方法 労基署調査の場合は違反があれば基本的に書類で届き、違反がなければ口頭で終わることが一般的です。違反や改善指導がある場合は、是正勧告書または指導表を渡されます。 是正勧告書は、違反の条文、具体的な是正内容や是正期限が記載されて、期限までに是正報告書を証拠書類を添付して労基署に提出します。指摘内容としては未払い残業の支払いや有給管理簿の未整備、36協定の届出について、健康診断未実施など多岐にわたります。もし間に合わない場合は、「間に合わないので〇〇までに変更してください」と連絡をすればよほどのことがなければ期限を変更してもらえたりもします。 指導表は、明らかな法律違反とまではいかないけれど改善が望ましいような軽微な場合に渡される可能性があります。ただ内容的にも改善が必要なものについては是正報告と同様に期限が定められて報告することもあり、逆に報告が必要とならない指導の場合もあります。 また、安全面で重大な危険がある場合には使用停止命令や作業停止命令が書面で交付される場合もあり、これは即時対応しなければいけません。業務の一部を停止して対応すべきケースもあります。悪質だったり重大な労働法違反があったりする場合は、是正勧告に加えて司法処分、書類送検をされることがあり、最終的には裁判や罰金となってしまう恐れもあります。 再調査の実施頻度 再調査は、調査の結果と事務所の対応次第で大きく変わってきます。結論から言うと、再調査はあまり頻繁に行われるわけではありませんが、是正勧告が未完了だったり、不十分な場合は高確率で行われる印象です。弊社が対応した範囲では、是正勧告書が出た事業所の2〜3割ほどが再調査を受けているように思います。 労基署調査でトラブルにならない企業の共通点 当日の取り繕いだけではなく、日頃の労務管理の積み重ねが重要です。これは書類を準備することだけではなく、書類と実態が一致しているかどうかです。雇用契約書や就業規則、賃金台帳、勤怠の記録などの内容がどれを見ても矛盾がないことが大切です。例えば、契約書上の労働時間と実際のタイムカードの打刻時間が一致していることなどです。規定は立派でも現場で全然守られていない状況だといけません。また、勤怠と給与計算が同じ担当者で1人の裁量だけで処理されていないか、きちんと2重チェックされているかなども大切です。 さらに、有給休暇の管理がきちんとされているかも重要です。時間外労働に関しては36協定を出して毎年更新届出済であることが必要になります。それと加えて有給休暇の管理簿が全員分揃っているか、年5日間の付与義務を満たしていない場合だと30万円の罰金のリスクもあるため注意が必要です。 あとは必ず労基署調査でも確認される安全衛生で、年1回の定期健康診断を全員に実施していることや漏れがないかなどのチェックをきちんとできているか、安全衛生管理者や衛生委員会などの選任と記録が残っているか、労災事故が起きた場合に死傷病報告書をきちんと作って提出しているかなども重要です。 日頃から労務管理をきちんと行いましょう これらのことは書類の準備だけではどうにもなりません。労務管理は年間に1回のことが多いため、社内カレンダーでスケジュールを管理するということも大切です。 労基署調査に関して相談したいという方は、是非お問い合わせください。 関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説! 関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説!