お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
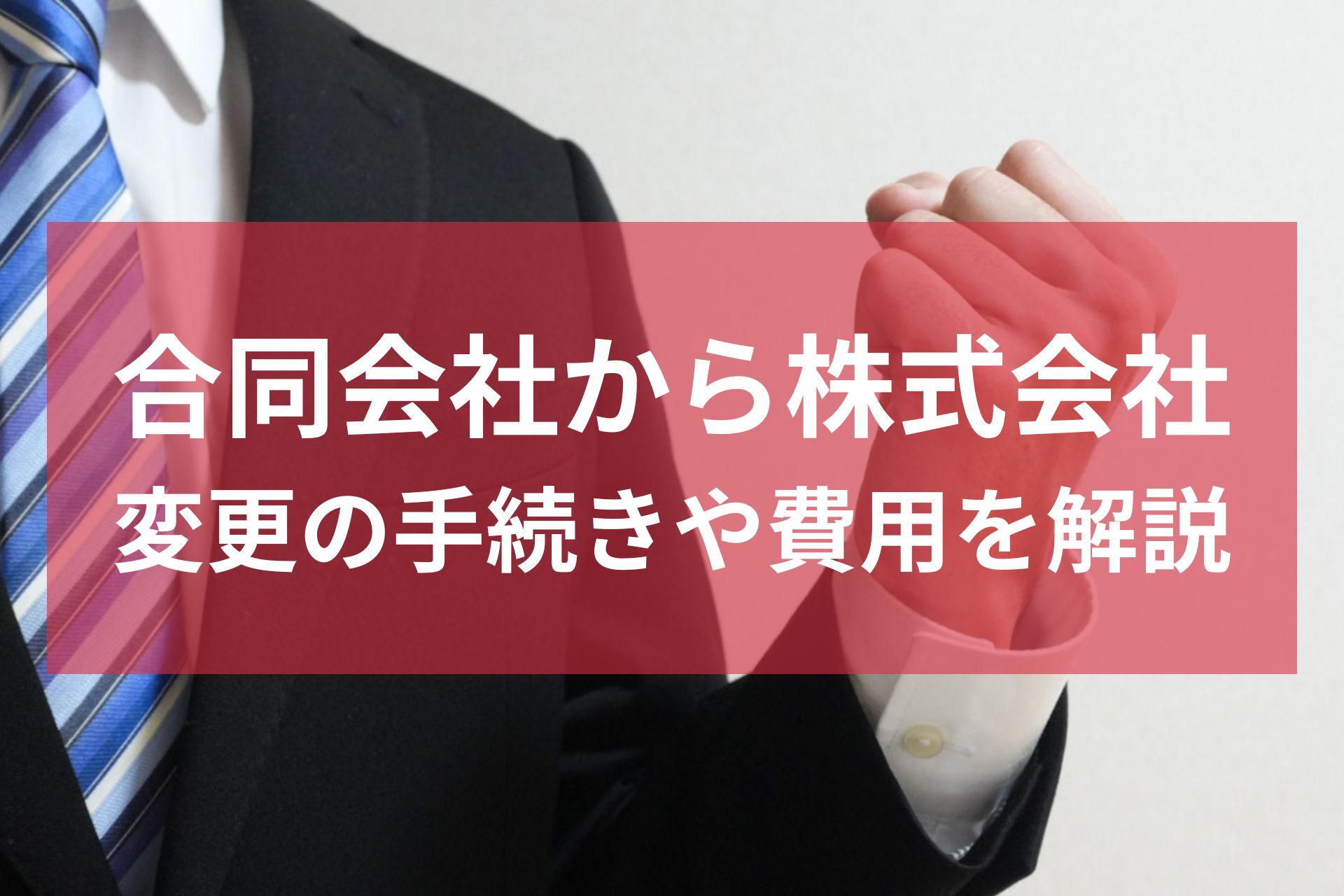
合同会社から株式会社へ|変更の手続きや費用を解説
現在、合同会社を経営されている方で、最初はコストを抑えて合同会社にしたけれど、今後組織拡大して大きくするために株式会社へ変更を検討しているという方もいらっしゃるかと思います。 今回は合同会社から株式会社へ変更する手続きや費用について解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=WJxVT1KiWv8 合同会社から株式会社に変更の際の必要な手続き 官報への公告 官報に載せ、合同会社から株式会社に変わりましたということを公告をして会社の関係者(取引先等)にお知らせする手続きが必要です。これによって債権者や利害関係者に周知し、一定期間後に申し立て等がなければ問題なしとして法務局が手続きを進める形となります。 登記申請 合同会社から株式会社に変えるには、登記が必要となります。合同会社から株式会社に変えた旨を法務局に申請して、申請が通れば株式会社に変わることになるため、その変更の手続きに対して準備をする必要があります。 その他行うべきこと 会社の名前が変わることになるため、通帳の名前の変更や契約の名義も変更する必要があります。 また、税務署や県、自治体に名前が変わった旨の届出を出します。その他、ホームページや名刺の変更、取引先への連絡なども必要になります。 発生する費用 費用に関しては、手続き上は以下となります。 登録免許税:6万円 官報への公告:約3万円 合計:約9万円 これに追加して、登記の手続きのため司法書士に依頼する場合はその費用もかかります。 変更までの期間 官報の公告をすると1ヶ月は待たなくてはいけません。これは、1日で良いというわけではなく、それなりに期間を空けて何も問題がなければという趣旨のためです。官報に申し込む時点で1週間ほどかかり、そこから1ヶ月あけてその後登記の申請となります。登記の申請も1週間はかかるので、それを踏まえるとかかる期間としては1ヶ月半〜50日ほどとなります。 変更時の注意点 合同会社で複数人出資者がいる場合には、全員が同意しないと変更することができません。株式会社の場合は株の持ち合いで権利の強さが決まりますが、合同会社はそうではなく1人1票となります。あまり強硬に反対されることはないかと思いますが、全員の同意が必要ということには注意しておきましょう。 株式会社へ変更のメリット 1番のメリットは、対外的に信用度が上がるという点かと思います。 例えば、取引を行うにあたって信用の関係上個人事業主とは取引しない、という会社もあったりします。合同会社の場合は、会社なのですが形態としては個人事業主に近いです。そうなると取引先も個人事業主のような会社である、と見ることがあります。そのため取引上、大きい会社と取引しようということであれば、ネックとなるかもしれません。また、人を採用する際、株式会社ではなく合同会社だと一般の方は「なんだろう」と思ってしまう可能性もあります。 これらのことから信用度としてはやはり株式会社の方が上であるため、それが1番のメリットだと言えるでしょう。 株式会社への変更のご相談もお任せください 状況に応じてですが、事業を拡大していきたい場合は株式会社の方がやりやすい面は多いかと思います。 現在、合同会社で株式会社に変更しようか検討されている方で、事業拡大を目標にされているのであれば変更されることをおすすめします。 弊社でもご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 関連記事:株式会社と合同会社って何が違う?メリット・デメリットを比較 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
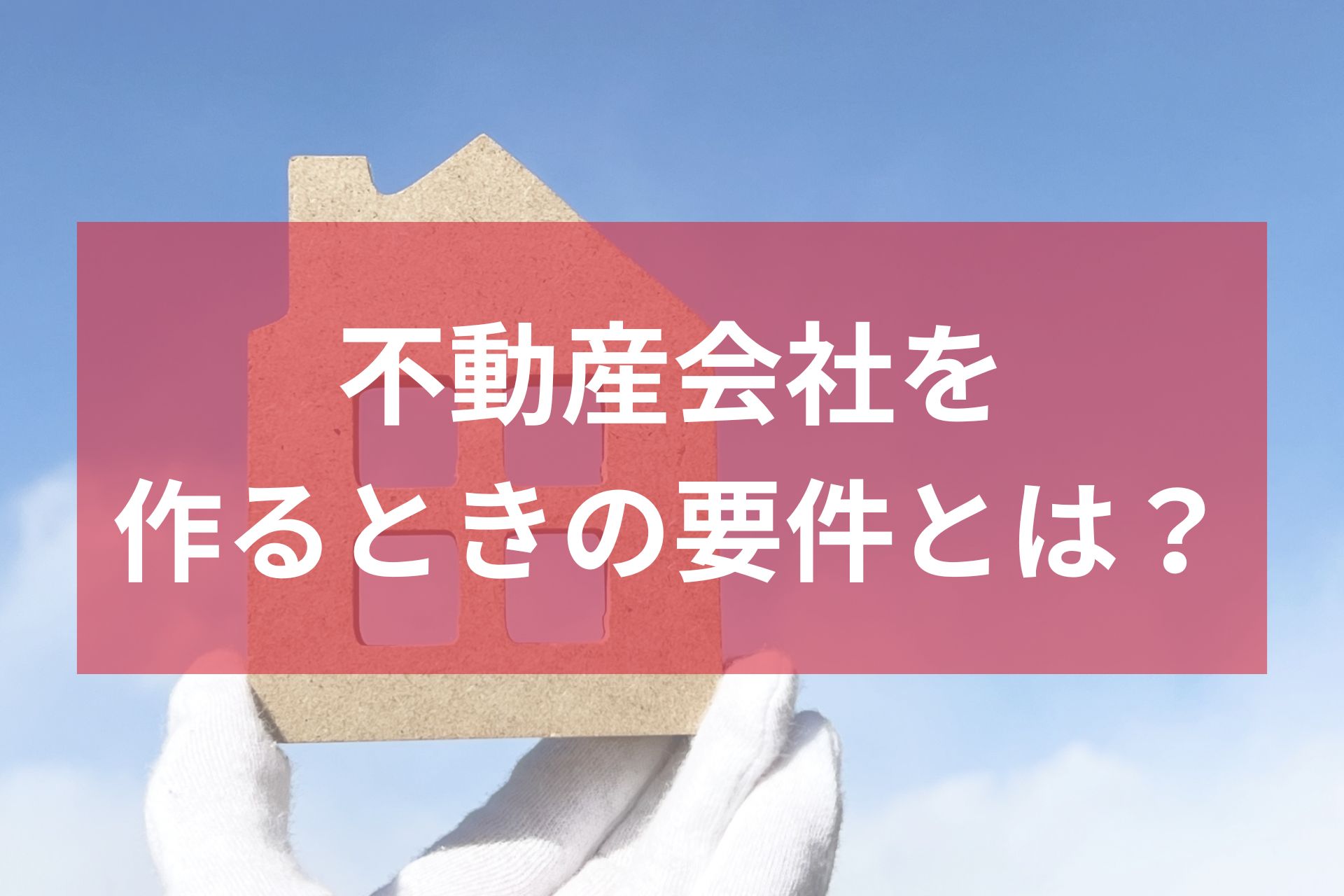
不動産会社を作るときの要件とは?費用や流れも解説
今回は不動産業で会社設立をお考えの方に向けて、会社設立の要件や発生する費用、手続きの流れなどについて解説いたします。 https://www.youtube.com/watch?v=xu0Ar6yzhjM 不動産業の会社設立要件 宅地建物取引業免許の申請 不動産業をするにあたっては、まずは宅地建物取引士試験に受かっている必要があります。いわゆる宅建の試験に受かった後に実際に不動産業に従事する場合は宅地建物取引業免許が必要です。行政に申請をして宅建業者として登録をするという手続きを行います。宅建業の許可がないと不動産業は始められません。 専任の宅地建物取引士の設置 代表者が宅建免許を持っていなくても、宅建業に専従する資格者を配置すれば良いです。 事務所の設置 宅建業をするにあたって事務所を設置しなければいけません。事務所にも要件があり、その要件に従った事務所を構えておく必要があります。 事務所設置に必要な設備はデスク・チェア、応接場所、固定電話、コピー機などです。事務所として最低限要件を備えていることが求められます。きちんと事務所を用意して申請することが望ましいでしょう。 標識の掲示 事務所に宅建取引業者票などを掲示しておく必要があります。 報酬額の掲示 「こういうことをしたらこのような報酬額です」ということを掲示しなければいけません。 これらの他に、通常の帳簿や従業員名簿などを備え付けることなどは通常の会社と同様です。 協会への加入は任意? 宅建協会や全宅保証などの団体への加入は任意ですが、ほぼ加入されているかと思います。なぜなら、不動産売買などの取引は高額で、その仲介をするということで取引者に損をさせることがないように、保証金として事務所を建てる時に供託をしなければなりません。その金額が原則的には本店は1,000万円、支店(1店舗)は500万円となります。このお金は会社のお金として使うことはできません。つまり、会社のお金+1,000万円必要ということになります。ただ協会に入ることで、本店60万円、支店(1店舗)で30万円で済む形になります。そのため、協会に入らないでやるという方はあまりいないと思われます。 不動産会社設立の流れ まず、事務所などを借りて、法人の設立をします。そしてその後に法人名義で許可申請をするという流れになります。その許可が下りたら営業開始です。途中までは一般的な会社設立の流れと同様です。 設立までの期間と開業費用 設立するまでの期間としては登記申請から設立まで1ヶ月かからないくらいでしょう。それから宅建業の許可を取る準備に入ることになります。大体、申請してから2ヶ月以上はかかります。何もなければ設立してからおおよそ2ヶ月後に営業する形になります。 また、諸費用は、協会に所属する形での設立を念頭に置くと、地域差はありますが、協会への加入金や供託金なども含めておおよそ130万円〜180万円ほどとなります。 開業計画はきちんと立てましょう 建設業と同様に不動産業も許可がないと営業できないため、前もって仕事の段取りはきちんとしておくことが大切です。開業の計画を立てる際は念頭に置いておきましょう。 不動産業は1人でもできるという意味では独立もしやすいかと思います。法人化をお考えの方は是非ご相談ください。 関連記事:会社設立時の資本金、いくら用意するべき? 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう!
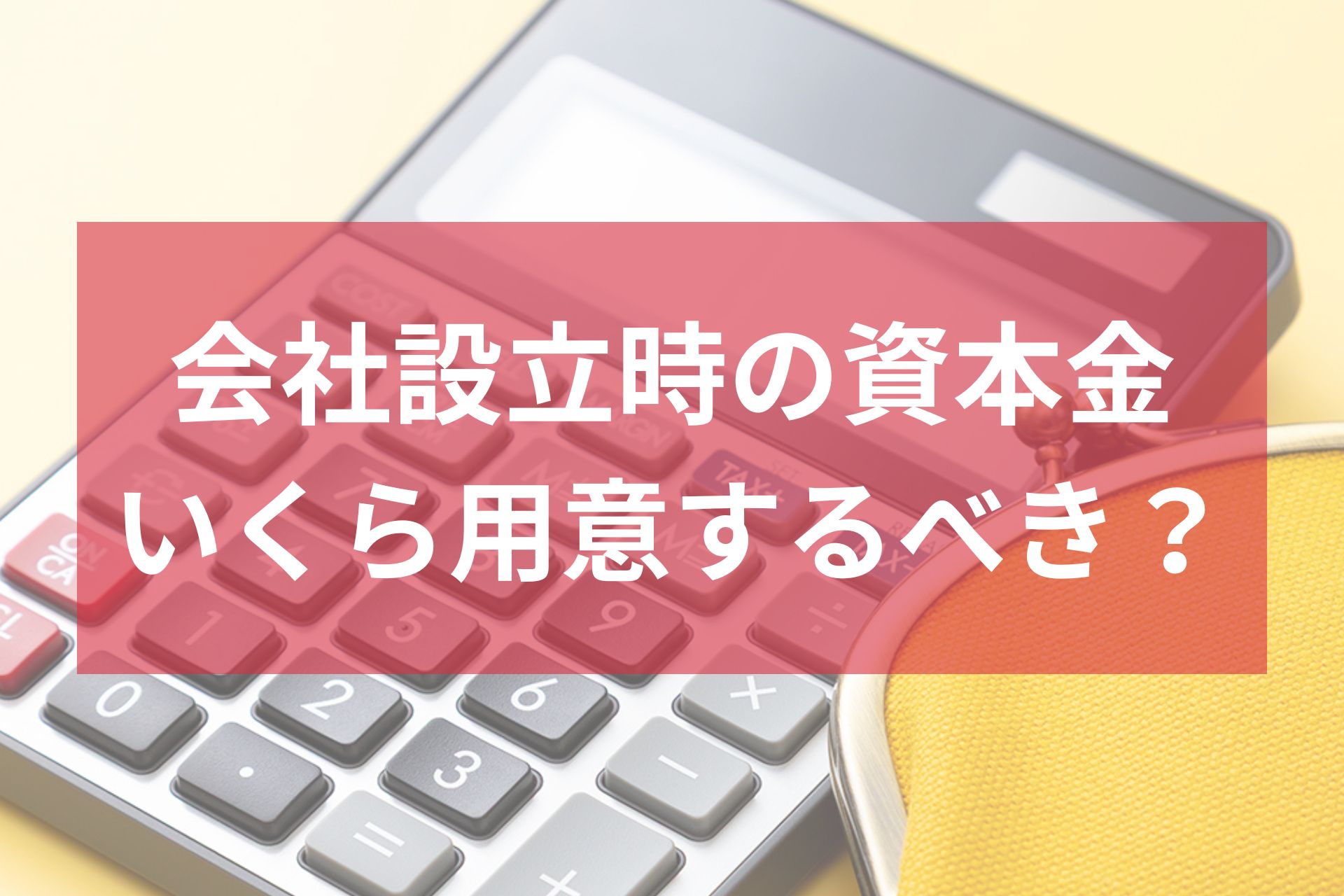
会社設立時の資本金、いくら用意するべき?
これから法人化をお考えの方に向けて、今回は、会社設立時の資本金はいくら用意するべきかを解説していきます。 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて https://www.youtube.com/watch?v=GD6QoQHHUvA 資本金は会社の運転資金? 資本金は設立時に会社に入れるお金となり、そこから経費などを支払ったり、会社に必要なものを買ったりすることになります。そのため、運転資金という認識を持っていただいて良いでしょう。 会社設立時に借り入れをする方も多く、基本的には資本金と借入金で会社を運営していくイメージです。 1円で会社を設立した事例はある? 1円で会社を設立した事例は、私は見たことはありません。法律の改正によってできるようになったのですが、その改正当時は1円で設立してみましたというような方もいらっしゃったのではと思います。 ただ、資本金が極端に少ない場合は信用度合いといったものはほぼないということになってしまいます。例えば資本金1円で借り入れをしようとしても難しいでしょう。少額の資本金でお金を借りるということはハードルが高くなります。また、資本金の金額は登記簿に載るため、取引先の会社にも見られる可能性があり、取引に影響を及ぼす恐れもあります。 また、合同会社でも株式会社でも資本金の考え方は同じです。 金融機関の資本金の捉え方 基本的には、個人事業主がお金を借りる時と同様で「自己資金はいくらか?」という視点で見られることになります。つまり、資本金の額は自己資金の額ということになり、金融機関からは自己資金をきちんと作ってきた人なのか、あるいは作れなかった人なのかという見方をされるでしょう。例えば100万円をきちんと貯めて作れる人は、「事業を始めても堅実に管理をして貯めていける」「利益を出していける」など管理面ではある程度実績がある人だという見られ方をします。逆に自己資金がつくれないとすれば、「お金を管理するのが苦手な人」と思われる可能性があります。 資本金は借入額の何割用意すべき? 望ましいのは借入額の2〜3割ほどは自己資金を用意しておいた方が良いと思います。自己資金が多ければ多いほど借り入れは通りやすくなり、銀行側としても安心でしょう。仮に3割用意できない場合でも、例えば1割ほどは最低限用意していただいた方が良いです。 税法上の資本金の考え方 税法上は資本金が多いと税金が増えるというケースがあります。これは大まかにいうと、資本金の金額が1億円を基準に中小企業か大企業かというラインが引かれている形です。1億円を超えると使えない特例があったり、中小企業ではないのでという条件ができたりなどします。例えば、交際費は中小企業は法人で年間800万円経費にできますが、1億円超えると大きい企業なので800万円という枠がなくなります。また、今は中小企業は、法人税は800万円までは税率は低いですが、それも1億円を超えるとなくなってしまいます。 このように、1億円というラインで受けられなくなる特例などが多数あるため、仕組み上税金が増えてしまうことがあります。 また、会社設立時の資本金が1,000万円以上の会社は消費税を必ず納めなくてはなりません。消費税は基本的に2年前の売上が1,000万円あれば納税義務者になります。会社設立時は2年前の売上がないため、本来は消費税を納めなくて良いのですが、1,000万円以上の資本金がある場合は消費税を納めることになります。(今はインボイスが始まっていて、設立時から消費税を納めることが多いため、消費税について資本金がいくらというのはあまり関係がなくなってきている感じもありますが、一応そのような規定があります。) 最低限用意すべき資本金額 資本金がいくら必要かというのはケースバイケースです。 例えば我々の税理士業で言えば、税理士を個人事業として持って、税理士業以外の保険の代理店やコンサルティング業務のようなことをやる場合、合同会社を設立しその法人に売上を上げるとします。その場合、特に借入をするわけではなく取引先も税理士としてその方自身を見るため、会社の信用などはあまり関係ありません。そのため資本金は少ない金額でスタートしても問題はないでしょう。 逆にご自身の会社として仕事をしていく場合は、信用は大事になり、資本金はある程度用意すべきでしょう。 その他、建設業などは資本金の制限があるのでそれを満たす必要があります。 会社設立に関するご相談もお任せください 今回は会社設立時の資本金について解説いたしました。 先ほどのように事業を行うにあたっての資本金のラインがない場合はいくらでも良いのですが、最低でも100万円ほどはあった方が事業の本気度は見せられるでしょう。 弊社でも会社設立に関するサポートをさせていただいています。今後会社設立をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。 関連記事:建設業で会社設立!必要な許可やその要件を解説 関連記事:運送会社を設立!運送業許可の要件とは? 関連記事:不動産会社を作るときの要件とは?費用や流れも解説
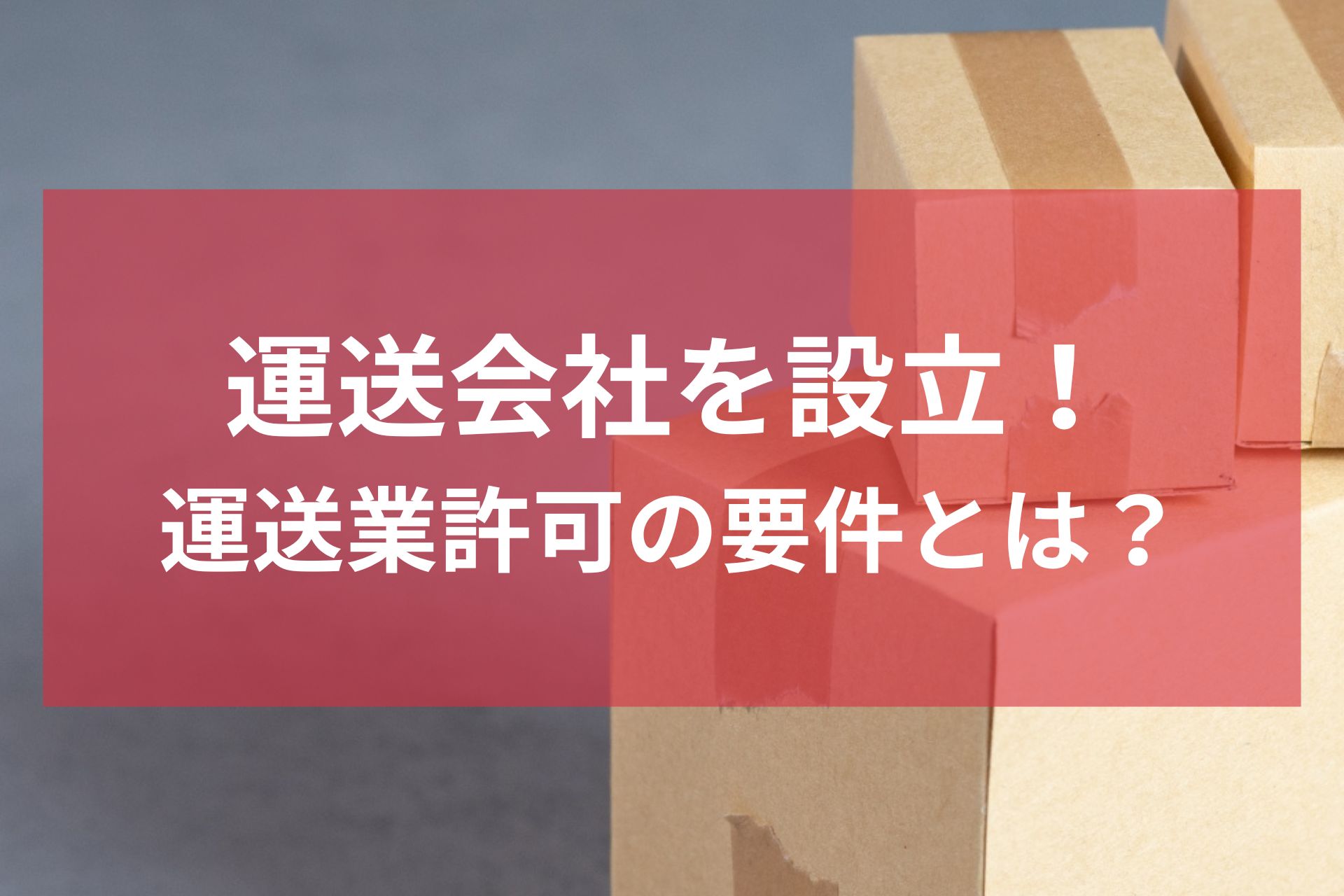
運送会社を設立!運送業許可の要件とは?
今回は運送会社を設立する場合の必要な許可や要件を解説します。 https://www.youtube.com/watch?v=YKCLj_lbR3s 運送業許可の要件 今回説明するものは、4tトラックなど大きめのトラックで他人の物を運ぶという仕事をイメージしていただけると良いかと思います。これを行うのに必要な許可を運送業許可といいます。分かりやすく言うと、緑のナンバープレートをつけて走っているトラックはこの許可を取っているということになります。ちなみに白いナンバープレートで大きめのトラックで運んでいる場合は自社のトラックで自社の物を運んでいます。自分の会社の物を運ぶのは特に許可は必要ありません。 以下で運送業許可の要件について解説します。 車両 まず車両が5台なくてはいけません。それに伴ってドライバーも5人雇用している必要があります。 人 ドライバーとは別に運行管理者の資格を持っている人を在籍させなくてはいけません。 場所 営業所、休憩室、駐車場を設置しなくてはいけません。営業所はきちんと事務作業できるか、そして休憩室に関してはドライバーが5人いてきちんと休憩できるスペースかということなどが重要です。狭すぎてだめだと指摘が入る場合もあるようなので、要件として決まっているわけではありませんが、休憩所や事務所は10平米ほどはあった方が良いかと思います。 駐車場に関してはトラックが5台停められるくらいの広さがないといけません。具体的には230平米くらい、もし大型が混ざった場合は300平米くらいは最低限必要になります。また、駐車場の出入り口前の道路の幅は6mないといけません。一方通行であれば3m必要です。 資金 いくらという決まりはありませんが、半年分ほどの運転資金が必要になります。 資本金額の要件などは特にありませんが、申請する際に資金があるかどうか計算して出す形になります。例えば人件費6ヶ月分がいくらなのかなど、これからかかる経費の積み上げの計算をしていき、それの合計額以上の現預金を持っていることが要件です。人件費がかかるため、大体少なくとも1,000万円前後必要になる場合が多いようです。 このように運送業許可はハードルが高いので、無許可で事業を行っている方もいるようです。その場合、銀行の融資審査で問題になり、事業上のリスクが大きくなります。融資がおりないために資金が必要な時に困るだけでなく、いつ事業をやめさせられるか分からないリスクを抱えた状態なのです。 このような状況を見ると、大きなハードルとして資金要件というのが立ちはだかっているケースが多いです。 運送会社を設立するまでにかかる期間 運送業許可の申請をするのですが、3〜5ヶ月ほどは審査で必要になります。 運送業許可を取るには先ほど説明したような要件の面でのハードルが高いため、しっかり準備をすることが重要です。許可を取得した後もトラックの緑ナンバーを取得したり、自動車の任意保険に加入したり、最後に運輸局に書類を提出したりなどしなければならないことがあります。そのため、設立が完了するまでは短くても半年ほどはかかると思っておいた方が良いでしょう。 長期的な準備をしましょう 前述したように、運送業許可は資金面などしっかりと準備を行っていないといけません。資金だけではなく、車両やドライバーも必要で、申請から事業が始められるまでの期間も半年ほどかかります。今後検討されている方は長期的な準備が必要になってくることを念頭に置いて計画をされることをおすすめします。 運送業の会社設立に関してご不明点がある方は是非弊社までご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:会社設立時の資本金、いくら用意するべき?
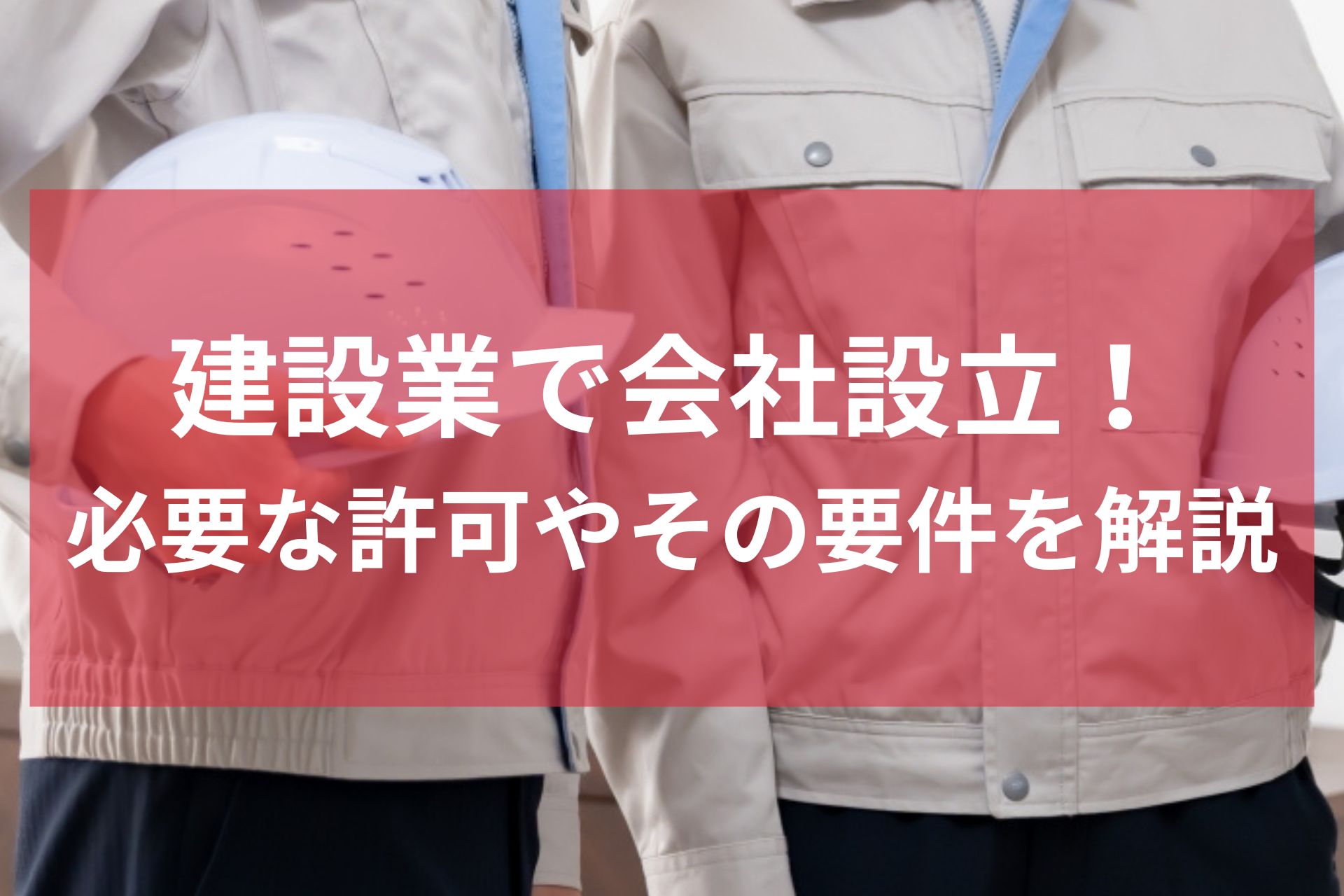
建設業で会社設立!必要な許可やその要件を解説
今回は建設業で会社設立をご検討の方に向けて、建設業の会社設立に関する必要な許可やその要件を解説します。 https://www.youtube.com/watch?v=jHfgtZ3dXiE 建設業許可とは? 建設業で会社設立をするにあたって、一定の金額以上の工事(500万円を超える工事)を請け負うには建設業の許可を取る必要があります。例えば、開業当初などで500万円以下の工事を受注し、経験を積んで改めて建設業許可を取るなどのケースもあります。また、あらかじめ経験を積んでから会社を設立する場合には、会社設立の時から建設業の許可を取るという流れとなるかと思います。会社設立の際に建設業許可を取れそうなのであれば設立と同時に申請をする形となります。 建設業許可を取るための要件 建設業許可を取るためには要件がありますので詳しくお伝えしていきます。 経営業務の管理責任者の設置 現場で仕事をしつつも、事業として建設業をやっている経験があるという方を建設業許可を取る個人や法人におかなければいけません。基本的には建設業の仕事をしている会社の役員や個人事業主で建設業を営んでいる方で、5年以上の経験がある必要があります。この5年以上の経験がないと経営管理責任者になることができません。個人事業主の方であれば確定申告書を5年分、その間の工事の見積書や発注書などの資料を持参し、5年以上の経験があることを証明します。そのため、今後建設業許可を取ろうと検討している方は、発注書などの書類をしっかりと保管しておくようにしましょう。 専任の技術者の設置 建設業許可を取ろうとする分野の5年の経験がある方を1人選任しておく必要があります。実務に従事している経験や、学生時代に建設に関する勉強をした経験なども期間の中に算入されたりと要件は諸々あります。こちらも経営管理責任者と同様に証明をしなければなりません。 財産的基礎・金銭的信用があること 建設業許可を得るには、ある程度の財産的基礎がないといけません。建設業許可は一般建設業と特定建設業に分かれます。この2つで、財産的基礎の内容が変わります。 一般建設業の要件としては、自己資本が500万円以上であることか、500万円以上の資金調達力を有すること、または、5年以上継続して営業しているということが挙げられます。これらのいずれかに該当すれば良いです。もし、会社設立をする際に建設業許可の申請をするのであれば資本金500万円を準備することが必要になるかと思います。 特定建設業の要件は少し複雑になります。簡単にお伝えすると資本金の金額が2,000万円以上でなければならないなど規模が大きくなります。また、毎年の赤字や黒字の累計額がもし赤字なのであれば資本金の20%を超えていないこと、その他、現預金の金額なども見られます。 なお、特定建設業の許可は、発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請に出す際の下請金額が4,500万円以上の場合に必要となります。そのため新しく建設業の会社を設立する場合は、ほぼ一般建設業の許可の取得になります。 請負契約に関して誠実性があること、一定の欠格要件に該当しないこと まず誠実性を判断する基準として、過去5年以内に業務停止などの指導をされていないなどの要件があります。 欠格要件というものは、該当する場合は許可が出せないというものです。例えば破産してまだ復権していない人や犯罪を犯して捕まった人、実刑を受けた人など一般的に見て建設業許可を出すのに不適当である人が欠格要件の中に織り込まれています。 建設業で会社設立される場合はご相談ください! 今回建設業許可について要件をお伝えしましたが、受注金額が500万円以下の工事を受注する分には建設業許可は必要ありません。そのため、早くに独立する場合には、そのような工事の経験を積んでから、建設業許可を取るという流れになるかと思います。 今後、建設業で会社設立をご検討されている方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて 関連記事:会社設立時の資本金、いくら用意するべき?