お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
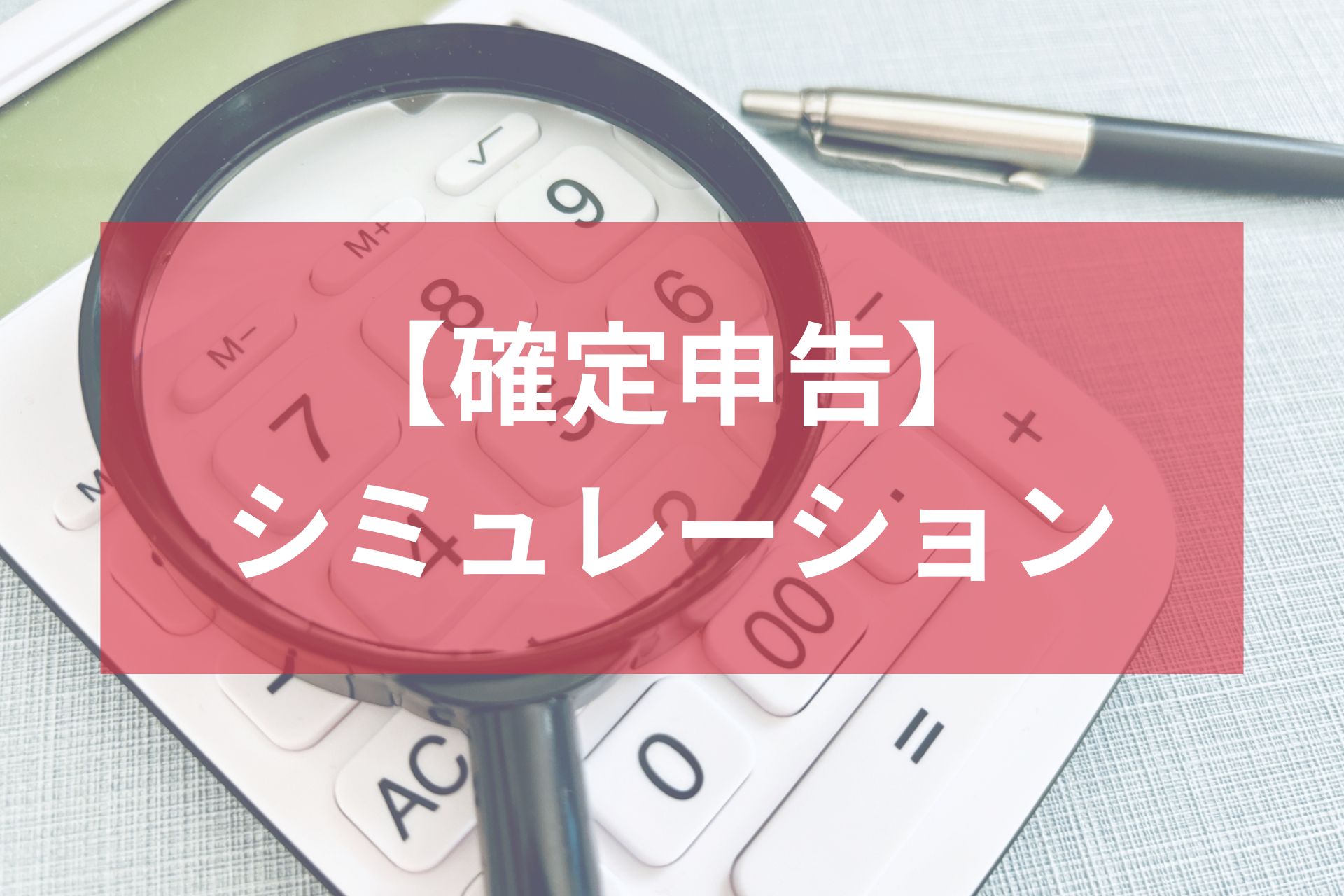
【確定申告】103万円の壁撤廃で何が変わる?経営者一家を例にシミュレーション
今回は仙台に在住の経営者一家のケースを例として、令和7年度の確定申告が具体的にどう変わるのか、その前の年と数字の面でどう変化するかを比較してご説明していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=gBqRGI7zhfQ 今回のペルソナ まず前提となるペルソナは以下です。 佐々木直人さん(仮)50歳 ・所在地:仙台市青葉区 ・家族構成: 妻48歳(パート年収160万円) 長男22歳(大学4年、年収125万円) 長女19歳(大学1年、年収125万円) ・職業:一人法人(エンジニア) ・役員報酬(年間):480万円 ・副業収入(年間):10万円 このモデルケースを使って具体的にどう変わるのかを説明していきます。 控除額シミュレーション このケースでは全体的には、ご主人に誰が扶養につくのかということとどれぐらい扶養の金額があるかということが今回変更点となります。 直人さんのケース(基礎控除) 前回基礎控除が引き上がった旨をお伝えいたしました。 基礎控除についての改正は以下の表の通りとなります。 佐々木直人さんはまずは基礎控除が昨年までであれば48万円でしたが、この令和7年度については68万円となります。 基礎控除が20万円上がるため、その分所得税が減ることになります。 妻のケース(配偶者特別控除) 次に奥様は、年収が160万円で昨年までの配偶者控除の計算をすると160万円から給与所得控除の55万円差し引いて105万円になります。105万円の場合、控除額が31万円となります。 今年の場合、給与所得控除の最低金額が10万円増え、65万円になります。 そのため、160万円−65万円=95万円となり、配偶者控除は38万円控除できるので、配偶者控除額は7万円上がるという形です。 妻のケース(基礎控除) 続いて奥様の基礎控除の金額は、今の給料の収入から給与所得控除を引いた金額で判定しますがそうすると95万円のため、先ほどの基礎控除の表を見ると、132万円以下の場合には95万円になるので、そうするとちょうど95万円引かれて所得が0となります。 つまり、奥様本人には課税されないことになります。 昨年だと奥様に少し所得が残り、直人さんは配偶者特別控除になって31万円の控除になっていたということです。 大学生の子どものケース(扶養控除・特定親族特別控除) 次は大学生のお子様で二人ともアルバイトをしていて年収が125万円の場合、昨年までであれば子どもたちは所得が出ているので扶養には入れません。 そのため、佐々木直人さんはお子さんたちを扶養に入れられないので扶養控除は0でした。今年はまず給与所得控除が65万円に上がったため、125万円−65万円=60万円で、60万円残っていますがこの金額を基準に令和7年は扶養控除の金額を決めていきます。 特定親族特別控除額についての表は以下となります。 先ほどの60万円を表に当てはめると扶養控除が1人につき63万円控除されるため、合計126万円その直人さんの収入から扶養控除として控除できるということになります。 ご本人たちの基礎控除も上がるため、132万円以下の所得の方は基礎控除が95万円になるので、このお二人も所得の金額が0となり、税金もかからないという形になります。 直人さんが控除できる金額 結果的に直人さんがどれほど控除が増えたかですが、以下の表の通りです。 改正前改正後差額妻31万円38万円7万円子ども0円126万円126万円合計31万円164万円133万円 奥様の分は昨年が配偶者の控除で31万円、今年は38万円になるのでまず7万円控除が増えます。 お子様2人の分は昨年までであれば0円ですが、今年は126万円控除が増え、126万円+7万円=133万円となり、133万円の控除が増えるということになります。 そうするとだいぶ税額としては変わってきます。 当てはまる方はご確認を! この改正のことをまだ知らない人もいらっしゃるかと思います。 年末調整の際なども今までのようにお子様が103万円を超えているから扶養から外していいというようなことではないケースになるため、注意しましょう。 気になられる方は奥様の収入や19歳から23歳のお子様の収入があるというご家庭の方は確定申告などの際などに聞いておかれると良いでしょう。 確定申告や年末調整が少し不安だという方は、是非弊社までお問い合わせください。 関連記事:2025年度(令和7年分)確定申告の変更点とは? 関連記事:仙台市で税理士に確定申告を依頼するならどう相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説
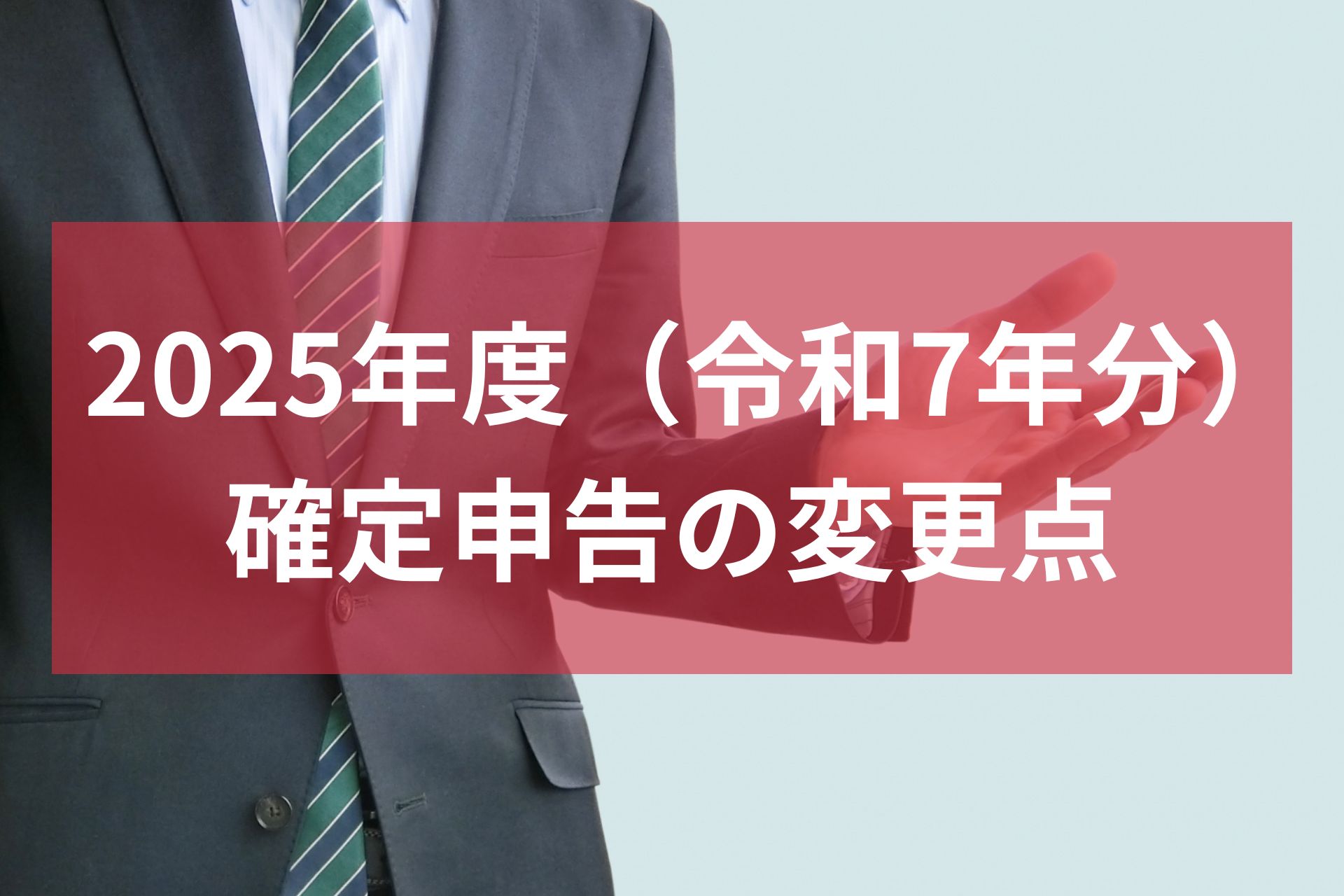
2025年度(令和7年分)確定申告の変更点とは?
今回は確定申告に関連して、2025年度で税制が変わったことに対して、何が変わったのかをお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=Hvq0ihyPRvY 令和7年分の確定申告の変更点 変更点は、昨年令和6〜7年にかけて103万円の壁、いわゆる扶養に入るかどうかの数字が上がった、つまり扶養に入れる方が増えたことが大きな改正です。 103万円の壁はそもそも何かというと、パートやアルバイトをしている方を前提にしていますが、給料をもらっている方は給料の金額がいくらであっても給与所得控除という給料の金額から税金の計算上マイナスできる金額が決まっています。今まではその最低金額が55万円でした。 その他に所得税を計算する際に収入の金額から差し引きできる基礎控除というどんな方でも控除する金額が48万円あり、55万円+48万=103万円という計算になっていました。 これが、まずこの基礎控除が引き上がること、そして、給与所得控除の金額も上がることとなります。 この2つに加えアルバイトをしている方で大学生あたりの年齢の方を扶養にする際に、その扶養の制度が少し広がったという改正となります。 基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除の3つが大きく変わったことです。 3つの改正点 基礎控除 基礎控除は一律48万円から、今年と来年度は大きく引き上がります。 具体的には所得の金額が132万円以下であれば、基礎控除が48万円だったのが95万円になります。 合計所得金額に応じた基礎控除の金額は以下の一覧となります。 このように収入が少ない人は減税されるという仕組みになっています。 令和7〜8年はこの体制ですが、それ以降は一律58万円という10万円プラスしたところで固定されます。 なぜ2年間だけ優遇されるのかというといろいろな事情があると思われますが、物価高などでそのような手当てをする必要があるということで基礎控除を一気に拡充して税金としての軽減を図ろうという意図かと思います。 給与所得控除 給与所得控除は給料の金額が上がるごとに控除額が上がっていきますが、最低金額が今まで55万円でしたが、基本的にこの最低金額が10万円引き上がるという改正です。 そのため、55万円が65万円になります。 それ以降は特に改正はされませんが、基本的にはパートの方々などに手当するようなイメージになるかと思います。これは会社員の方にも影響します。 特定親族特別控除 特定親族特別控除は年齢が19歳以上23歳未満の大学生世代の扶養控除について新しく拡充されたということです。 元々この年齢の範囲の方は控除額が多かったのですが、それにまたプラスして、アルバイトをしている人が今までは103万円を超えると扶養から外れてしまうという形になっていました。 それが控除額を超えて所得の金額が出てしまったとしても段階的に控除を受けられるような改正となります。 配偶者の方はすでにそのような形の控除の制度になっており、扶養の範囲を外れてもある程度の収入までは控除が段階的に減っていくけれども控除自体は受けられるというのが配偶者特別控除ですが、それと同じ形となります。 要するに大学生でもアルバイトをしやすいようにというところで、昨今の人材不足に対して働ける人が増えた方が良いという趣旨ではあります。 ただ一方で学生はアルバイトをすることが目的ではないと言う方もおり、いろいろ意見はあるようですが、趣旨としては働くことをセーブしないように少し広げたということです。 申告書類の変更点 この改正にあたり、確定申告での変更については、特定親族特別控除という欄が増えるわけではありませんが、一応計算方法が変わるため、そこを計算しなくてはいけません。 基礎控除の金額や給与所得控除の金額が変わることで申告書を記載する際にそのあたりはきちんと計算をしなければいけないという形になります。 確定申告に関するご相談はお早めに! 先ほどお伝えしたのは確定申告書の話ですが、年末調整でも同じで、年末調整の書類は本当はご自身で書いていただくことが原則ではあるのですが、なかなか難しいというのがあるかと思います。 ただ書いていただいてご提出いただければ、例えば金額が間違っていたとしても、もし税理士の方が年末調整を依頼してやってくれているということであれば直していただいたりなどもできるかと思います。 確定申告に不安がある方はぜひお早めに弊社にご相談ください。 関連記事:仙台市で税理士に確定申告を依頼するならどう相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説 関連記事:【確定申告】103万円の壁撤廃で何が変わる?経営者一家を例にシミュレーション
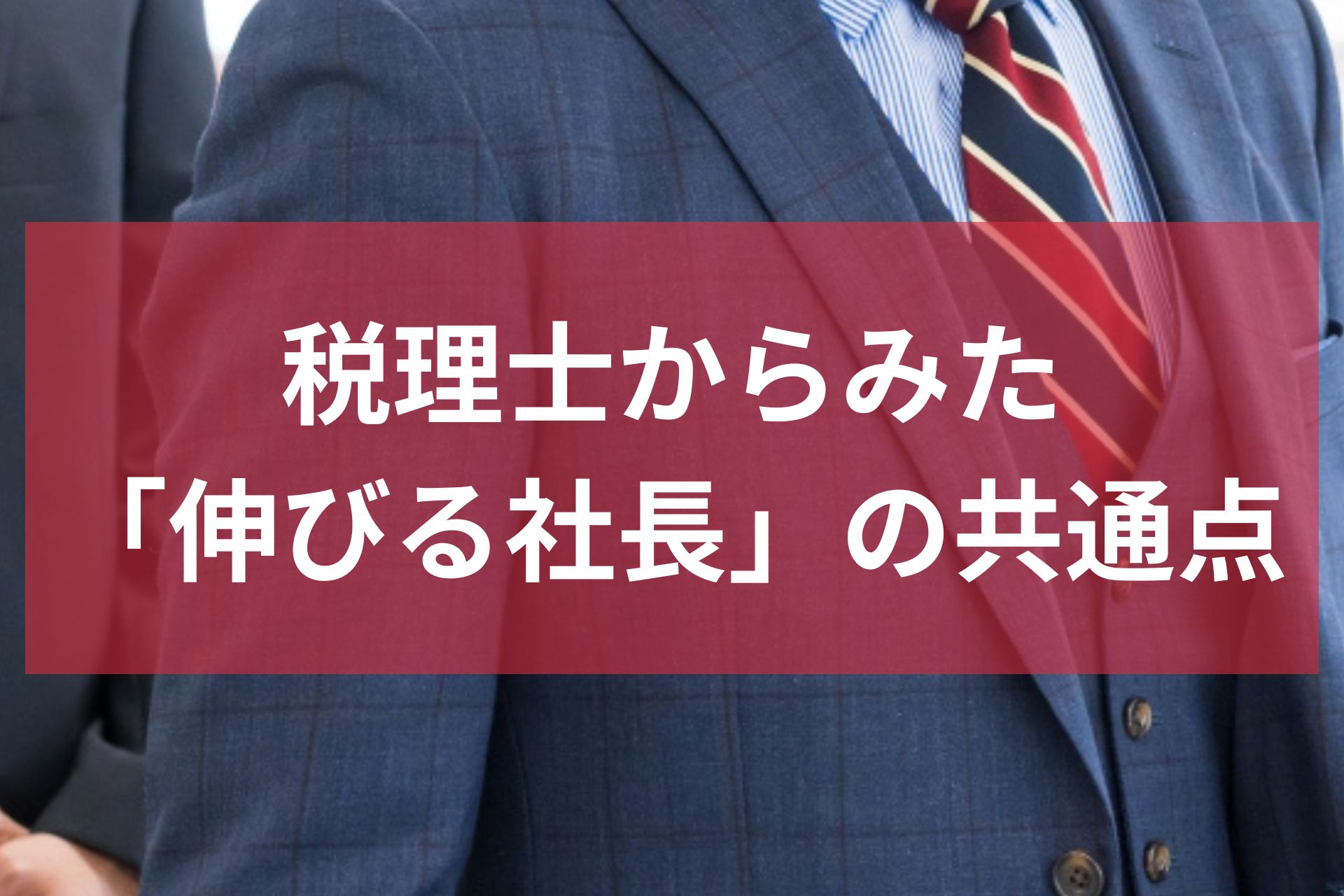
税理士からみた「伸びる社長」の共通点
今回は、税理士からみて「この会社伸びる!」と思った社長の特徴についてご紹介していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=qxB9dLOl0NE 伸びる社長の特徴とは 行動している人 端的に言うと「行動している人」です。 事業は、仕事を受注しなければ始まりませんので、とにかく行動ができなければ売上が上がりません。ただし、やみくもに行動するのではなく、数字やご自身なりの基準を持つことが大切です。例えば受注の際、これは受けないまたは受けられるなどの基準が挙げられます。数字的にも正しく意思決定できると会社としては伸びていきやすいでしょう。 行動に対する成果を正しく判断出来る人 行動に対する成果をきちんと判断することができるか、という点も重要です。 売上が上がっていても、赤字になっていたら意味がありません。売上に対してどの程度経費が掛かり、利幅がどの程度なのか、ということを正しく捉えた上で行動することが大切です。 実際に伸びた社長の話 今は顧問先ではないのですが、私たちがお手伝いしていた当時、売上が1億もいっていなかったところを、5年程で10億円弱ほどに伸ばした方もいらっしゃいます。その方はご自身で目標を立てて行動をされていた方でした。また、ご自身の会社の強みをきちんと認識されていました。自社の状況や強み、弱みなどを的確に認識できていれば、より効果的な行動(例えば、どこに対して営業すれば良いかなど)をすることができます。 また、この受注に対してこれほどの工数で行えば利益が出るなどがイメージでき、それが現実の損益とズレがなければ、売上が立った分、利益も残ります。 仕事に対する姿勢 成果が出るか、つまり仕事が取れるかどうかはご自身を信じて行動しているかで変わってきます。ご自身の状況を把握して、こうすればいける!というように計画を立てて、信じていると行動の端々に表れてきます。例えば営業マンの方でも売っているものが本当に良いと思ってるかそうでないかで、営業時の話し方や雰囲気が全然違うと思います。 ご自身のやっている仕事や、やっていることに対して信じているということは一番重要です。 その上でご自身のイメージしている数字と、実際の数字を見比べて、ご自身の感覚が現実の数字と合致しているか現状を把握することも大切です。そのためには数字を理解する必要があるため、ある程度の数字の勉強は必要かと思います。自分の感覚と数字が異なっている場合には、自分の感覚を修正することも必要です。信じるものもあるでしょうが、時には第三者の意見なども参考に、正しい方向に修正することも必要でしょう。 是非ご相談ください 今回は、税理士からみて「この会社伸びる!」と思う社長の共通点についてご紹介しました。仕事を取るために行動することはもちろんのこと、きちんとその成果、数字にも目を向けることが重要です。あまり数字には強くないという方は、顧問税理士にサポートを依頼することがおすすめです。 顧問税理士にサポートしてもらう中で、ご自身が必要な情報があれば出してもらうことがベストだと思います。顧問税理士と経営者の双方ですり合わせをしていくということが重要な点です。弊社でもご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。 関連記事:税理士必須な社長の特徴とは?顧問税理士選びのポイントも解説! 関連記事:黒字倒産しないためにやるべきこと 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説! 関連記事:黒字倒産の真実!利益とキャッシュがズレるわけとは? 関連記事:黒字倒産しないために経営者はどのような意識を持つべき?
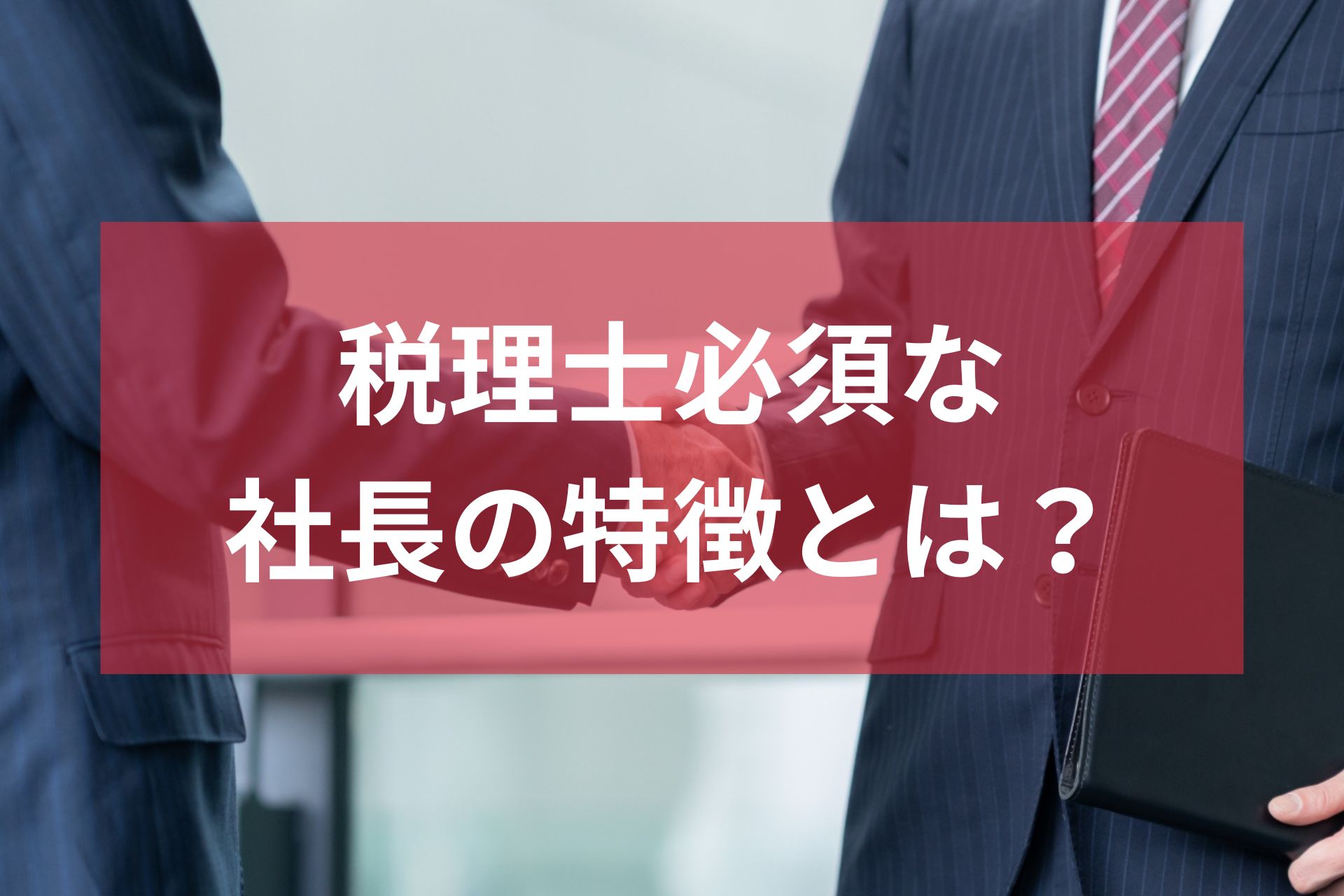
税理士必須な社長の特徴とは?顧問税理士選びのポイントも解説!
今回は、税理士と顧問契約を結ぶべき人の特徴などについてお伝えさせていただきます。 「今は顧問税理士がいないけれどこのまま大丈夫なのか」 「知らないうちに損をしているのではないか」 このような不安を感じている経営者の方は是非ご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=rl_Gdi9-Gwg 顧問税理士は必ず必要なのか? 結論からお伝えすると、全員が全員必要ということではないと思います。申告書の作り方や決算書の作り方が分かっていれば、ご自身でできるという方もいらっしゃるでしょう。ただ、大部分はできていても細かい部分で間違っている場合もあります。また、融資の際など、顧問税理士をつけていると、ある程度、「決算書の内容は正しいだろう」と銀行側で認識される、という側面も否めません。そのため、できる方はご自身でやっていただいて構いませんが、できれば顧問税理士をつけていただいた方が後々のためにはなるかと思います。 顧問税理士をつけた方が良い人の特徴 基本的には最初から顧問契約をしておくことをおすすめします。いくつか方法がある場合に、税金上こちらの方が有利になる、というようなことがありますが、税理士に相談せずにご自身でやっている場合、こういった事になかなか気付くことができず、後から相談した際にこうしておけば良かったとなるケースがあります。また、例えば源泉所得税の支払いなど、やらなくてはいけないものをやらずに、後から余計に税金を納付することになった、などのケースもあります。 また、本業が忙しく、会計帳簿の入力、領収書の整理などが億劫になり、溜まってしまう、という方もいらっしゃいます。そうなると手を付けにくくなり、最終的には何期か申告をできなかった、しなかったということが続いてしまうという事態になることもあります。そのような状況になって税理士に依頼をしてしまうと、料金が嵩んでしまったり、そもそも依頼を受けてくれなかったりということにもなりかねません。 会社規模によって顧問契約ができないことはある? 顧問契約が会社規模によってできないということはないでしょう。ただ、あまりにも小規模の場合は年1回で良いのではなどという話にはなるかと思いますが、基本的には月々で顧問契約していただいて、体制を整えていくというところからスタートとなります。 顧問料は売上によって変動する? 弊社の場合は、売上と消費税によって変えさせていただいています。それにプラスして記帳代行を行う場合は追加という形になります。毎月の記帳や経費計算などをご自身で行うことで費用の調整をすることも可能です。 税理士とのやり取りの頻度 基本的には資料を提出いただいて入力やチェックなどを行うため、定期的に資料を出してくださいというお願いはさせていただきます。その他、別途お打ち合わせ等が必要であれば、内容や頻度を確認の上、別途料金でお引き受けしております。 税理士選びはコミュニケーションの相性が重要 顧問税理士選びにおいて税理士の方とご自身の相性はとても重要です。税理士の方にも色々なタイプがあります。厳しく指導される方もいらっしゃれば、優しく指導される方もいらっしゃると思います。一般的には優しい方が良いかと思いますが、数字を基に打ち合わせをして事業拡大していきたい、という方は厳しい指導を受けた方が良いかもしれません。ご自身の状況や性格に合わせてお選びいただくのが良いかと思いますが、税理士とコミュニケーションを取りづらい、というようなことを感じている場合には、顧問税理士を変更するのも良いかもしれません。コミュニケーションスタイルがマッチする方を選ぶという視点は、非常に重要かと思います。 弊社もご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
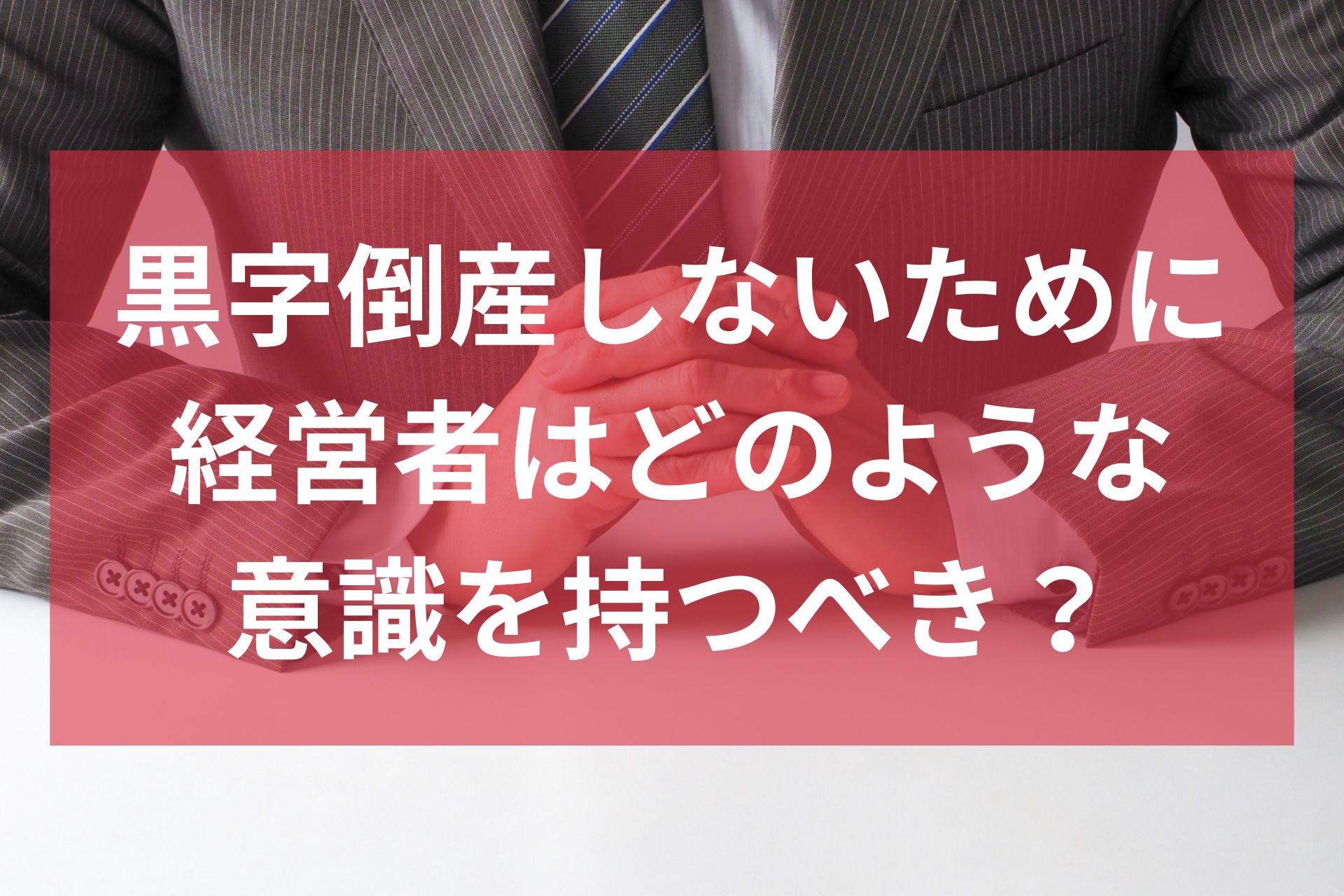
黒字倒産しないために経営者はどのような意識を持つべき?
前回の記事で黒字倒産しないためにやるべきこととしていくつかのポイントをお伝えさせていただきました。 今回は、前回の続きとして経営者はどのような意識を持つべきなのか、また注意すべきことについて解説いたします。 https://www.youtube.com/watch?v=kwa1DtOITGQ 通常の事業活動でどのような意識を持つべき? 資金繰りが悪化する要因は、商品や材料などのいわゆる棚卸資産の過剰在庫や売掛金の回収遅れなどが挙げられます。これら以外にも、土地取得など資金が固定化されやすい投資も注意が必要です。 貸借対照表の左側にある、現預金以外の資産については資産としての価値と実際の価値が異なることが多々あります。例えば土地などは、購入時の価格から今は価格が下がっている場合でも、原則として会計上は資産として購入時の金額が載っています。実際に売る時は下がった金額のため含み損になっているということになります。また、貸し倒れている売掛金があったとしても、貸し倒れが発生するまで分かりません。 一方で右側(負債)は、帳簿上の金額=将来返済すべき金額です。 つまり「資産は思ったほど価値がない一方で、負債は確実に返済が必要」というアンバランスが、資金繰り悪化の大きな要因になるのです。 過度な節税に注意する 税負担を軽くするための節税は大切ですが、必要以上に利益を圧縮する過度な節税をしてしまうと資金繰りを圧迫するケースに繋がります。 例えば利益が1,000万円出たとして、おおよそ3分の1の300万円ほど法人税を払うことになります。ただその法人税を払いたくないからといって、利益1,000万円で、1,000万円経費を出したとします。そうすると法人税は0になりますが、経費として払った1,000万円はキャッシュとして出ていきます。もし法人税を支払っていれば、700万円ほどは手元に現金が残っていたにも関わらず、1,000万円経費として出して節税をしたことによって税金は0ですが手元の資金も0になってしまいます。 必要な利益の考え方ですが、最低限必要な資金として借入の返済額は確保しなければいけません。税金を払った後の利益と減価償却費が年間の返済額以上になる(税引後利益+減価償却費≧年間の返済額)、少なくともそれまでは利益を出さないと毎年キャッシュが減っていってしまいます。 資金繰りに関する助言や指導もさせていただいています 今回は、黒字倒産しないために経営者として意識すべきことをお伝えしました。弊社は、資金繰りに関する助言や指導もさせていただいています。顧問先のお客様で売掛金が何ヶ月も入っていない取引先などがある場合は、「ここの取引先は大丈夫ですか」という声掛けや、売上規模はあまり増えていないにも関わらず在庫が増えている場合などは数値を見て分かるため、毎月の帳簿を見て、または決算時に昨年と比較し、お話をさせていただくこともあります。 また節税に関するお話もさせていただいています。基本的に私たちは全ての借入のあるお客様に返済計画表というものを作成させていただき、翌年の必要な利益に関するアドバイスなどを行っています。資金の計画と来年の設備投資の計画を事前に把握することは重要です。 何かご相談をお持ちの場合は弊社までお気軽にお問い合わせください。 関連記事:黒字倒産しないためにやるべきこと 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説! 関連記事:黒字倒産の真実!利益とキャッシュがズレるわけとは?