お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
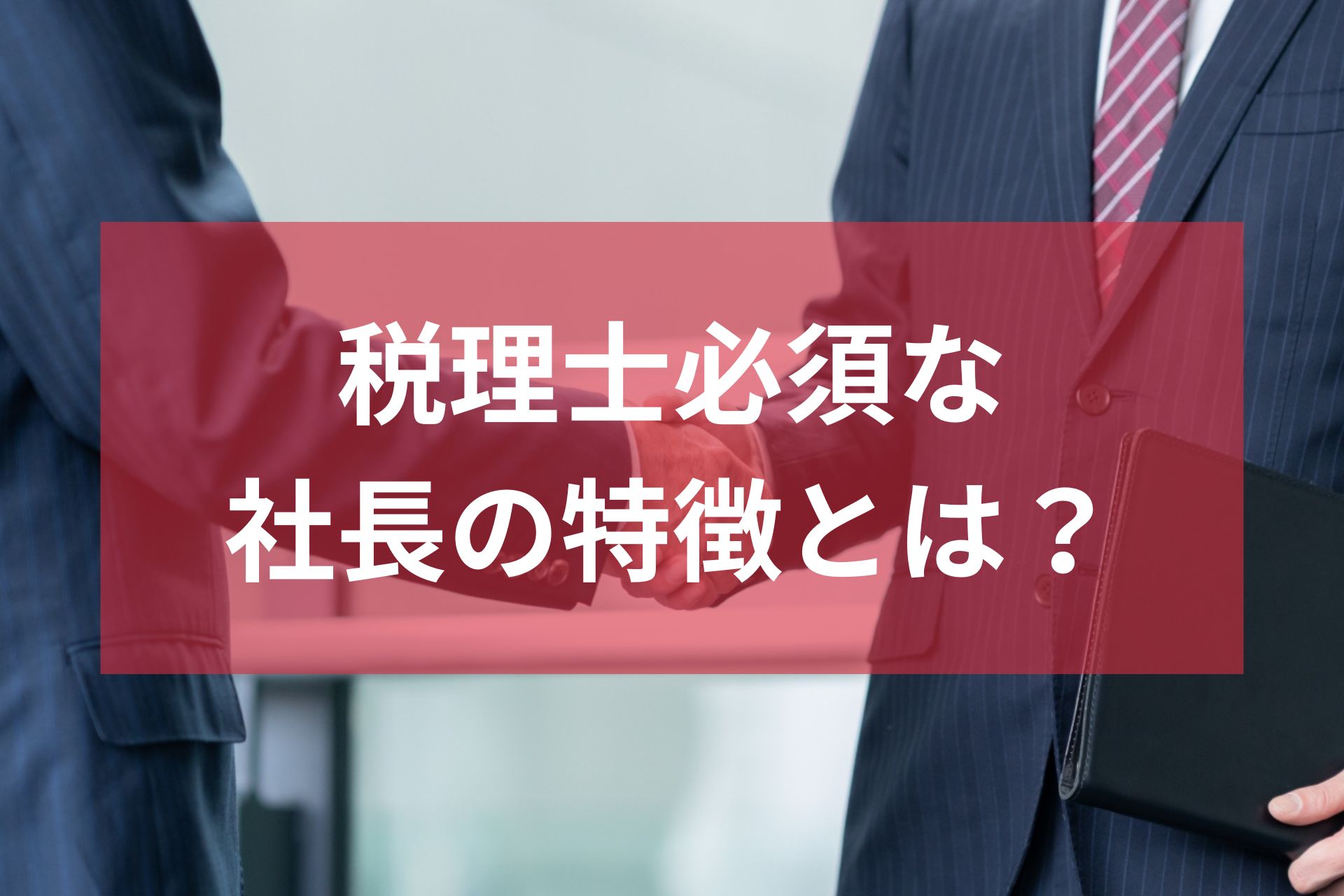
税理士必須な社長の特徴とは?顧問税理士選びのポイントも解説!
今回は、税理士と顧問契約を結ぶべき人の特徴などについてお伝えさせていただきます。 「今は顧問税理士がいないけれどこのまま大丈夫なのか」 「知らないうちに損をしているのではないか」 このような不安を感じている経営者の方は是非ご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=rl_Gdi9-Gwg 顧問税理士は必ず必要なのか? 結論からお伝えすると、全員が全員必要ということではないと思います。申告書の作り方や決算書の作り方が分かっていれば、ご自身でできるという方もいらっしゃるでしょう。ただ、大部分はできていても細かい部分で間違っている場合もあります。また、融資の際など、顧問税理士をつけていると、ある程度、「決算書の内容は正しいだろう」と銀行側で認識される、という側面も否めません。そのため、できる方はご自身でやっていただいて構いませんが、できれば顧問税理士をつけていただいた方が後々のためにはなるかと思います。 顧問税理士をつけた方が良い人の特徴 基本的には最初から顧問契約をしておくことをおすすめします。いくつか方法がある場合に、税金上こちらの方が有利になる、というようなことがありますが、税理士に相談せずにご自身でやっている場合、こういった事になかなか気付くことができず、後から相談した際にこうしておけば良かったとなるケースがあります。また、例えば源泉所得税の支払いなど、やらなくてはいけないものをやらずに、後から余計に税金を納付することになった、などのケースもあります。 また、本業が忙しく、会計帳簿の入力、領収書の整理などが億劫になり、溜まってしまう、という方もいらっしゃいます。そうなると手を付けにくくなり、最終的には何期か申告をできなかった、しなかったということが続いてしまうという事態になることもあります。そのような状況になって税理士に依頼をしてしまうと、料金が嵩んでしまったり、そもそも依頼を受けてくれなかったりということにもなりかねません。 会社規模によって顧問契約ができないことはある? 顧問契約が会社規模によってできないということはないでしょう。ただ、あまりにも小規模の場合は年1回で良いのではなどという話にはなるかと思いますが、基本的には月々で顧問契約していただいて、体制を整えていくというところからスタートとなります。 顧問料は売上によって変動する? 弊社の場合は、売上と消費税によって変えさせていただいています。それにプラスして記帳代行を行う場合は追加という形になります。毎月の記帳や経費計算などをご自身で行うことで費用の調整をすることも可能です。 税理士とのやり取りの頻度 基本的には資料を提出いただいて入力やチェックなどを行うため、定期的に資料を出してくださいというお願いはさせていただきます。その他、別途お打ち合わせ等が必要であれば、内容や頻度を確認の上、別途料金でお引き受けしております。 税理士選びはコミュニケーションの相性が重要 顧問税理士選びにおいて税理士の方とご自身の相性はとても重要です。税理士の方にも色々なタイプがあります。厳しく指導される方もいらっしゃれば、優しく指導される方もいらっしゃると思います。一般的には優しい方が良いかと思いますが、数字を基に打ち合わせをして事業拡大していきたい、という方は厳しい指導を受けた方が良いかもしれません。ご自身の状況や性格に合わせてお選びいただくのが良いかと思いますが、税理士とコミュニケーションを取りづらい、というようなことを感じている場合には、顧問税理士を変更するのも良いかもしれません。コミュニケーションスタイルがマッチする方を選ぶという視点は、非常に重要かと思います。 弊社もご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
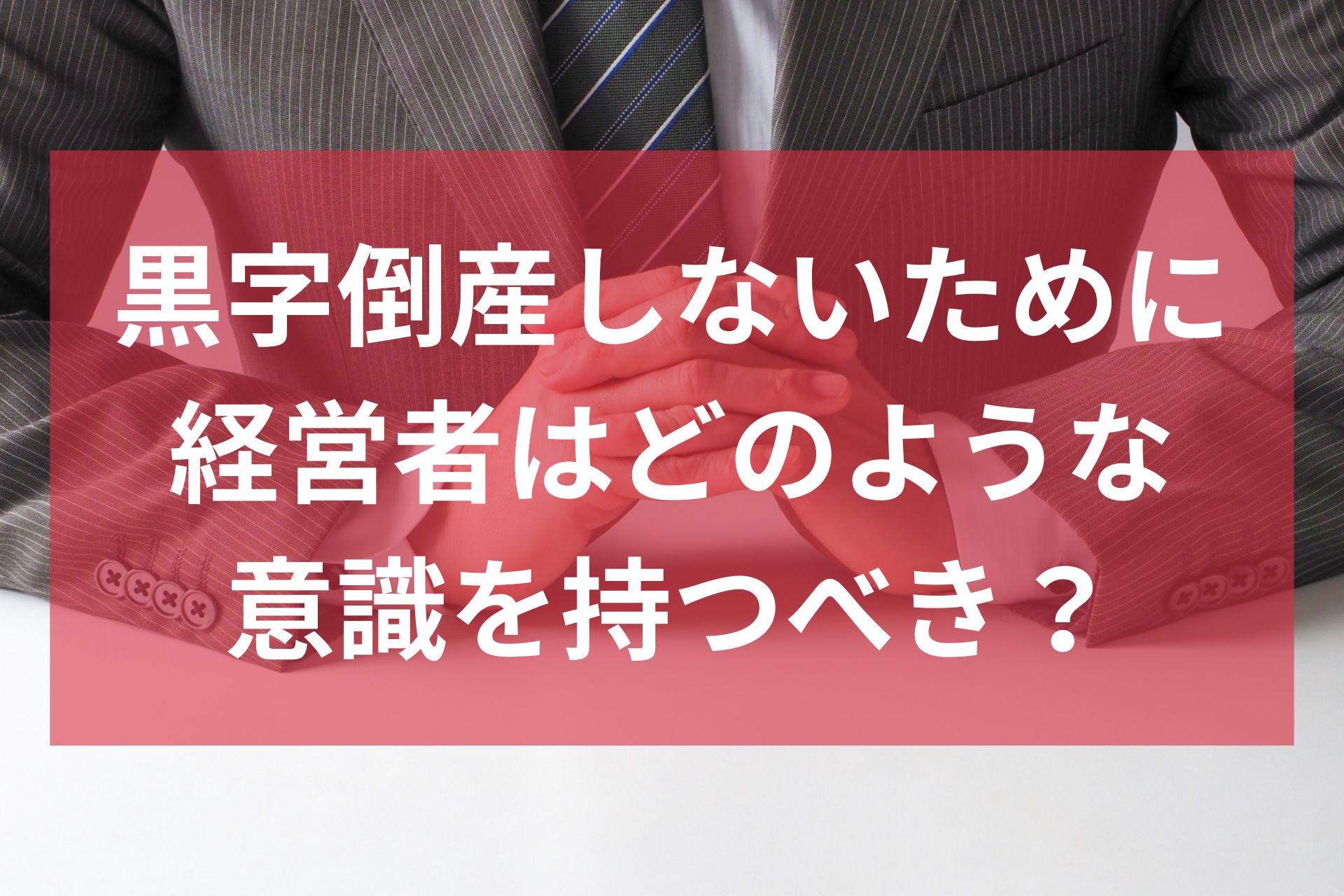
黒字倒産しないために経営者はどのような意識を持つべき?
前回の記事で黒字倒産しないためにやるべきこととしていくつかのポイントをお伝えさせていただきました。 今回は、前回の続きとして経営者はどのような意識を持つべきなのか、また注意すべきことについて解説いたします。 https://www.youtube.com/watch?v=kwa1DtOITGQ 通常の事業活動でどのような意識を持つべき? 資金繰りが悪化する要因は、商品や材料などのいわゆる棚卸資産の過剰在庫や売掛金の回収遅れなどが挙げられます。これら以外にも、土地取得など資金が固定化されやすい投資も注意が必要です。 貸借対照表の左側にある、現預金以外の資産については資産としての価値と実際の価値が異なることが多々あります。例えば土地などは、購入時の価格から今は価格が下がっている場合でも、原則として会計上は資産として購入時の金額が載っています。実際に売る時は下がった金額のため含み損になっているということになります。また、貸し倒れている売掛金があったとしても、貸し倒れが発生するまで分かりません。 一方で右側(負債)は、帳簿上の金額=将来返済すべき金額です。 つまり「資産は思ったほど価値がない一方で、負債は確実に返済が必要」というアンバランスが、資金繰り悪化の大きな要因になるのです。 過度な節税に注意する 税負担を軽くするための節税は大切ですが、必要以上に利益を圧縮する過度な節税をしてしまうと資金繰りを圧迫するケースに繋がります。 例えば利益が1,000万円出たとして、おおよそ3分の1の300万円ほど法人税を払うことになります。ただその法人税を払いたくないからといって、利益1,000万円で、1,000万円経費を出したとします。そうすると法人税は0になりますが、経費として払った1,000万円はキャッシュとして出ていきます。もし法人税を支払っていれば、700万円ほどは手元に現金が残っていたにも関わらず、1,000万円経費として出して節税をしたことによって税金は0ですが手元の資金も0になってしまいます。 必要な利益の考え方ですが、最低限必要な資金として借入の返済額は確保しなければいけません。税金を払った後の利益と減価償却費が年間の返済額以上になる(税引後利益+減価償却費≧年間の返済額)、少なくともそれまでは利益を出さないと毎年キャッシュが減っていってしまいます。 資金繰りに関する助言や指導もさせていただいています 今回は、黒字倒産しないために経営者として意識すべきことをお伝えしました。弊社は、資金繰りに関する助言や指導もさせていただいています。顧問先のお客様で売掛金が何ヶ月も入っていない取引先などがある場合は、「ここの取引先は大丈夫ですか」という声掛けや、売上規模はあまり増えていないにも関わらず在庫が増えている場合などは数値を見て分かるため、毎月の帳簿を見て、または決算時に昨年と比較し、お話をさせていただくこともあります。 また節税に関するお話もさせていただいています。基本的に私たちは全ての借入のあるお客様に返済計画表というものを作成させていただき、翌年の必要な利益に関するアドバイスなどを行っています。資金の計画と来年の設備投資の計画を事前に把握することは重要です。 何かご相談をお持ちの場合は弊社までお気軽にお問い合わせください。 関連記事:黒字倒産しないためにやるべきこと 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説! 関連記事:黒字倒産の真実!利益とキャッシュがズレるわけとは?
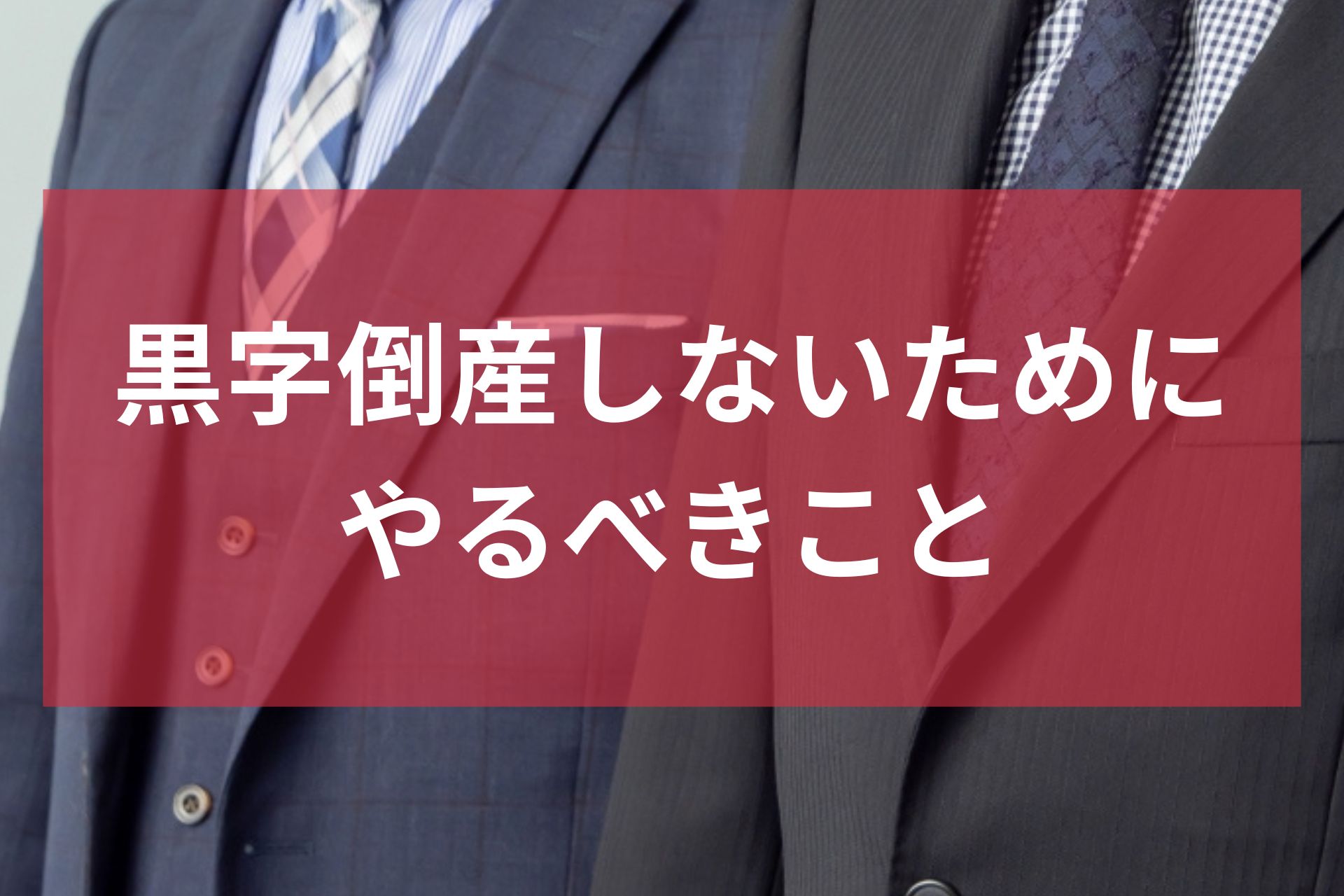
黒字倒産しないためにやるべきこと
過去の記事で「利益が上がっているのに現金が減っていく原因」について解説いたしました。今回は黒字倒産しないためにやるべきことについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=IMiHXGrJS5o 会社経営における現金を残すことの重要性 会社経営において、利益を上げることは重要な要素です。ただ、黒字倒産のリスクという観点では、利益よりもキャッシュ(現金)の確保が優先されます。 金融機関の融資判断には、会計上のいわゆる利益というのは欠かせません。資金繰りを良くする中で銀行融資は必要になりますので、全く利益を上げなくて良いというわけではありません。また、最終的に利益とキャッシュは直接は一致しませんが、キャッシュを増加させる一因であることも間違いありません。 ただ、利益とキャッシュは一致しないケースが多いため、利益がマイナスになってもキャッシュがプラスであれば即倒産とはなりません。しかし、利益のプラスマイナスに関わらずキャッシュがマイナスになると倒産ということになってしまうため、会社の存続のためにはキャッシュは重要ということが言えます。 黒字倒産しないためにやるべきこと 資金繰り表の作成・運用 黒字倒産しないためにやるべきこととして、まず資金繰り表を作成し実際に使ってみるということが挙げられます。 実際にいついくら入金になっていくら出金があるかというような管理表のことを資金繰り表といいます。これは税務申告の際に税務署に提出するようないわゆる決算報告書とは異なり、経営のためだけに作るものになります。そのため、会社によっては作成していないケースもあるかと思います。資金繰り表に決まったフォーマットはないため、インターネットで検索して出てくるひな形をご自身が使いやすいように変更して使用してみても良いでしょう。 会社や業種ごとに資金の流れは大きく変わるため、ご自身の会社の資金繰りの特徴を意識するとキャッシュで苦労することは減ると言えるでしょう。 売掛金の回収を早める 取引先との関係もあるため、容易なことではないかもしれませんが、売掛金の回収を早める努力も黒字倒産しないために重要です。現預金以外の資産を減らすと現金が増えるという考え方に基づくもので、資金繰りにマイナスになる資産を減らすことでキャッシュを増やすという考え方です。 また、売掛金の回収を早めるのと同じ効果があるものとして、前受金をもらうということも挙げられます。前受金をもらうことで資金繰りをよくすることも大変有効な手段となります。建設業などは前受金をもらうことで資金繰りを改善しているケースも多いのではないかと思います。 買掛金などの支払いを遅らせる 負債の支払いを遅らせるということも手段の一つとして挙げられます。買掛金や未払金などの負債の減少を遅らせるという考え方になります。負債は減少すればするほどキャッシュにはマイナスになっていきます。例えば銀行口座振替になっている電気料や各種経費の支払いをクレジットカード払いに変更し、1〜2ヶ月ほど未払金の支払いを遅らせるということで、2ヶ月ほど資金繰りが良くなるという効果があります。 在庫管理の適正化 在庫管理をしっかりするということも重要なポイントです。過剰在庫は資産の増加になるためキャッシュフローの悪化に繋がります。古くなってしまったり、不良化して使えなくなってしまったりで、将来販売できずに利益を生じるどころか損失となるケースとなる可能性があります。通常の営業活動のための在庫はもちろん必要ですが、過剰な在庫を持たないよう、きちんと管理しましょう。 金融機関との関係強化 経営者にしかできない大切な取り組みが、金融機関との関連性を強化することです。ご自身の会社の特性に応じて、運転資金を確保できるような金融機関を確保するということは、経営をしていく上で非常に大切です。 運転資金は以下のように求めます。 売上債権+棚卸資産−仕入債務 例えば、銀行に「運転資金を貸してほしい」と言った時に、運転資金はいくらか聞かれた場合、1ヶ月の「売上債権+棚卸資産−仕入債務」の金額の3ヶ月分借りたいとなると明確な数字が出てくるはずです。 運転資金の3〜6ヶ月分ほどの資金は持っておいた方が良いでしょう。 資金繰りに関するご相談もお任せください 今回は、黒字倒産しないためにやるべきことについてお伝えしました。 重要なのは、経営者ご自身が資金繰りに関する知識を深めて常に会社の資金の状況を把握し、早期に問題を解決することです。販売だけでなく、回収までしっかり管理することがキャッシュを十分に確保するために大切です。 弊社は資金繰りに関するご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。 関連記事:黒字倒産の真実!利益とキャッシュがズレるわけとは? 関連記事:利益=お金ではない!?会社のお金が減る仕組みを解説! 関連記事:黒字倒産しないために経営者はどのような意識を持つべき?
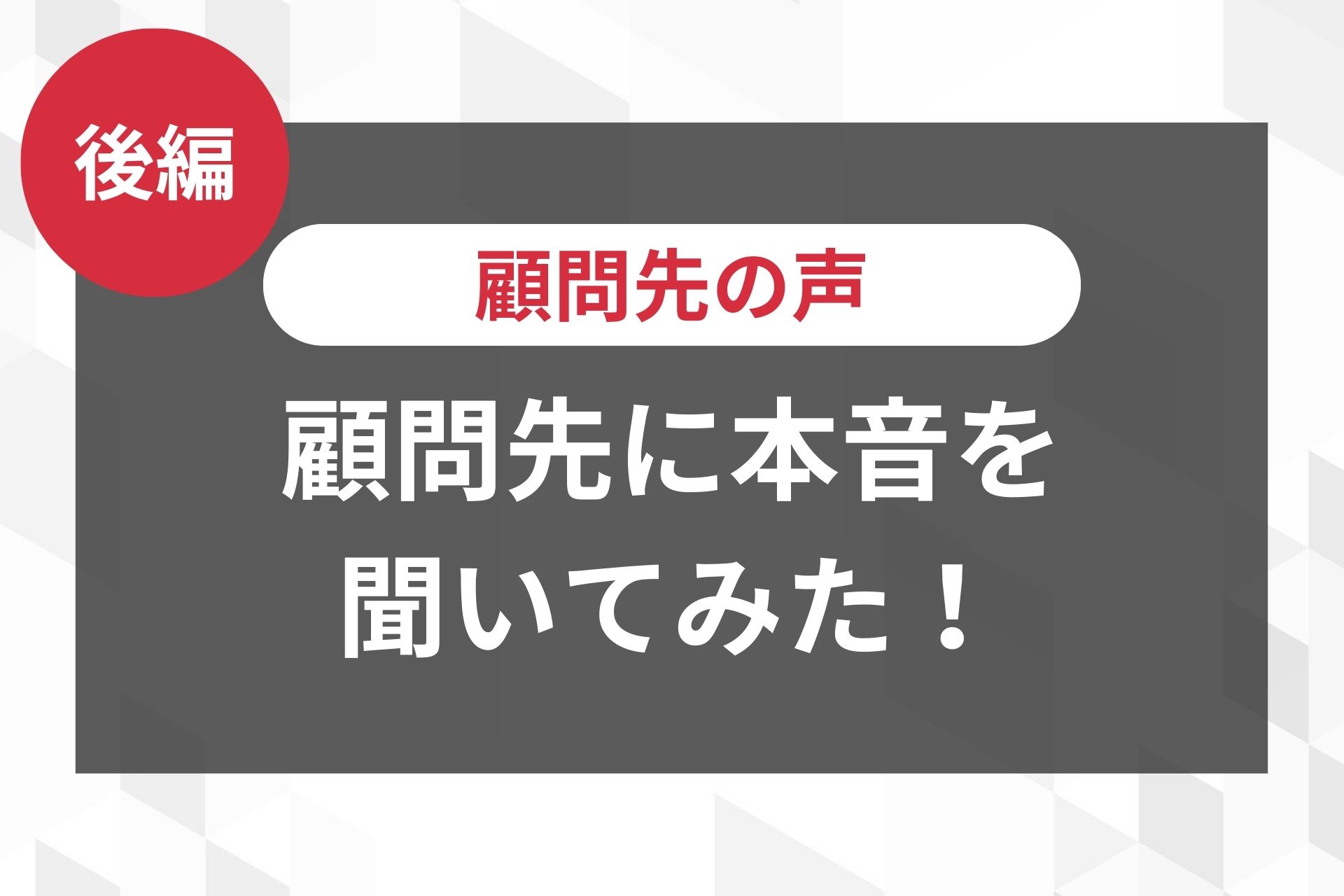
【顧問先の声】顧問先に本音を聞いてみた!(後編)
今回も前回に引き続き、プロゲート仙台オフィスの顧問先である「みうらのぽてと」の三浦来喜さんにお話を伺っていきます。今回も前回同様に顧問税理士としてどうかということを率直にお話いただきたいと思います。 今三浦さんは仙台市でキッチンカーの「みうらのぽてと」を運営されていて税務顧問をプロゲートに依頼されています。 https://www.youtube.com/watch?v=XzNY_kvJfiE 具体的な依頼内容 具体的にどんな業務をご依頼されているのですか? 三浦さん: プロゲートでは菅原先生に税務のことを全て見ていただいていますし、あと社労士にもお世話になっています。やっぱり社労士がやってくれる手続きを前は自分でやっていたのですがとても大変でした。プロゲートに社労士がいるということで、税理士と一緒に依頼しています。 菅原先生: 領収書をお預かりして記帳の代行や税務相談を行ったり、社労士は給与計算や雇用保険・社会保険の手続きを行っています。 税理士とのやりとりの頻度 やりとりはどれくらいの頻度で行っていますか? 三浦さん: 税務上の書類などは月1で持って行って、それを見て打ち合わせなどもします。あとは悩みや困ったことがあったら随時電話で話したり、ご飯に行って直接話したり、プロゲートの事務所に行って話したり、結構密に連絡は取っています。僕が事務所に訪問する形が一番多いです。 また、難しい書類などは社労士と菅原先生とのアプリがあるのでそれに送って双方の意見をもらって、やりとりしています。 菅原先生が顧問税理士で助かったという局面は? 三浦さん: 助かってばっかりですけどね。 菅原先生: ありがとうございます。 三浦さん: まず困ったことがないですね。全部助かっています。 僕も随時相談するようにはしているので、困ったことは今パッと思い浮かばないくらいスムーズにやりとりもできています。 菅原先生: 困る前に都度ご連絡していただくので、こういうふうにしようなど事前の打ち合わせなどをさせていただき、こちらも助かっています。 なかなか連絡が取れない顧問先の場合は対応されていますか? 菅原先生: 都度ご連絡いただく場合には色々お話させていただくのですが、ご連絡があまりないという場合は、こちらからあまりしつこくお話してもというところはあるので必要に応じてという形で対応させていただきます。 必要書類をなかなか送っていただけない場合などは送っていただけない原因などを解消しましょうというようなお話は都度させていただいています。 話やすさ、連絡のしやすさはとても大事ですね 三浦さん: これはとても大事だと思います。僕の場合は同級生でもあるし、高校からの知り合いでもあるので連絡しやすいですが、話にくい税理士さんや連絡しにくい税理士さんもいると思うんですけど、そういうふうになると正直やりにくくなってしまうので、僕は今の現状でそれは全く感じていないです。 やっぱり人と人なので、一番大事だと思います。なので僕が菅原先生にお世話になってから、僕の後輩とかにも紹介したくなるし、実際契約もしています。 周りに困っている経営者がいたときに紹介しやすいですよ。 仙台市は若い起業家が多い? 仙台市は起業される方で若い方は多いのですか? 菅原先生: 仙台市としてもスタートアップということで力を入れて後押ししている分野でもありますので比較的若い方は多いんじゃないかと思います。 顧問税理士として改善してほしいところは? 顧問税理士として菅原先生に改善してほしいところはありますか? 三浦さん: ほんとお世辞じゃなくないですね。それは友達とか関係なくゼロで、プロゲートの事務所にも別に改善してほしいところもないですし、全部早め早めに打ち合わせもしていただけますし、連絡して返ってくるスピードも早いです。レスポンスがとてもいい事務所だなと思います。 本当に怪我だけはしないようにしてほしいです(笑) (※菅原先生の負傷歴は前回の記事をご覧ください) 菅原先生から見た三浦さん 三浦さんはお仕事がしやすい顧問先の方ですか? 菅原先生: 話もよく聞いてくださいますし、考え方もしっかりしていらっしゃるので本当にすごいなと思いながら日々お話を伺っています。 やっぱり上を目指す意識が強いので、私にはない発想だというか「気合い入っているな」と関心したり、自分も頑張らなきゃと思ったり、そういう影響も受けています。 お気軽にご相談ください 前編と後編に渡って顧問先の声ということで三浦さんにお話をお伺いしてきました。 ご相談はお気軽に弊社までご連絡ください。 今回お話をお伺いした三浦さんのお店「みうらのぽてと」にも仙台市の方、お近くの方は是非お立ち寄りください。 関連記事:【顧問先の声】なぜプロゲートに依頼した?(前編) 関連記事:【顧問先の声】税務顧問を依頼したきっかけは?(前編) 関連記事:【顧問先の声】税理士としてどう?(後編)
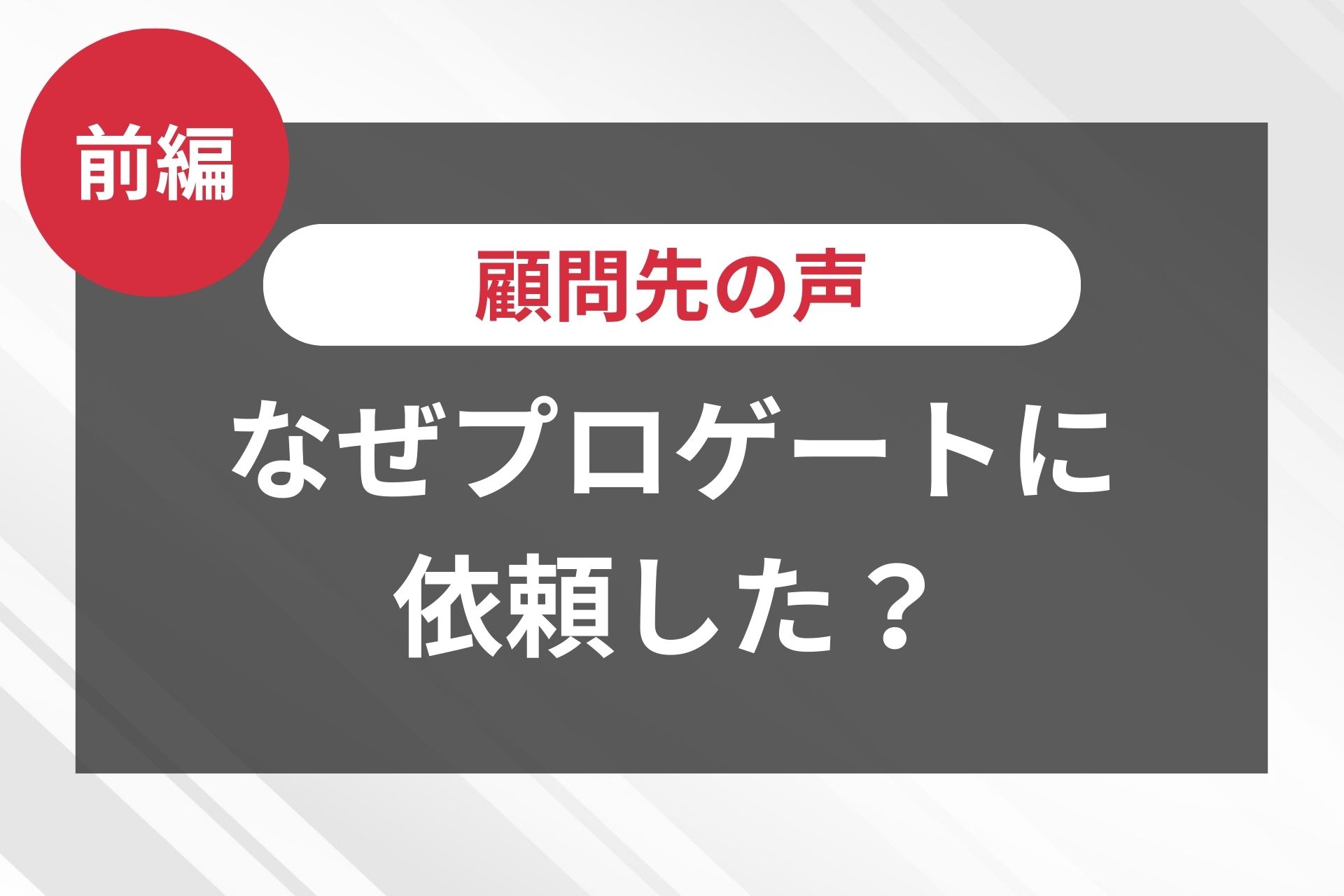
【顧問先の声】なぜプロゲートに依頼した?(前編)
今回は、プロゲート仙台オフィスの顧問先である、「みうらのぽてと」の三浦来喜さんにお話を伺っていきます。実際に顧問先のお客様の率直な声をお聞きしていきたいと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=eVahXKmT4Gs 自己紹介 簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか? 三浦さん: 私は2021年から法人を立ち上げ、飲食店の経営をしておりました。 最初の1年くらいは違う税理士さんにお願いしていたのですが、2,3年目くらいから高校の同級生でもある菅原先生のところに依頼をして、今は4期目を迎えました。 仙台市若林区に店舗とキッチンカーが2台あり、今はキッチンカーのみで営業を行っています。 ポテトはもちろん、チキン、フランク、ハンバーガーなどを主にトッピングでつけられる商品になっています。また、生地に宮城県産の米粉を100%使用したバブルワッフルというスイーツもあります。このスイーツとポテトを主に販売しています。 お客様は若い方が多いのですか? 三浦さん: そうですね。 20代〜40代までのお客様が主に90%ほどを占めています。 出店される場所は決まっていますか? 三浦さん: 大体スーパーに出店しています。12時から大体18時〜19時まで出店していますが、ポテトはお昼ご飯でも、3時のおやつでも、夕飯のおかずでも食べられますし、お酒を飲む方はおつまみとしても購入いただくことも多いです。 食べ物を買うというお客様の思考がスーパーだと多いので、スーパーに出店するようにしています。 その許可なども申請しなければいけないということですよね? 三浦さん: そうですね。 あとはインスタグラムのDMで誘っていただくことも多いです。 税理士を変更したきっかけとは 顧問税理士をプロゲート(菅原先生)に変更されたきっかけは? 三浦さん: 高校の時はお互い認知はあったのですが、仲良く喋る間柄ではありませんでした。ただある時、うちの店に来てくれてそこで色々話ていくうちにやっぱり話しやすさや相談のしやすさもあったので、結構すぐに税理士さんを変更しました。以前の税理士さんも良い税理士さんでしたし、何か不満があったわけではなかったのですが、それよりもやっぱり同級生ですし親身になって話を聞いてくれたりなどもあったので菅原先生にしました。プロゲートさんと契約する前にも食事に数回行って仲も深めあって、その後すぐに契約しました。 菅原先生の素顔とは 友人だからこその菅原先生の良いところやエピソードは? 三浦さん: 良いところはやっぱり人柄です。 税理士さんって同じ免許を持っている中でどうやって違いを出せるかというと人柄が一番だと思うので、そこはやはり群を抜いて素晴らしいと思います。 また、高校の時から、税理士さんって簿記が必要ですが、学年でもトップクラスでしたし、同じクラスではなかったのですが簿記ですごい人がいるっていうことを聞いていました。 なので、人柄と簿記の凄さを合わせたら、最高の税理士さんかなと思います。 菅原先生のここはちょっと心配だなと思う部分はありますか? 三浦さん: 心配なところは特にないんですが、(菅原先生は)怪我しがちなんですよ。趣味でマラソンをやっているみたいなのですが、足を折ったり、最近では指を折ったりして会うたびにどこか折れているというところぐらいですかね(笑) 菅原先生: 今も絶賛骨折中です(笑) 三浦さん: お互い野球もやってたんですよ。 菅原先生: 野球をやめた理由も怪我です(笑) お二人は野球部で一緒だったとかではないんですか? 三浦さん: 僕は野球部でした。菅原先生は高1の時に大怪我をしたので、、 菅原先生: 軟式野球部と硬式野球部だったんですよ。私は軟式野球部に入って、半月板を損傷して辞めてしまいました。すぐに辞めた結果、部活で簿記をやって今に繋がっています。 菅原先生が税理士になられたきっかけは? 菅原先生: 先ほどもお伝えした通り、部活で簿記をやっていたんですけれども、3年生の時に進路をどうしようと考えた時に就職しようかなと思っていたんですが、日商簿記1級を取ると専門学校の学費が2年間無料という噂を聞いて、「もうこれでいくしかない」と日商簿記1級をとって進学しました。 そこから専門学校に行って、公認会計市か税理士かどちらがいいですかと聞かれ、公認会計士の方は真面目そうな人が多く、税理士の方が面白そうだなと思い税理士を選びました。 そのクラスがってことですね。 たまたま私は日商簿記1級を取って入ったので1つ上のクラスに入れられたんですが、たまたまそのクラスの人たちがユニークな人たち多く、それで税理士の勉強を始めることになりました。だから色々な偶然が重なって税理士を目指し始めたという感じです。 菅原先生の学校のエピソードは? 菅原先生: 私は勉強している時間よりも専門学校の時は寝ていた時間の方が多いんですよ。 「何をしに来てるんだ!」とよく怒られて、その後心を入れ替えて真面目に勉強し始めました。 次回もお楽しみに! 色々お話いただきありがとうございました。 今回は菅原先生の人柄や過去のエピソードやキャリアなどもお伺いできましたので、次回は顧問税理士としてどう思われているのかということを三浦さんにまたお聞きしたいなと思います。 関連記事:【顧問先の声】顧問先に本音を聞いてみた!(後編) 関連記事:【顧問先の声】税務顧問を依頼したきっかけは?(前編) 関連記事:【顧問先の声】税理士としてどう?(後編)