お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
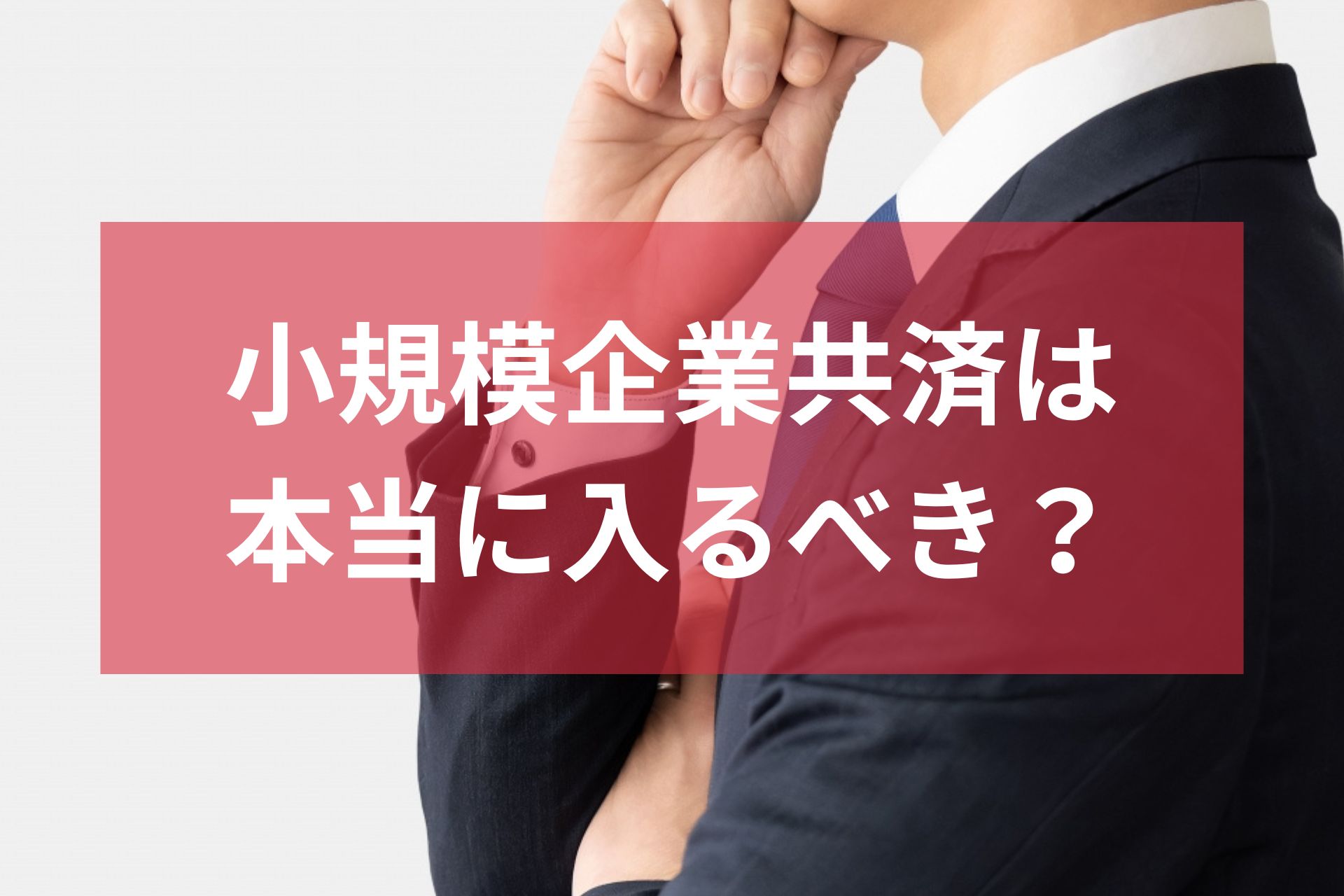
小規模企業共済は本当に入るべき?
独立して間もない方であれば、検討されている方も多いかと思われる小規模企業共済について解説をしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=qsSamKu8oHM 小規模企業共済とは? 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が退職後に備えて積み立てることができる制度のことです。掛金を積み立てていき、事業や会社を辞める時などに個人で退職金をもらうことができます。詳しくは以下で説明していきます。 中小機構|小規模企業共済 税制優遇 この制度は掛金の全額が所得控除の金額になります。またそれに加えて、受取時には退職所得という所得区分になるため、税制優遇される計算の仕方になります。つまり、支払い時には払った分の掛金が全て控除されて、実際に受け取る時には退職所得となり税金が少ない形で計算されるため、税金の観点からいうと、非常に有利と言えるでしょう。 掛金に応じた融資 掛金に応じて個人で借り入れをすることが可能です。借り入れの内容も様々あり、内容に応じて金額は異なりますが、掛けておくことでいざという時にお金を借りることができるのです。 貸付には種類があり、大きく分けて一般貸付と特別貸付に分けられます。一般の貸付は掛金の範囲内、おおよそ今まで掛けた金額の7〜9割ほどで、掛金に応じて借入できる金額が決まっています。金額の範囲は10万円以上2,000万円以下の範囲で貸付を受けることが可能です。利率は1.5%となります。また加入期間が1年以上という条件があります。 その他にも種類があり、例えば事業承継をする際や病気になった際などの特殊なケースの場合にも貸付を受けることができます。その場合は利率が低いなど条件が良くなります。こちらも同じく掛金の7〜9割前後で、50万円〜1,000万円までの融資の金額で、利率は0.9%となります。 自由度の高い掛金額 掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で自由に設定することができます。加入後に掛金の増減も可能です。 小規模企業共済はあくまでも個人に対する制度であり、個人の所得税の確定申告で所得控除できることになります。 制度の加入資格 サービス業の宿泊業や娯楽業、建設業、製造業などに関しては、従業員数20人以下、それ以外のサービス業や小売業などは5人以下という条件があります。 もし、従業員数が5人以下の時に加入をして、その後従業員が増えて50人ほどの規模になったとしても加入時に小規模であるためこの制度を続けることが可能となります。 また、会社を2社経営していて、1つの会社は加入条件を満たしているけれども、もう1つが規模がとても大きい会社の場合で加入条件を満たしていないという場合には、加入することができません。これは経営者ではなく役員として入っている場合も同様です。 途中解約はできる? 途中で解約することは可能です。ただ、納付年数が20年未満で解約をした場合には、元本割れをしてしまうので注意しましょう。元々、退職金という観点で制度設計されているため、途中の解約というのが考慮されていません。そのため長い期間で加入するということが前提となります。 制度利用の重要性 ここまでの話でいくと、事業を始める時にそもそも退職金を考える人はいるのかと思われるかもしれません。基本的には事業が軌道に乗って、ある程度継続できるとなった時に初めて退職金はどうするのか検討される場合が多いかと思います。そのため、最初から入ること自体悪いことではありませんが、無理して掛金をかけることはしない方が良いでしょう。 制度を始められた際には、ご自身の状況によって掛金を増減させて継続していくことをおすすめします。 中小企業倒産防止共済との比較 中小企業倒産防止共済は、戻ってくる時には税制優遇などはなく収入として入ってきます。それに対して小規模企業共済は、退職金として入ってくることにメリットがあると言えるでしょう。例えば、20年掛けて戻ってくる金額が800万円だとした場合、退職所得控除の20年掛けた場合は控除額が800万円になるため、入ってくる金額と控除額が同額になります。そのため退職所得が0円となります。この800万円は掛金を掛けているためその分の所得税の控除は受けており、そうすると支払った時に税金が所得控除で少し減り、なおかつ入ってくる時には税金なしで入ってくるというケースも考えられるのです。この部分を考えると小規模企業共済はやる意味はあると言えます。 小規模企業共済のデメリット 小規模企業共済は、年末に一括で掛金を納付することが可能です。例えば12月に月額7万円、年間84万円を前払いする際にその金額が口座から落ちなかった場合、自動的に1月から7万円の引き落としが1年間続き、止めることができません。その点は注意しておきましょう。 きちんと検討しましょう 今まで小規模企業共済について解説してきましたが、加入する際には、掛金を他に使う道があるかどうかを吟味して決めるようにしましょう。どのようなものであるかということをきちんと理解した上で加入することが重要です。 小規模企業共済についてもっと知りたいという方は是非弊社までお気軽にご相談ください。 関連記事:小規模企業共済の賢い使い方とは?
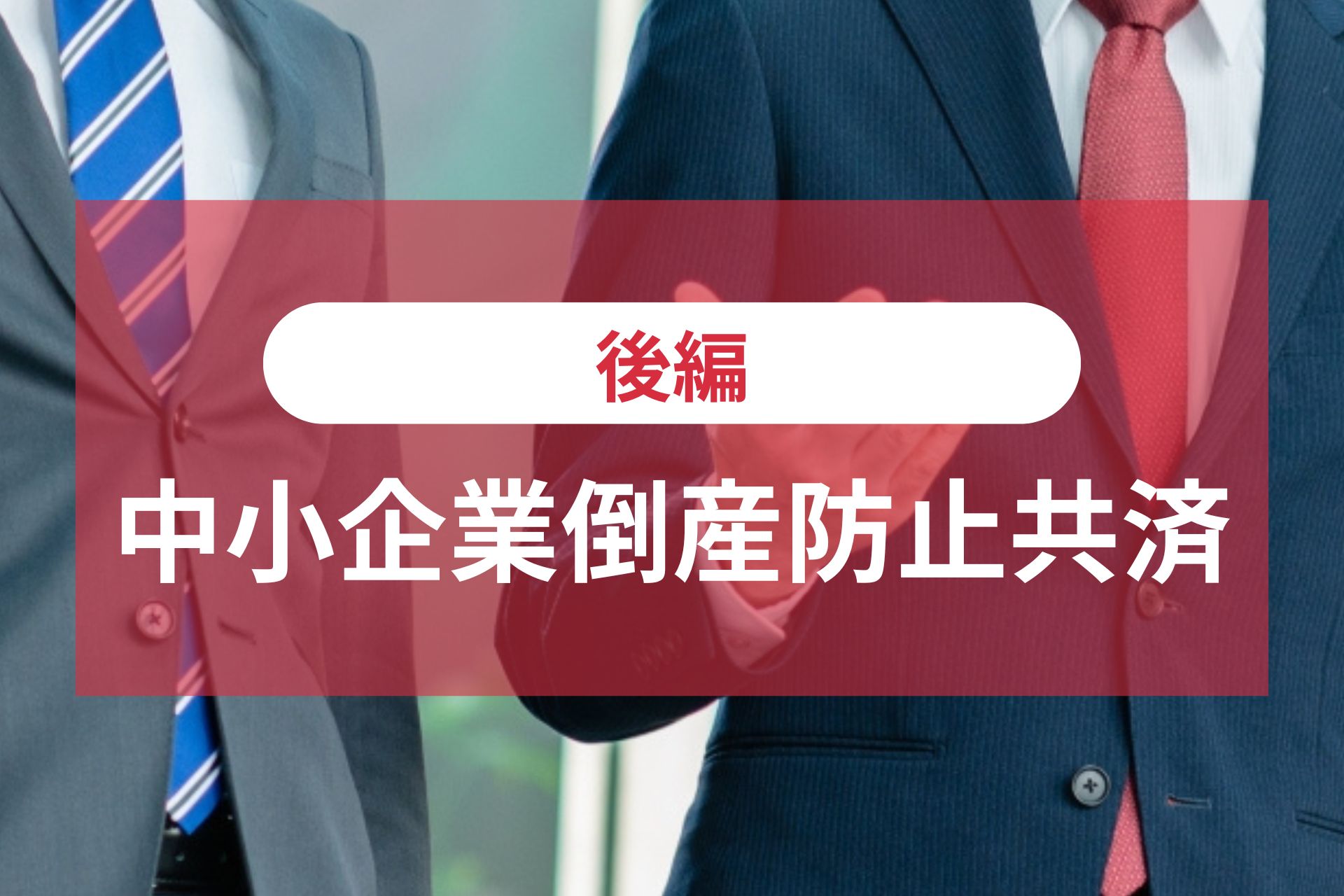
中小企業倒産防止共済とは?(後編)
前回は中小企業倒産防止共済の概要とメリットなどについて解説しました。 今回はこの中小企業倒産防止共済の注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=2qyCuXSaqFc 中小企業倒産防止共済の注意点 掛けた期間によって返戻率が変わる 中小企業倒産防止共済の注意点の一つ目は掛けた期間によって、戻ってくる金額が変わってしまうという点です。 中小企業倒産防止共済の契約を解約した場合の返戻率は以下の通りとなります。(12ヶ月未満での解約は掛け捨てとなります。) 掛金納付月数任意解約みなし解約※1機構解約※21ヶ月〜11ヶ月0%0%0%12ヶ月〜23ヶ月80%85%75%24ヶ月〜29ヶ月85%90%80%30ヶ月〜35ヶ月90%95%85%36ヶ月〜39ヶ月95%100%90%40ヶ月以上100%100%95%※1 会社の解散や個人事業主が亡くなった場合※2 滞納や不正が発覚したことにより共済側から解約した場合 掛けてから1年経たずに解約してしまうと掛金は戻ってきません。1年以上からは期間に応じて返戻率のパーセンテージが上がっていき、40ヶ月で100%となります。 もし、掛金を前納(前払い)している場合は前納金を充当する月がきてはじめて掛金として扱われます。例えば令和7年の12月に1年分を前納した場合、令和8年の12月に12ヶ月分掛けたという数え方となります。そのため、掛金の納付月数をきちんと把握しておくようにしましょう。 中小機構|経営セーフティ共済 手続きに時間がかかることがある 決算の月に入金するなどのケースが多いですが、手続きに時間がかかることがあります。そのため、1年間の前払いをする場合は、可能であれば1ヶ月ほど前までに利益予想などを出して早めに掛金を支払えるようにしましょう。 節税ではなく投資先として適切かを考える 前述しているように中小企業倒産防止共済は、40ヶ月経たないと100%戻ってくることはありません。掛金の額は月5,000円〜20万円と選ぶことができますが、例えば月20万円で掛け始め40ヶ月積み立てると相当な額になります。一度掛け始めるとその掛金をいわば拘束してしまうことになるわけです。 そうではなく、その金額で設備投資をしたり、人を雇ったりすることも可能です。そうすることで売上をあげる方がメリットになる可能性もあるため、節税をするというよりも事業計画に沿ってやるかどうか検討するべきでしょう。 計上する際の裏ワザとは? この中小企業倒産防止共済は、経費として計上する方法と積立金として資産計上する方法があります。このどちらを選ぶかによって決算書の利益の金額が変わってきます。 経費処理して決算書を作ると、利益の金額がその分減ることになりますが、積立金として決算書の処理をすると、経費処理した場合と比べて決算書上利益が残ることになります。 資産(積立金)として計上して、経費にするには申告書で税金計算をする時に別で差し引くことになります。決算書の利益額の計算方法と税金の所得金額の計算方法は少し異なるところがあり、申告書で決算書の利益をもとに調整する形となります。つまり支払う税金は経費計上した場合と同じとなります。これを行うことで決算書上は黒字ですが支払う税金は掛金を経費として処理した場合と同じとなるため、決算書の見栄えがよくなるというメリットがあります。 そうすることで融資の際などに役立つことが考えられます。金融機関が融資をするための判定をするにあたって、例えば赤字だったため悪い方に振り分けられてしまうという可能性があります。その際に中小企業倒産防止共済を経費処理せずに資産として計上して、申告書の中で経費処理を行い税額計算するという方法をとることで、その部分をクリアできる可能性があると考えられます。 具体的に経費の勘定科目は保険料、積立金は保険積立金の勘定科目を選ぶ形となります。 税務関係のご相談お待ちしております 今回は中小企業倒産防止共済について注意点と計上する際の裏ワザについてお伝えしました。 中小企業倒産防止共済をするにあたって節税になるからするということではなくて、しっかりと事前に検討してから行うようにしましょう。どうお金を使っていくかということを考えることがとても大切です。 また、節税についてご相談したいという方は是非弊社までご連絡ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(前編)

中小企業倒産防止共済とは?(前編)
今回は中小企業倒産防止共済、通称、経営セーフティ共済についてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=6BHoDQVutKw 中小企業倒産防止共済とは? まず、この中小企業倒産防止共済とは、経営に対しての保険のような位置付けのものとなります。具体的には取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度となります。掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れをすることが可能です。この掛金は月5,000円〜20万円まで選ぶことができ、累計で最大800万円までとなります。掛金は申告上は経費として計上することができます。 ただ、設立1期目は入ることができません。また、個人事業主の加入は可能ですが、医療法人やNPO法人、農事組合法人なども加入することができません。 掛け方としては毎月支払っていくか、前納という方法、つまり1年分を前払いすることも可能です。そのため、利益がでている場合は、年度末に1年間分前払いする方法がとられるケースもあります。 中小機構|経営セーフティ共済 中小企業倒産防止共済のメリット メリットとしては、何かあった時の保障のため、掛金の10倍の額を借入をすることができることです。 また、金利は0.9%となります。 借入は売り先が倒産してお金が回収できなくなった場合などに行うことができます。 中小企業倒産防止共済は節税にはならない? 中小企業倒産防止共済は、加入をして掛金を払って解約した場合、40ヶ月以上掛けていれば、その掛金はそのまま戻ってきます。そこから再加入もすぐにすることが可能です。 この中小企業倒産防止共済は節税という形で耳にすることがあるかもしれませんが、個人的にはあまりそのようには思っていません。なぜなら、解約した場合にその掛金が利益となるためです。支払う時は経費となりますが、解約時に利益となるため節税とはなりません。 また、倒産防止共済は、前述したように40ヶ月以上掛金を掛けていれば全額戻ってくることから、一時的に損金を出せるものとして活用し、40ヶ月経ったらすぐに解約するという使い方がよくされていました。ただこのような使われ方をしてしまうと、必要な資金を貸し付けるという業務で、保険料が安定せずそのような保障業務ができるか分からなくなってくるということで、改正が行われました。 今回の制度の改正点としては令和6年10月1日以降に解約して再度加入する場合は、解約から2年経過するまでは損金・必要経費算入ができないという点です。つまり解約をしてすぐ加入をして掛金を払ったとしても経費にすることはできません。 解約するタイミングは選ぶことができる? この中小企業倒産防止共済を解約するタイミングは選ぶことができます。そのため、何か投資が必要なタイミングに解約することもできます。 ただ、40ヶ月掛けていないと解約時に全額戻ってこず、もし1年未満の場合は1円も戻ってこないので注意しましょう。1年後に80%戻り、その後は掛けている期間に応じて戻る率が上がり40ヶ月で100%となります。 詳しく知りたい方はご相談ください 今回は中小企業倒産防止共済について解説いたしました。 今回の制度改正は、本来の使い方ではないというところからなされたので、少なくとも節税のためにやるものではないというイメージは持っておいた方が良いでしょう。 事業者によって、入っておいた方がもしもの時に困らない、備える必要がある場合があるかと思います。 もっと詳しく知りたいという方は是非お気軽にご相談ください。 関連記事:中小企業倒産防止共済とは?(後編)
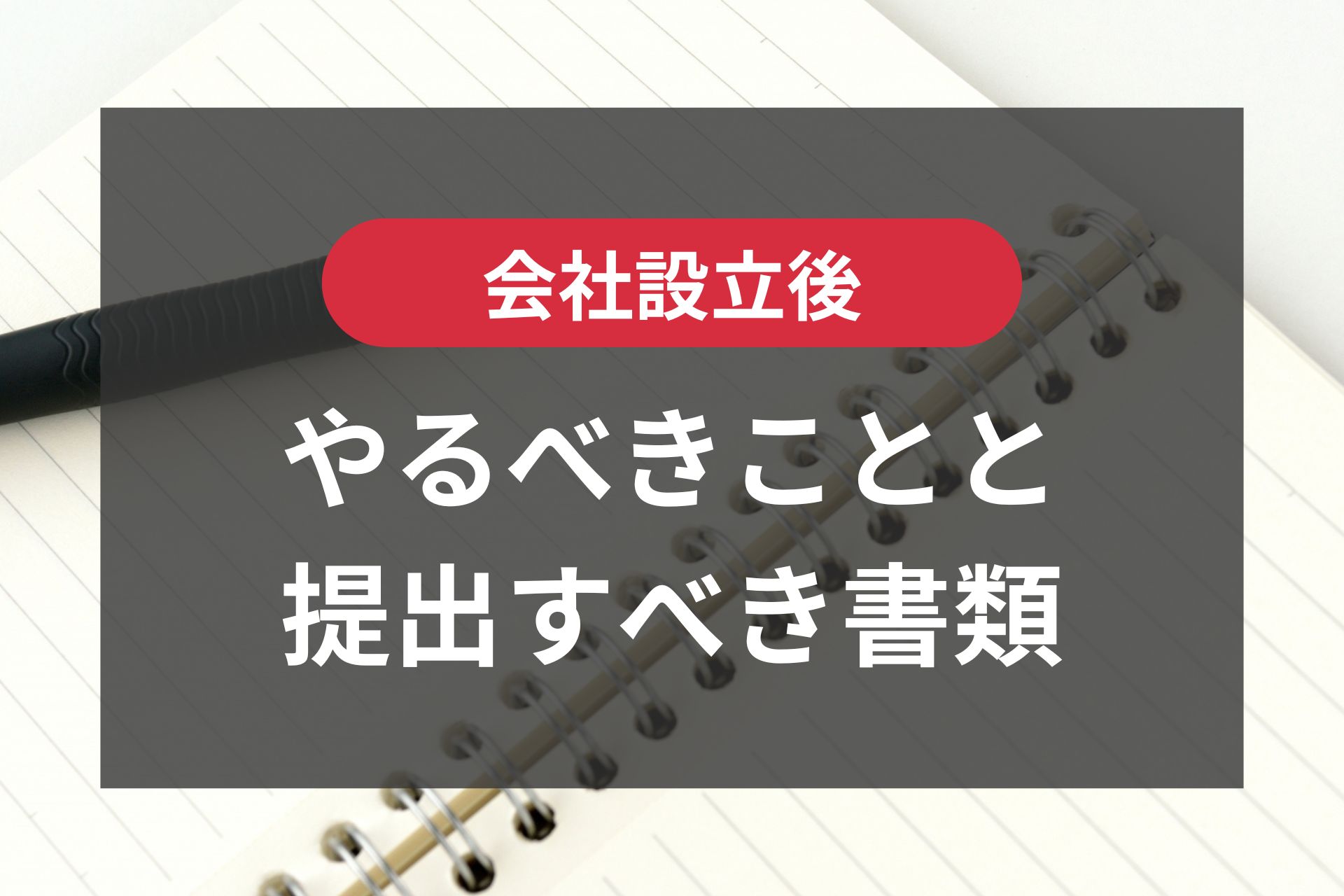
会社設立後にやるべきことと提出すべき書類
今回は会社を設立した後にやるべきことと提出する書類についてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=QmCW7SlEYcE 会社設立後にやるべきこと 会社設立後にやるべきことは大きく分けて2つあります。まずは銀行口座の開設、そしてもう1つは税務署や年金事務所など公の機関への届出です。 あとは会社によっては何か許可が必要な場合は、行政の許認可を担当している部署に申請を行うなどの手続きが必要となります。 銀行口座の開設 銀行も最近では口座を作るのが厳しくなっており、事業の実態などをきちんと確認して口座を作成するという流れになっています。登記事項証明書や定款などの書類はもちろん持っていきますが、その他に事業内容が分かる書類などを用意しなければならないケースもあります。 届出書類について 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場 会社設立後に税務署や各都道府県税事務所、市区町村役場に提出する書類について以下にまとめています。 税務署法人設立届出書青色申告の承認申請書給与支払事務所等の開設届出書源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書各都道府県税事務所市区町村役場法人設立届出書定款のコピー登記事項証明書 まずは税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に「会社を設立しました」という届出である法人設立届出書を提出します。電子申告をすることもできますが、そうでない場合はご自身が設立した会社の管轄の税務署や県税事務所、市区町村役場などに直接届出を行います。 また、青色申告を行う場合には青色申告の承認申請書を提出する必要があります。こちらは設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日の前日までに提出しなければなりません。例えば1月や2月に設立をして3月が決算という場合には、3月までに届出をしないといけません。会社を設立した際に多くの経費がかかった場合、青色申告でなければ赤字を2期目に繰り越すことができないため、提出遅れになってしまうと損失を繰り越せずに損をしてしまうケースもあるので注意しましょう。 給与の支払いがある場合には、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出します。こちらは従業員だけではなく、役員にも給与を支払うのであれば提出する必要があります。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書とは、給与を会社から払う際に天引きした税金の納付ですが、通常毎月行うものを半年まとめてにできるというものです。こちらは給与を支払う人数が10人未満の場合に使うことができます。設立当初は何かとバタバタしており、なかなか毎月納付することがままならない場合にはこちらを提出しておいて、半年に1回の納付にするというのが一般的かと思います。 年金事務所 年金事務所に提出する書類は以下となります。 年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届健康保険被扶養者(異動)届 健康保険・厚生年金保険新規適用届は、会社設立から5日以内に提出となっています。また役員や従業員など人単位での届出は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届となります。扶養の方がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届も合わせて届出をしましょう。 ハローワーク・労働基準監督署 従業員を雇用する場合には、ハローワークと労働基準監督署に以下の書類を提出します。 ハローワーク雇用保険適用事業所設置届雇用保険被保険者資格届労働基準監督署労働保険の保険関係成立届労働保険の概算保険料申告書就業規則(変更)届適用事業報告書 従業員を雇用する場合には、雇用保険と労働保険に入る必要があり、その届出もしなければなりません。ただ、1人社長の場合は必要ありません。 まずはハローワークで雇用保険の手続きを行います。労働保険に関しては、労働基準監督署が管轄となります。 これらの他に会社の状況によって、提出すべきものが異なりますのでしっかり確認をするようにしましょう。 手続きに関してご相談ください! 今までお伝えしてきた手続きを一人で行うことは手間はかかりますが、できないことはないと思います。ただ、どうしても会社設立後、特に忙しく、これら手続きを全て一人で行うのが難しい場合もあるかもしれません。そのため、専門家に依頼できるのであればその方が間違いはないかと思います。 もちろん会社設立後の手続きだけを依頼することも可能です。ただ期限があるものがあるため、出来るだけ設立前から手続きの代行などできる税理士や社労士を見つけることをおすすめします。 弊社でも会社設立のサポートをさせていただいておりますので、「時間がなかなか取れない」「手間だ」ということであれば、是非一度ご相談ください。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
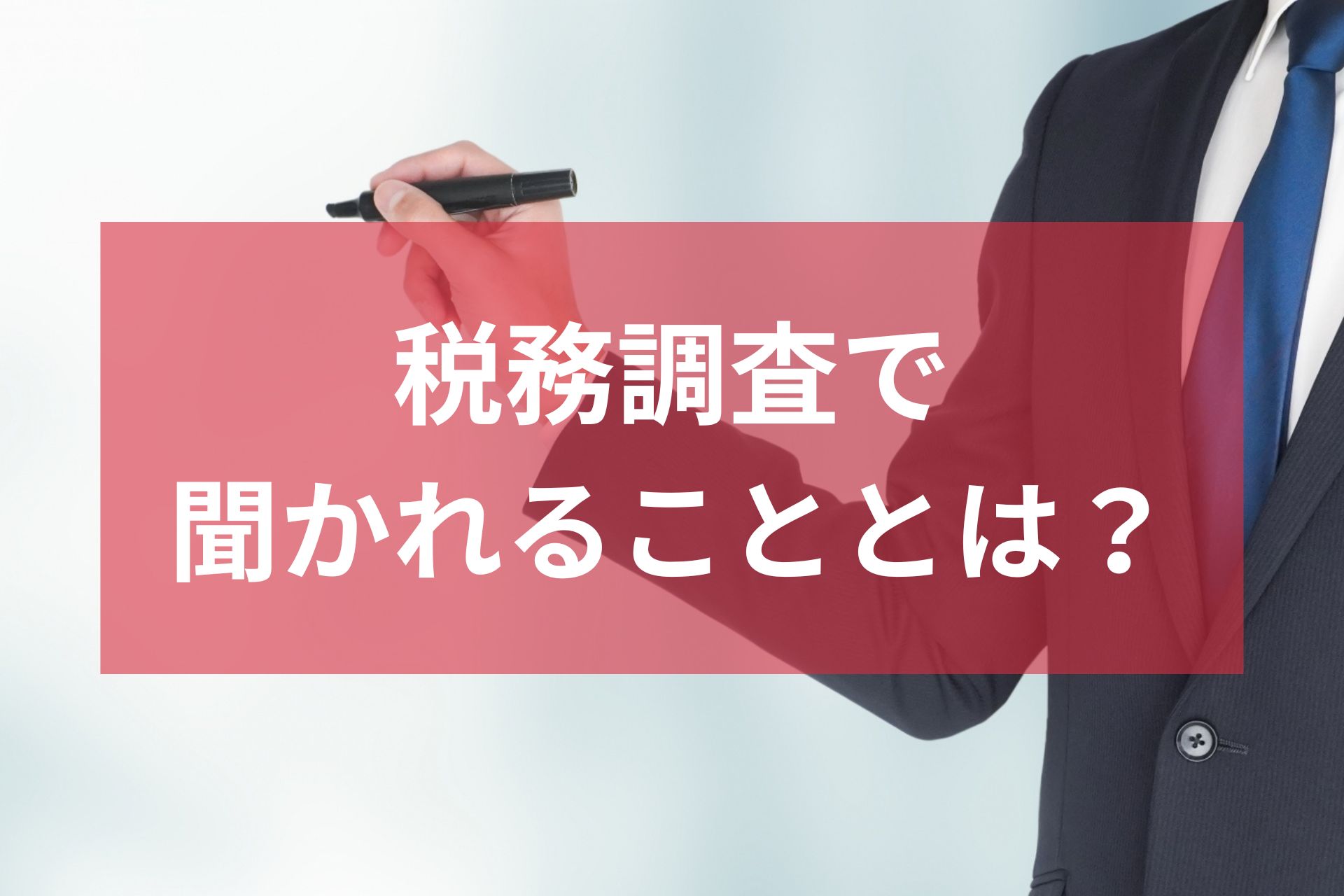
税務調査で聞かれることとは?当日の流れも解説
前回に引き続いて、税務調査に関して、今回は具体的な税務調査の流れや聞かれることについてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=JaC_mR1YxnQ 税務調査が入る時はどのように知らされる? 事業主の方に税務調査が入る場合は税務署から連絡があります。税理士をつけずに申告された方は、納税者に直接連絡が入ります。税理士を介して申告をしている場合には、税理士へ連絡が入り、税理士から納税者へ連絡をするという流れとなります。 大抵の場合はその電話の際にスケジュール調整を行います。例外として、本当にやむを得ないケース、例えば重い病気などで今対応できる状況ではない場合などはスケジュールを後ろにずらすなどの対応がとられる場合もあります。 税務調査の所要日数 税務調査の所要日数に関しては会社の規模や調査の種類によって異なってきますが、個人事業主の方はおおよそ1〜2日ほどです。法人の方も基本的には同じですが大体2日ほどと考えていただければと思います。ただ規模が多い場合や何か事情がある場合には3〜4日に渡って行われ、さらに規模が大きい場合には1週間ほどの日数がかかるケースもあるようです。 税務調査当日のタイムスケジュール 9時半〜 調査が入る時は、おおよそ9時半に調査官が来社されます。そこで創業年数や役員構成、どのような仕事をしてモノの流れやお金の流れがどうなっているかなどの基本的な質問がされます。そこで必要に応じて作業現場の訪問があります。 11時〜 質問だけで終わる場合には、おおよそ11時から帳簿書類の確認の時間となります。書類などは事前に準備をしておく必要があります。 12時〜 お昼休憩 13時〜 帳簿書類の確認が再開されます。 17時 大体17時前くらいに終了となります。または、次の日がある場合には次の日という流れとなります。 税務調査の間は、最初と最後、そして必要に応じて質問がある場合以外は基本的に税理士が付いていれば大丈夫です。そのため、社長や事業主の方は、ご自身の仕事を行っていただいて構いません。 調査の中で質問があり、その中で何か問題点があり、その場で解決とならなかった場合には後日結論が出る場合もあります。そのような問題点があった場合には、税理士側でも検討して税務署との折衝をあとで行うというのが基本の流れとなります。 税務調査で受ける質問 どんな質問をされる? 税務調査の際に行われる質問内容はケースバイケースではありますが、事前にある程度会社の申告書などを確認して確認したいポイントがある場合が多く、そこに関しての質問がなされます。例えば商品の在庫管理に関する質問などが挙げられます。「ここが気になるな」「ここが間違っているのでは」と思う部分を質問されることが多いです。 プライベートな質問もある? 税務調査の質問だけではなくて、世間話もあります。納税者があまり緊張しないように世間話も交えながら話をするという感じです。 世間話の中でも色々見られているのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。調査官も、最初は世間話をしてその後しっかり行っていく方や世間話をしながらも要所要所で質問をきちんと織り交ぜて意図を持って質問していく方など様々なタイプがあります。基本的には聞かれたことには答えますが、余計なことは話さない方が良いかと思います。過度に緊張せずに、正直に話すようにしましょう。 税理士が代わりに回答はできる? 税理士が回答できることや納税者が回答することが難しいような場合には税理士が回答することもあります。ただ、現場での管理の仕方や会社の成り立ちなどの納税者に関することは基本的にはご自身で答えていただく形となります。 税理士は調査官と顔見知りにはなる? 私たちの場合、仙台市は調査官の数も多いため同じ方にあまりあたることがありません。税務調査対応をしている税理士などは立ち会う数も多いので顔見知りになってしまうことはあるかもしれません。そうではなく通常の税理士事務所であれば、顔見知りになることは少ないかと思います。ただ、地方などの調査官自体の数が少ないところでは顔見知りになる場合も考えられます。 税務調査に臨む際の注意点 税務調査の前に帳簿の確認をして、事前の打ち合わせを行います。その際に、税理士に言っていないことや税理士が把握していないようなことに関しては正直に伝えるようにしましょう。あまり都合の良くないことも含め、それを抱えたまま税務調査に臨むことは精神衛生上良くありません。税務調査に入る前にきちんと対処しておけば、傷は浅くて済むというケースは多いので、正直に税理士に報告して後ろめたさがない状態で調査に臨むことが大切です。 日頃の処理をきちんと行いましょう 税務調査は怖かったり不安に思ったりする方もいらっしゃるかと思いますが、今は丁寧に優しく対応してもらえるのであまり不安に思う必要はありません。 税務調査は日々の積み重ねの答え合わせのような性質があるため、日々の処理をきちんと行い、税務調査が来たとしても安心して対応できるような体制を整えていきましょう。 弊社でも税務調査のサポートをさせていただいております。ご不明点あればお気軽にご相談ください! 関連記事:税務調査はいつ来る?入りやすい会社の特徴とは?