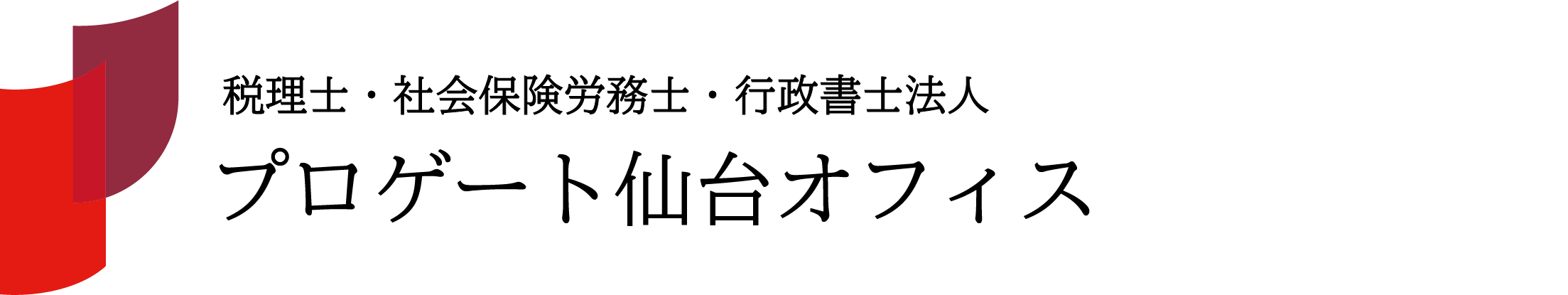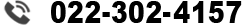- 会計関連
経営者必見!決算書の見方や活用方法を分かりやすく解説
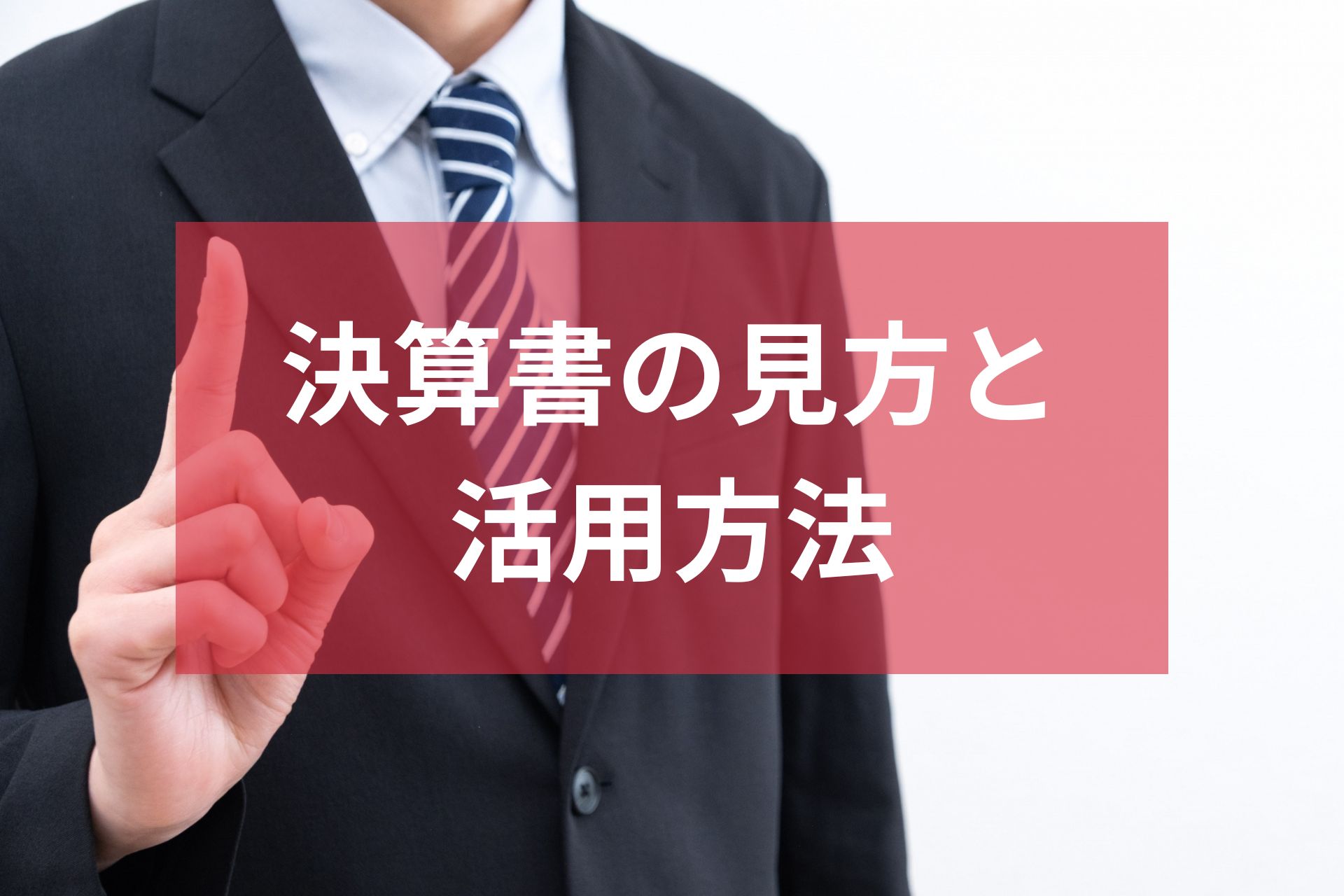
経営者の中でも決算書の見方がよく分かっていないという方もいらっしゃるかと思います。
今回は、決算書の見方と正しい活用方法についてお伝えしていきます。
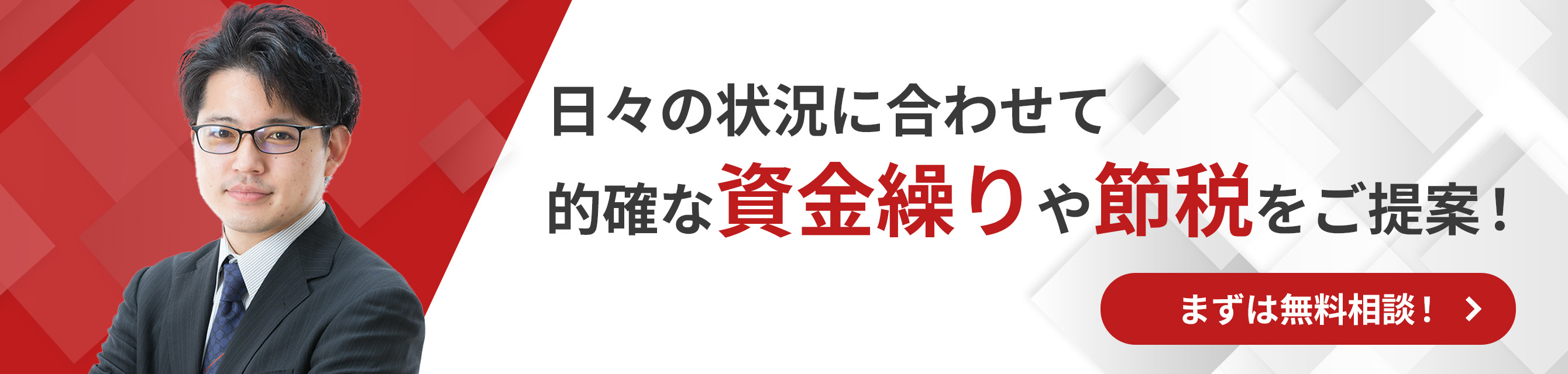
決算書の役割とは?
中小企業の決算書は、税務申告用としての側面が多く、税金の計算をするために作成すると考えていらっしゃる方も多いように思います。
ただ本来、上場企業の決算書を見ると税務申告という目的とは全く違う形で決算書が使われています。具体的にいうと、数字を見て、自分たちの事業がどういう状況にあるのかということを具体的に把握して、来年度以降にこういう計画でいくという形で使われています。
つまり、数字を把握して具体的に行動に落とし込むというところまでやるというのが正しい決算書の使い方です。
決算書の見方と活用方法
 決算書の数字を細かく分析し、事業の改善に繋げていく
決算書の数字を細かく分析し、事業の改善に繋げていく
決算書だけではどうしてもその行動を考えるところまではなかなかいきません。どういう事かというと決算書の売上・経費・利益などの数字からさらに細かく現場の活動に落とし込んでいくという作業が必要になるのです。
例えば、商品がA、B、Cと3つあるとします。そこからさらに商品の単価がいくらで、販売個数はいくらなのか分けていきます。そうした時にAは好調だが、BとCが少し伸び悩んでいるといったような傾向が分かってきます。そうした傾向が分かった時に、現場では何が起こっているかを繋ぎ合わせていくのです。先ほどの例でいうと、営業努力が足りていない、例えば「一つの地方だけの営業で他の地方には行っていないため伸び悩んでいる」といったことが分かってきます。そうして今後の改善方法を検討していきます。
このように、決算書の数字を細かく分析し、事業の改善に繋げていくことが非常に重要です。
 決算書の数字と経営者の頭の中を一致させる
決算書の数字と経営者の頭の中を一致させる
経営者は、売上がこれぐらい上がるだろうという予測のもと、仕事を獲得されるかと思います。しかし、その数字と実際の決算書の数字が大きくかけ離れていたら、経営者は現場をうまく把握できていないということになります。そうすると、もう一度照らし合わせながら計画を組んでいくことが必要となります。
では、経営者が現場を把握できるのはどれくらいの規模まででしょうか?
製造業などある程度の人数を使って拡大しなければいけないような業種は、経営者だけでは把握しきれないので、中間管理職のような方を使って把握していく形となります。人を使って拡大したり、人が増えたり、遠方に拠点があり社長があまり現場にいけなかったりなど、経営者から離れるごとに一人だけでは判断ができなくなってきます。
とはいっても、中小企業の場合などは、人を使ったとしても権限が全て経営者にある場合が多いため、全体を把握できている状態のはずです。だからこそ経営者の方が思い描いていることと実際の決算書の数字とを照らし合わせてできるだけ齟齬がないようにしていくことが重要になります。
月次で行いましょう
年に1回だけ決算書を作成するのではなく、月次で行っているかどうかも融資を受ける上で重要です。そこからプラスアルファで、今後の見通しをたてて状況ごとに更新をしているような会社は金融機関からの印象もとても良いです。また自社の状況をきちんと理解しているということもなるので、意思決定のスピードも早く、正確です。
経営者の方が数字を日頃からきちんと把握をして、重要な意思決定の場面でもスピーディに決断できるということはとても大切です。
決算書を見て意思決定権を持つ人が現場をイメージできるということは非常に重要です。
まずは決算書を見る習慣をつけて、そこから将来の行動を決めていくというような考え方を持っていただくと良いでしょう。
弊社でも、簡単な目安の数字や今の現状から立て直しの見通しを伝えたり、打ち合わせをして予算と実績の管理をしたりなども行っています。是非、お気軽にご相談ください。
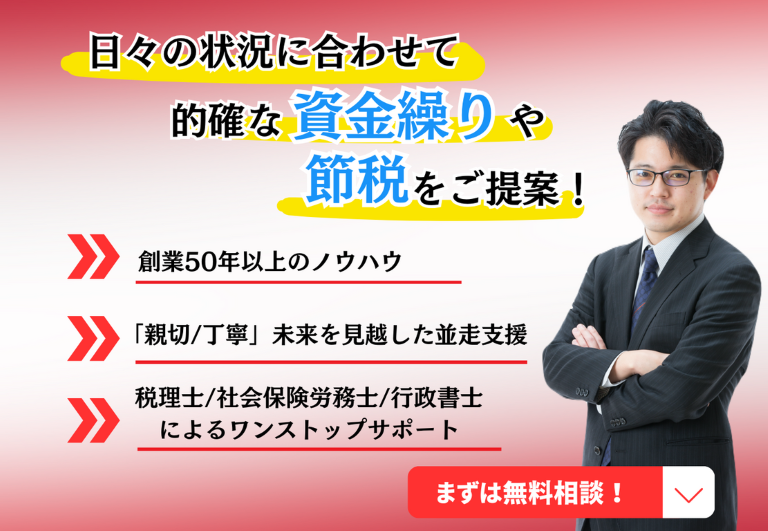
投稿日: 2025年4月3日 10:53 am