お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
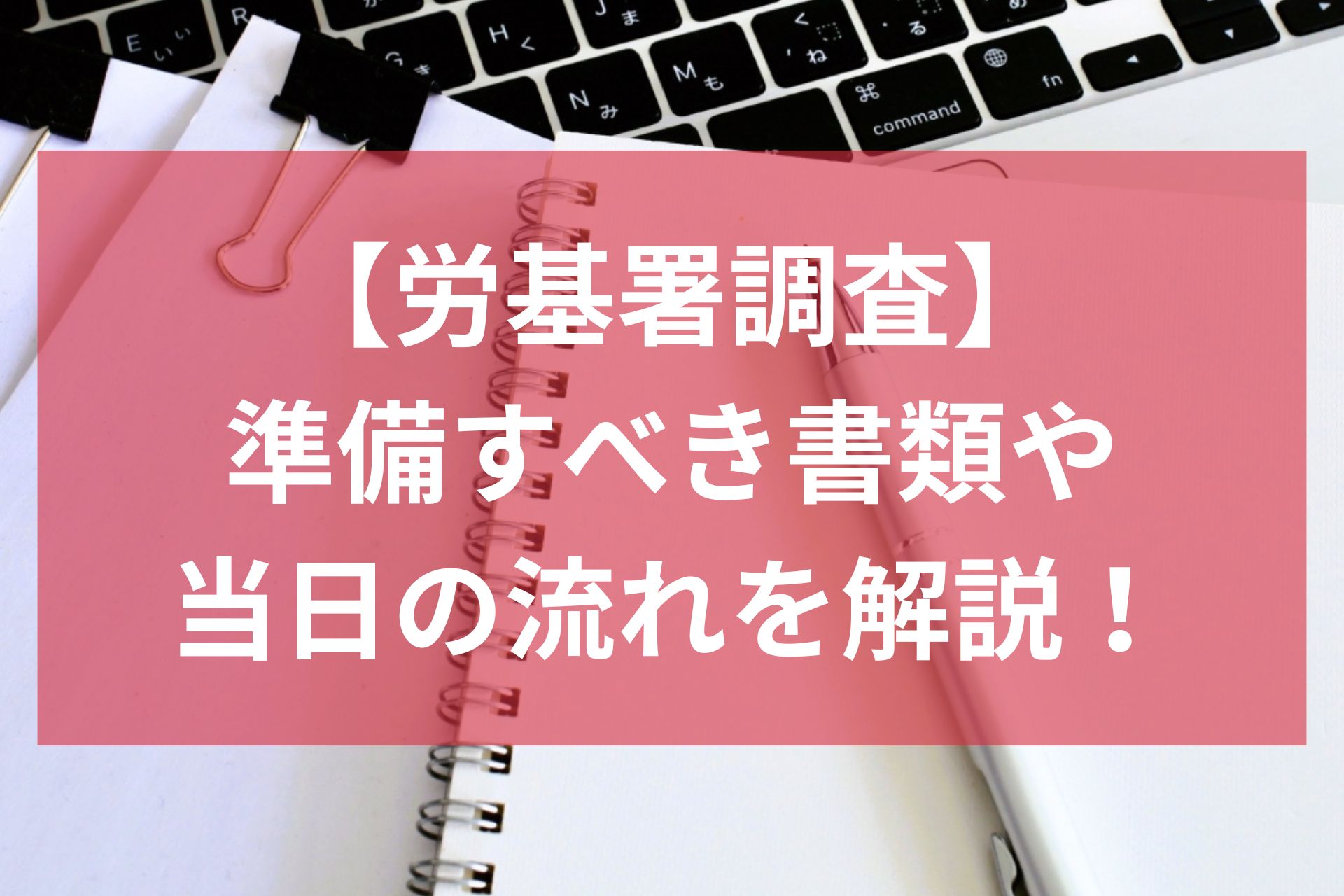
【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説!
今回は労基署調査で準備すべき書類や調査当日の流れについて解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=OgiiWFEq-bQ 労基署調査前に準備すべき書類 労基署調査で予告がある場合は、「このような書類を準備してください」といった事前要請があることが多いです。定期監督なのか、申告監督なのか、災害時調査なのかによって準備すべき書類は異なります。 例えば、労働者からの申告を受けて行われる申告監督であれば、その申告内容に関連する書類が重点的に確認されます。一般的な定期監督の場合は、基本的には労働条件や労働時間、安全衛生関係、社会保険、労働保険関係の内容を確認できる書類一式を求められる形となります。 事前連絡がある場合は調査の対象期間やこういった書類を用意してくださいという案内が来ますし、これは呼び出しの場合も同様です。 それぞれの場合で準備すべき書類は以下となります。 【労働条件関係】 ・労働者名簿 ・雇用契約書または労働条件通知書 ・就業規則および各種規定 (賃金規定) (退職金規定) (育児・介護休業規定)など ・常時10人以上の労働者がいる場合はそれを届出しているかという届出の控え ・派遣労働者や有期契約社員がいる場合はその契約書 【賃金・労働時間関係】 ・賃金台帳 ・タイムカードや勤怠管理記録 ・残業申請書や36協定届 ・有給休暇の管理簿 ・変形労働時間制や裁量労働制を採用している場合はその協定届や制度概要 賃金台帳は基本給や手当、残業代の算定根拠がわかる形のものが必要であり、労働基準法では過去3年分保管する義務があります。(2020年4月の労働基準法改正により保存期間が5年間に延長されましたが、当面の間は経過措置として3年間とされています。)ただし、税法上は所得税や法人税など対象となる税目によりますが、原則7年、法人で赤字があった場合などは10年とされています。このように同じ賃金台帳ですが法律によって保管義務が異なるため注意しましょう。 【安全衛生関係】 ・安全衛生管理体制の組織図や選任届 (安全管理者、衛生管理者、産業医の選任届) ・定期健康診断の実施記録 ・労働者死傷病報告書 ・作業場ごとのリスクアセスメント記録 ・特定業務(高所作業や有機溶剤等)の作業環境測定記録 【労働保険・労災関係】 ・労働保険(労災・雇用保険)関係書類 (保険関係成立届、年度更新申告書) ・社会保険加入状況の確認書類 ・労災事故発生時の休業補償記録 労基署調査は個人事業主が対象になることもある? 個人事業主も従業員を雇っていれば調査の対象になります。個人事業主の方が労基法などの知識や意識が低い場合が多いのではないかと思います。従業員が1人でもいて残業がある場合は、労基署に36協定を出さなければいけません。しかし、個人事業主の方は提出が漏れてしまっているケースが多いようです。1人でも従業員を雇ったら労働保険の保険関係成立届を労基署に出しますが、そもそもその届出さえ出しておらず従業員が結果的に労災に未加入ということになってしまっている場合もあります。個人事業であっても、人を1人でも雇う経営者は従業員が保護されている労働基準法や労働関係の法律に関して知識を持っていないと問題が起きるリスクがあります。 労基署調査当日の流れ 調査の内容や事業規模によって1時間程度で終わる場合もあれば、半日や丸1日、1日以上かかる場合もあります。そのためタイムスケジュールは一概には言えないのですが、丸1日の場合(従業員が数十名いるような規模の会社の場合)でお伝えしていきます。 10:00〜10:15 調査員到着・挨拶 10:15〜10:45 会社概要・労務体制ヒアリング 10:45〜12:00 書類確認①(労働条件関連) 12:00〜13:00 休憩 13:00〜14:30 書類確認②(賃金・労働時間関連) 14:30〜15:00 現場確認(必要な場合) 15:00〜15:30 指摘事項の口頭説明 15:30〜16:00 終了・今後の対応説明 現場確認は業種にもよりますが、例えば保護具や機械の安全装置の確認などが行われます。また、有機溶剤を使う場合は、その使うスペースが法律で定められている構造になっているか、換気がきちんとされているかなどが確認されます。 飛び込みの調査の場合は1〜2時間で終わる場合が多いです。 お気軽にお問い合わせください 今回は労基署調査に関して、準備すべき書類や調査当日の流れについて解説いたしました。 少しでもご不明点やご不安をお持ちの場合は是非、弊社までご相談ください。 関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説! 関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説! 関連記事:【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
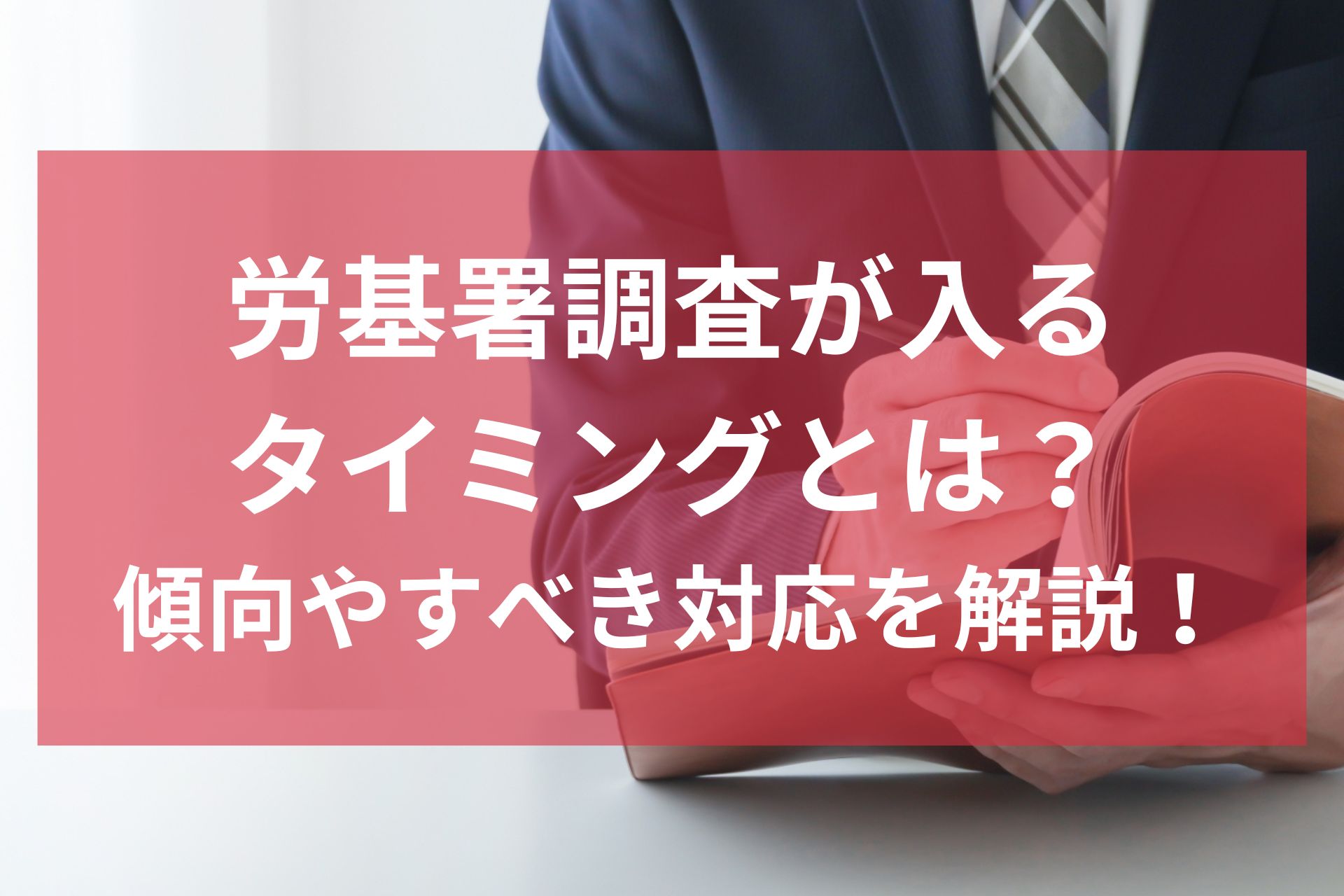
労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説!
今回も前回に引き続き、労基署調査に関して、調査のタイミングや傾向、すべき対応などを解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=OEMQ-i44xuc どんな会社が労基署調査に入られやすいのか? 大企業よりも中小・零細事業者の方が労働基準法や安全衛生法への対応が遅れがちだったりで調査の対象になることが多いです。法律の大きな改正があるとやはり零細事業者への監督が多いと感じます。主に指導的な内容で入れられることが多いです。 どんなタイミングやきっかけで調査が入るのか 労働者からの申告や通報があった場合 調査のきっかけは労働者からの申告や通報で入る場合が多いです。法律改正などで調査に入る場合は、一気に周知する目的ですが、大幅に指摘されるような、いわゆる厳しい労基署調査は申告監督が多いかと思います。未払い残業や不当解雇、セクハラ・パワハラなどで労基署に相談や申告があると高い確率で実地調査に入る形になります。 労災事故が発生した場合 労災事故が発生した場合も挙げられます。労災事故は2種類あり、簡単にお伝えすると労働者が労災事故にあって休んだ日にちが3日までの場合と4日以上の場合で大きく作成する書類などが変わります。4日以上の労災は大きな扱いになり、そのような労災が起こって労基署に報告があった場合には原則として現場調査が行われているかと思います。 これらの他に、会社が残業や休日労働を可能にするために労働者の代表と締結し労基署に届け出る協定である36(さぶろく)協定の書類が未提出で調査に入られるというケースもあります。 最近の労基署調査の傾向 最近の傾向としては雇用関係の助成金、コロナの時に助成金を申請した会社に不正受給のチェックの一環として労基署調査が入るケースが多くなっていると感じます。 また、テレワークが普及したことによって労働時間の管理が見えにくいという部分から、労働時間の把握やメンタルヘルスの問題などで労基署調査が増えているように思います。適正な労働時間の管理をテレワークでどのようにしていくかということを会社としてもきちんと考える必要があるでしょう。 さらに働き方改革の推進と連動して36協定の内容がきちんと守られているかや残業時間のチェックが特に重視されています。 労基署調査時にすべき対応 税務調査は原則として事前通知が行われます。一方で労基署調査の場合は原則、無予告です。ただ、コロナ以降は時間と持参すべき書類の通知が郵送で送られ、労基署に訪問するという調査も増えました。とはいっても原則巡回の調査は無予告のため、専門家が立ち合いに対応できないケースも多いです。調査する事項としては基本的なことで、雇用契約書の有無や労働時間、残業代、残業代の計算方法、有給、健康診断などに関してチェックが行われます。そこまで多い項目ではないため、書類さえ揃っていれば自社でも調査の対応は可能です。 ただ労基署調査があると是正勧告書が出されるケースが多いです。是正勧告がでた場合には違法状態であることの指摘をどう改善するかという報告書を出さなければいけません。それは法律をクリアするための書類を整備することはもちろんですが、書類に応じてその違法状態を改善しなければならず、これらを証拠書類として報告していく形になります。これに関しては自社ではなかなか難しい部分もあります。そのため調査の後に社労士にご相談いただくということもあります。 必要書類の準備は難しい? 必要な書類も1日でできるようなものではない場合もあります。例えば従業員が10人いるにも関わらず就業規則を作成していなかったとなると、就業規則は簡単に作れるものではありません。そのような場合に社労士に依頼するというケースも多いのではと思います。 また、書類を作成するだけではいけません。例えば雇用契約書は、きちんとその契約書通りに雇用をしなければなりません。労基署対策のために用意するのではなくて、あくまでも雇用主と労働者間の契約を文章化しているものになります。働いてもらう人にも安心して働いてもらうためにきちんと作成するべきものです。 社労士へご相談ください 今回は労基署調査に関して、調査のタイミングやすべき対応などに関してお伝えしました。書類の作成は、労使間でのトラブルを未然に防ぐという意味で行わなければいけません。そのため労基署と利害関係がぶつかるというよりも、きちんと法令を遵守していないことによって従業員に迷惑がかかる可能性があることを直していくという考え方でいくと、労基署調査は良い会社にするための一つのきっかけになるとも言えるでしょう。 そのためには書類をきちんと揃え、実行することが重要で、もしそのような状況でない場合は社労士へご相談することをおすすめします。 弊社でもサポートをさせていただいておりますので、ご不安がある場合はお気軽にご相談ください。 関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説! 関連記事:【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説! 関連記事:【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
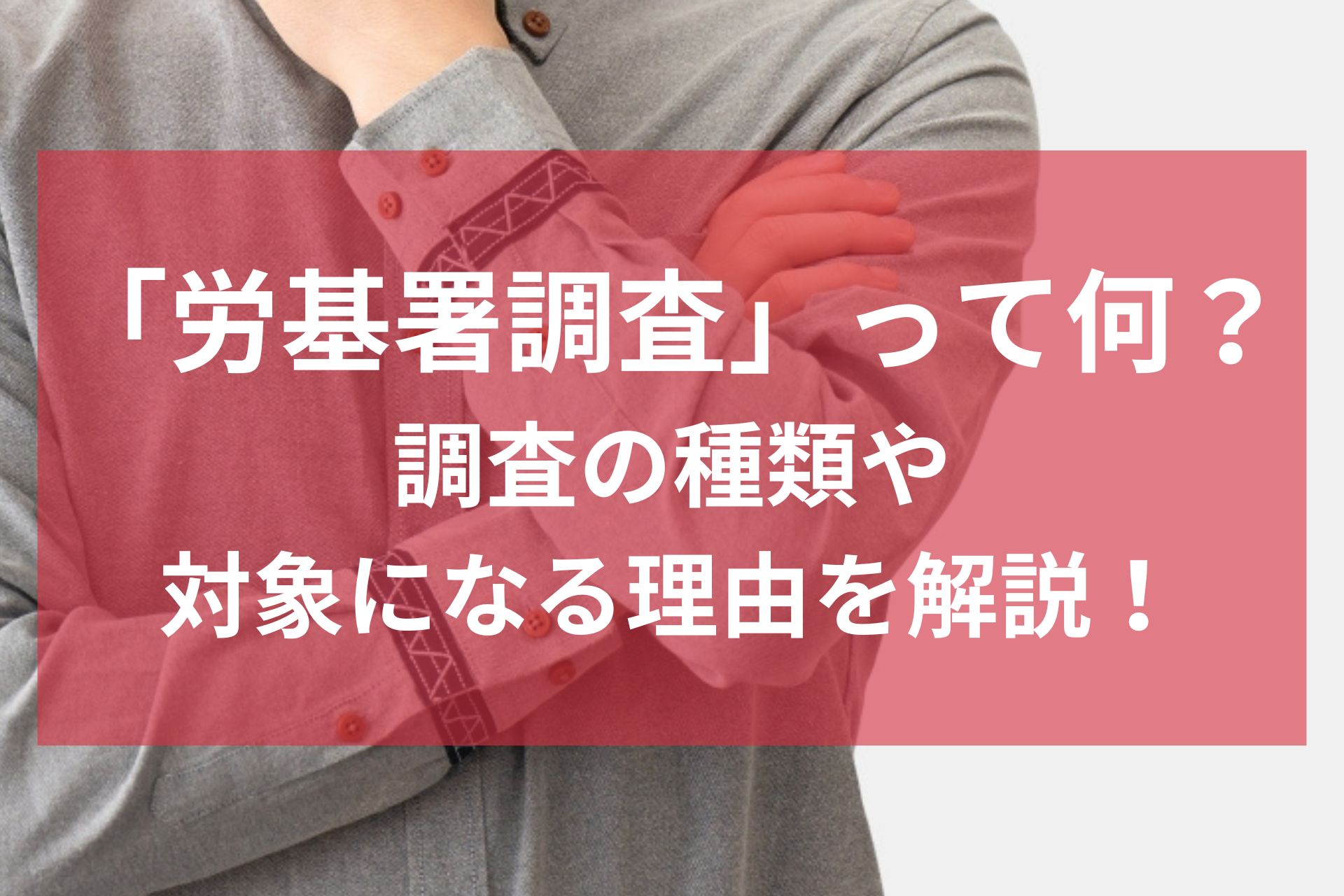
「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説!
今回は労基署調査について、具体的にどんなものなのか、また調査の種類や対象になる理由などについて解説していきます。 https://www.youtube.com/watch?v=qZ7W5C7mW7A 労基署調査とは? 税務調査というと事前に税務署から連絡がある場合がほとんどですが、労基署調査は様々な種類があり、会社に監督官が来るという場合だけではなく、監督署に呼び出されたり、労災事故があった際労災の現場に調査が入ったりと色々なパターンがあります。 基本的には任意調査ですが、拒否した場合は罰則が科される可能性があります。 また、税務調査の場合は税理士の独占業務のため、税理士が立ち合います。一方で労基署調査は社労士法には定められていません。独占業務ではないため、言い換えれば社労士でも税理士でも、労働法に精通していれば立ち会うことができるということになります。 労基署調査の種類 労基署調査の種類は大きく分けて4つあります。以下で解説します。 定期監督 労働基準法や労災防止の観点から、定期的・計画的に行われる調査のことです。年度ごとに重点業種が設定されて、巡回する形になります。そこで労働時間が長すぎないかや、割増賃金の計算をきちんと行っているか、健康診断をきちんと受けているか、例えば安全衛生の分野でいうと有機溶剤などを使用している場合それに対応している設備になっているかなどがチェックされます。 申告監督 労働者からの申告や通報(例えば未払いの残業代や長時間労働、パワハラなど)に基づき実施されます。申告された内容に基づいた重点調査が行われるケースが多いです。具体的には未払い残業や長時間労働などについての調査が行われるという形になります。基本的には労基署に呼び出されることが多いですが、場合によっては無予告で行われることもあります。 災害時監督 労災事故などが発生した際にその原因調査と再発防止のために行われます。基本的に労災事故が起きた現場で行われるので会社に来られることが多いです。 再監督 過去の調査で是正勧告があった場合、その是正内容の履行状況を確認する目的で行われます。再監督は無予告で来ることが多いです。 どんな会社が労基署調査に入られやすいのか? 労基署調査は単純に1つの内容を確認するということが目的ではないため、例えば労災事故が多く起きている会社であれば、業種関係なく調査の件数は多くなります。 監督指導の重点業種は毎年公表されています。過去数年でいうと建設業や製造業が多いです。労災事故や安全衛生のチェック事項などが多く不備が起きやすいということが理由として挙げられます。 また、介護や福祉業などでも、腰痛などを患うケースで労災と絡む場合や深夜の労働、長時間労働になりがちで重点業種にあたりやすいです。 運輸業や物流業も拘束時間が長く、過労やトラックなどの過積載などで、定期的に長時間運転をして事故があったりした場合は重点業種として挙げられる可能性があります。 会社としては、大企業よりも中小・零細事業者の方が労働基準法や安全衛生法への対応が遅れがちだったりするため、監督署の調査対象になることが多いかと思われます。 税務と労務の両面でサポートいたします 今回は労基署調査について、調査の種類や対象になる理由などについて解説しました。 プロゲートグループは税理士だけではなく、社労士も所属しています。税務と労務の両面でサポートできる体制が整っており、お客様に対してワンストップサービスをご提供させていただいております。ご相談をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。 関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説! 関連記事:【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説! 関連記事:【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
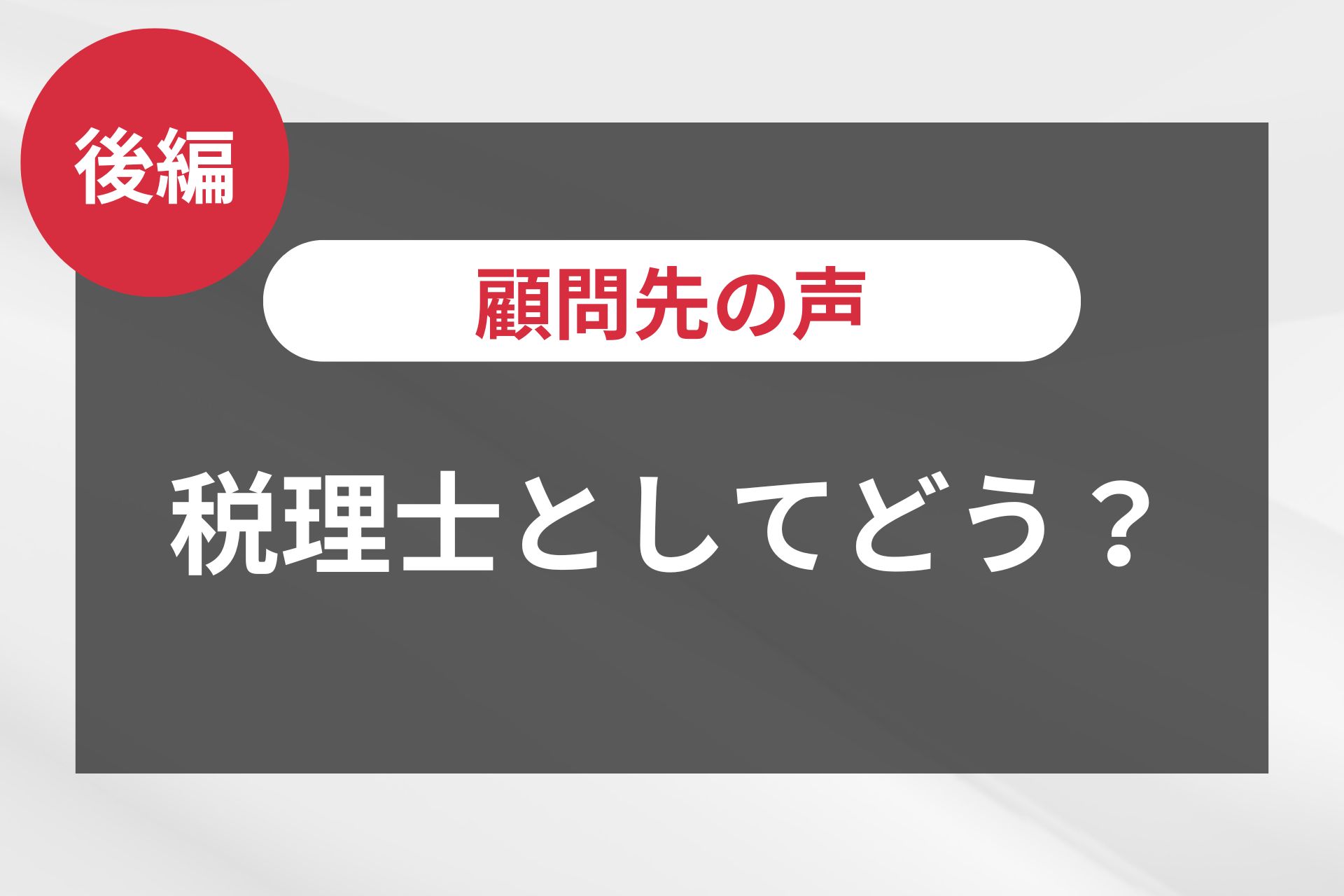
【顧問先の声】税理士としてどう?(後編)
今回も前回に引き続き、MAGIC×MAGICのYUNOさんにお話を伺っていきます。今回は顧問税理士として実際どういったやりとりで、どう感じていらっしゃるのかということをお話いただきたいと思います。 YUNOさんは仙台市でマジックバーのMAGIC×MAGICを運営されて、税務顧問を弊社にご依頼いただいております。 https://www.youtube.com/watch?v=i-p1iysHCsI 顧問税理士として改善してほしい点 YUNOさん: 僕的にはないですね。 何か心配なことがあったらすぐに相談に乗ってくれますし、特に不満なところもありません。安心してお任せして自分の事業に集中できる状態をつくれています。 業務内容について 依頼されている業務は何がありますか? 菅原先生: 記帳代行と確定申告のお手伝いをさせていただいています。 YUNOさんには通帳のコピーやものを買った領収書、売上、現金出納簿のエクセルデータをご提出頂き、それらを基に記帳を行っております。 立ち上げの時からサポートは受けられる? 菅原先生: 最初の方からお話いただいた方が、お客様のご事情に合わせてサポートを行うことが出来ます。事前にご相談いただけた方がスムーズにご準備も進めていただけますし、こちらとしてもありがたいです。 顧問税理士を選ぶポイント 顧問税理士を選ぶ際に重視していたポイントは? YUNOさん: 話している時に信頼できるのか、相談しやすい人なのかという点で選びました。 話しやすさやコミュニケーションのしやすさですか? YUNOさん: そうです。また、出来るだけレスポンスが早い人が良いなと思います。 距離の近さは? YUNOさん: そうですね、ただ最初は事務所の距離が近いとは知らずにだったので・・・ 菅原先生: 偶然そうなったというのはあります。ただ個人的に距離は近い方が良いとは思います。全国対応されている税理士さんもいらっしゃいますが、物理的に会える距離の方が色々お互いにやりやすい部分があるかと思います。 遠方からでも税務顧問の依頼はできる? 菅原先生: 遠方の方は相談できないというわけではありません!遠方の方の場合はzoomなどを活用しているので問題なくお引き受け可能です。可能であれば近くで会いにいける範囲の方がやりやすい部分はどうしても出てきますというくらいの話です。ご依頼いただけるのであれば全国ご対応させていただいております。 普段のやりとりについて 普段やりとりしているツールは? YUNOさん: 普段はLINEでやりとりさせていただいています。データを送る時だけメールで送っています。 菅原先生: 最近はチャットワークを主に使用しています。お客様に合わせてコミュニケーションを取るようにしていますが、社内的にはできればチャットワークでということでご案内しています。 菅原先生から見たYUNOさん 菅原先生: なかなか連絡いただけないなどは全くありませんし、本当に自己管理ができる方だなと思っています。資料なども定期的にまとめて持ってきていただけるのでこちらとしてもとても助かっています。 飲食業は記帳が大変? 飲食業は支払い方法が様々なので記帳は大変ではないですか? 菅原先生: YUNOさんはエクセルで売上帳簿を管理されており、そこでカードや現金ということも記載いただいているのでそこまで苦ではありませんが、飲食店のお客様で取引量が多いということになると難しくなる場合はあります。例えば、従来のレジスターですと売上データがレジで管理できませんので、別途売上データを管理する必要がありますが、取引量が多いとデータ管理が煩雑になり、かつ記帳時にも確認が手間、というケースが考えられます。 基本的には新しく飲食店を始められる方は売上データも管理できるレジ(スマレジなど)を入れていただいた方が良いかなと思います。 お気軽にご相談ください! 今回は前編と後編に渡って、顧問先の声ということでYUNOさんにお話をお伺いしました。普段のやりとりのイメージや税理士を選ぶ視点などお聞きすることができました。 今回お話をお聞きしたYUNOさんのお店にも是非遊びに行かれてみてください! 関連記事:【顧問先の声】税務顧問を依頼したきっかけは?(前編) 関連記事:【顧問先の声】なぜプロゲートに依頼した?(前編) 関連記事:【顧問先の声】顧問先に本音を聞いてみた!(後編)
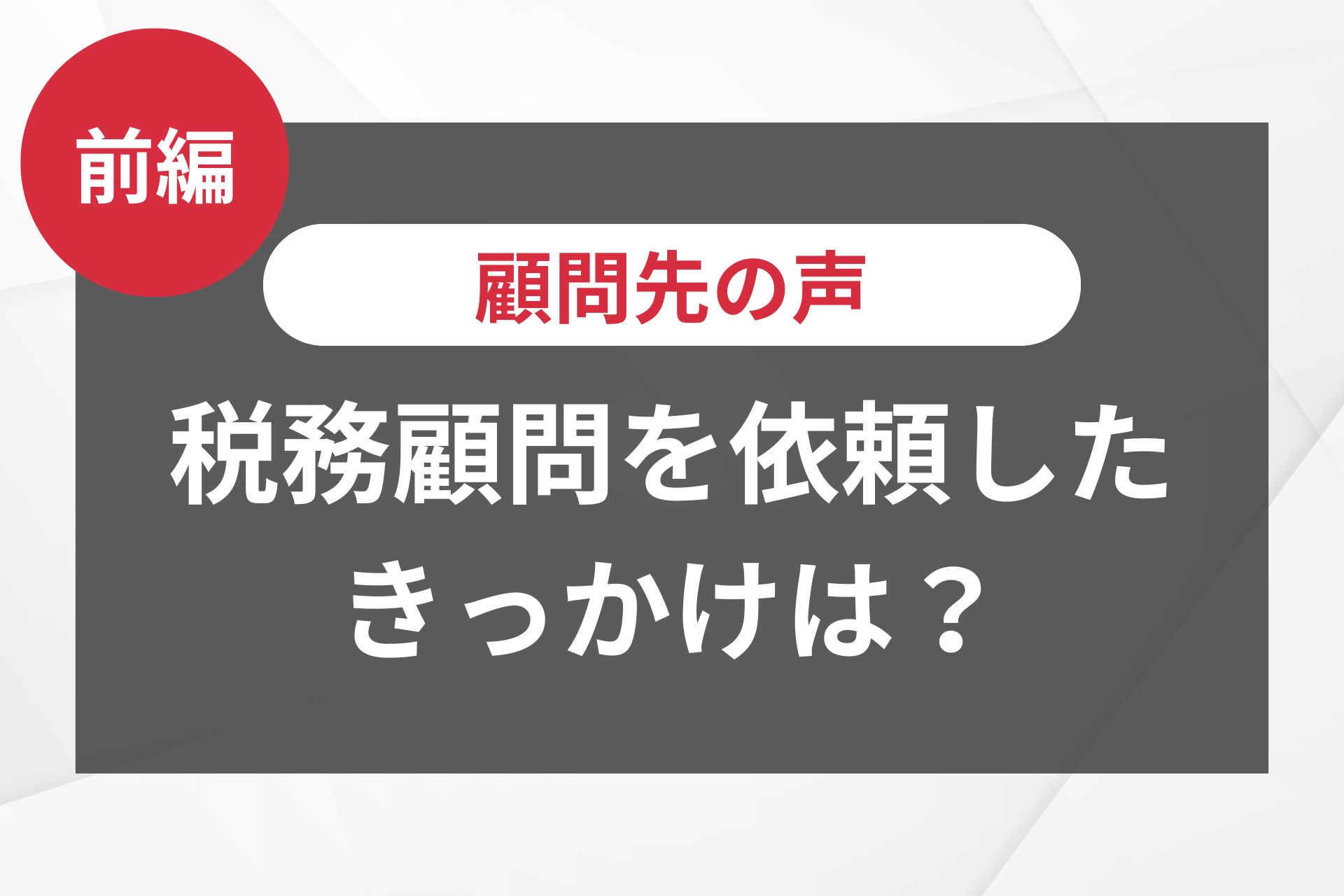
【顧問先の声】税務顧問を依頼したきっかけは?(前編)
今回は弊社の顧問先である、MAGIC×MAGICのYUNOさんにお話を伺っていきます。実際に顧問先の方は顧問税理士としてどう感じていらっしゃるのかを本音でお聞きしていきたいと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=iJgVGOcLufU 関連記事:【顧問先の声】税理士としてどう?(後編) 自己紹介 YUNOさん: 手品を目の前でお客様に体感していただいて、気軽にお越しいただけるようなBarを経営しています。お客様にマジックの楽しさを感じ取ってもらえるということを第一にしています。 また、企業のイベントや商業施設、市のイベント、学校などにも出張してマジックショーなどを行うこともあります。 以前は関西や宇都宮にいましたが、今は仙台で2年ちょっとこのお店をやっています。 菅原先生との出会いのきっかけ YUNOさん: 元々、お店のお客様で社労士の先生がいらっしゃって、その方のご紹介で一緒にお店にお越しいただきました。ちょうどその時税理士を探していたのでタイミングよく菅原先生と出会いました。最初は税理士の先生とは知らずにお話をしていました。 菅原先生: お店に行ってお話をする中で、始めたばかりで税理士を探していると伺って「実は税理士なんです」とお話した感じです。 YUNOさん: 元々お店を始める前はマジシャンの会社に所属していて、独立する時に経理関係は僕にはよく分からないので税理士に頼んだ方がいいのかなと思っていた時に菅原先生とたまたま出会いました。 最初から税理士を付ける人は多い? 菅原先生: 最初から税理士を付けるかどうかは人によります。税理士をつけないといけないと思う方もいれば、1度、自分でやってみるという方もいらっしゃいます。 ただ、自分でやるにしても、最初は税理士や税務署へご相談されることをおすすめします。 必要な手続きが漏れてしまったりすることがあるためです。 菅原先生について 菅原先生の第一印象は? YUNOさん: マジックをしながら会話をする中で、「この人話しやすいな」「相談しやすいな」というのは感じました。また年が近いということや元々知っている方からの紹介なのでなおさら信頼できるなと思いました。 普段は聞けない菅原先生のエピソード YUNOさん: 菅原先生はお話が面白い方なので、マジックの合間に菅原先生の楽しいマラソントークなどを聞いています。お店で初めて会った人とも仲良く喋って楽しいお客さんです。マジックをした時のリアクションも素晴らしいです。 顧問税理士として 顧問税理士として菅原先生の良いところ YUNOさん: レスポンスが早いので、何か困った時や悩んでいる時にすぐ問題を解決してもらえますし、月に1回面談もしていただいています。元々お店をオープンしたときからずっと移転を視野に入れていたので、このくらいの売上が出ていたら次のお店に行きやすいなどの相談にも乗ってくれています。 月に1回の面談とは YUNOさん: 売上などを提出するタイミングで、良かったらお時間いただけませんかというお話をいただいて、そこで色々とお話させていただいています。 菅原先生: YUNOさんが出勤される途中に弊社の事務所があるので、ついでに寄っていただいて資料をお持ちいただいた時に少しお話をさせていただいています。 お客様によって、決算の時だけ打ち合わせを希望される場合やYUNOさんのようにお越しいただいて打ち合わせをする場合もあります。お客様のご希望に合わせて行っています。 次回もお楽しみに! 今回は主に人柄や出会いのエピソードなどを伺いましたので、次回はお仕事のやり取りや顧問税理士としての内容についてお話をお聞きしたいと思います。 関連記事:【顧問先の声】なぜプロゲートに依頼した?(前編) 関連記事:【顧問先の声】顧問先に本音を聞いてみた!(後編)