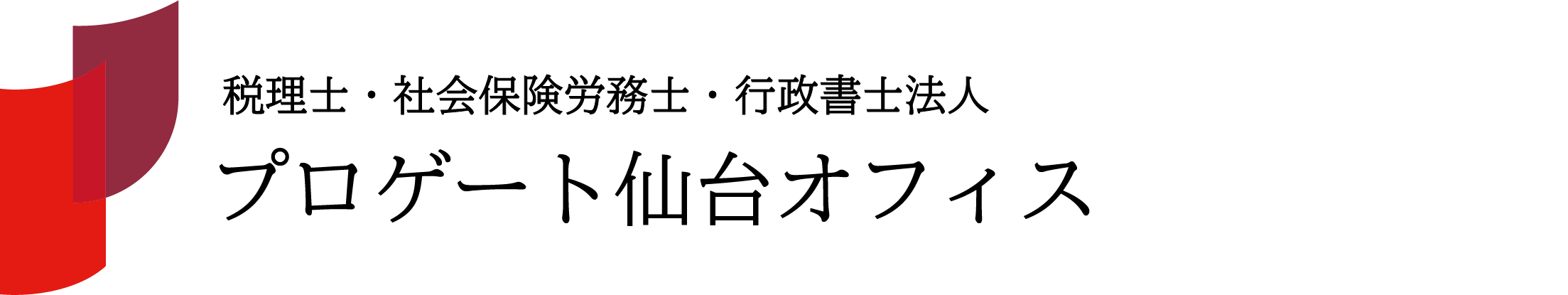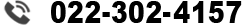- 社会保険関連
【労基署調査】準備すべき書類や当日の流れを解説!
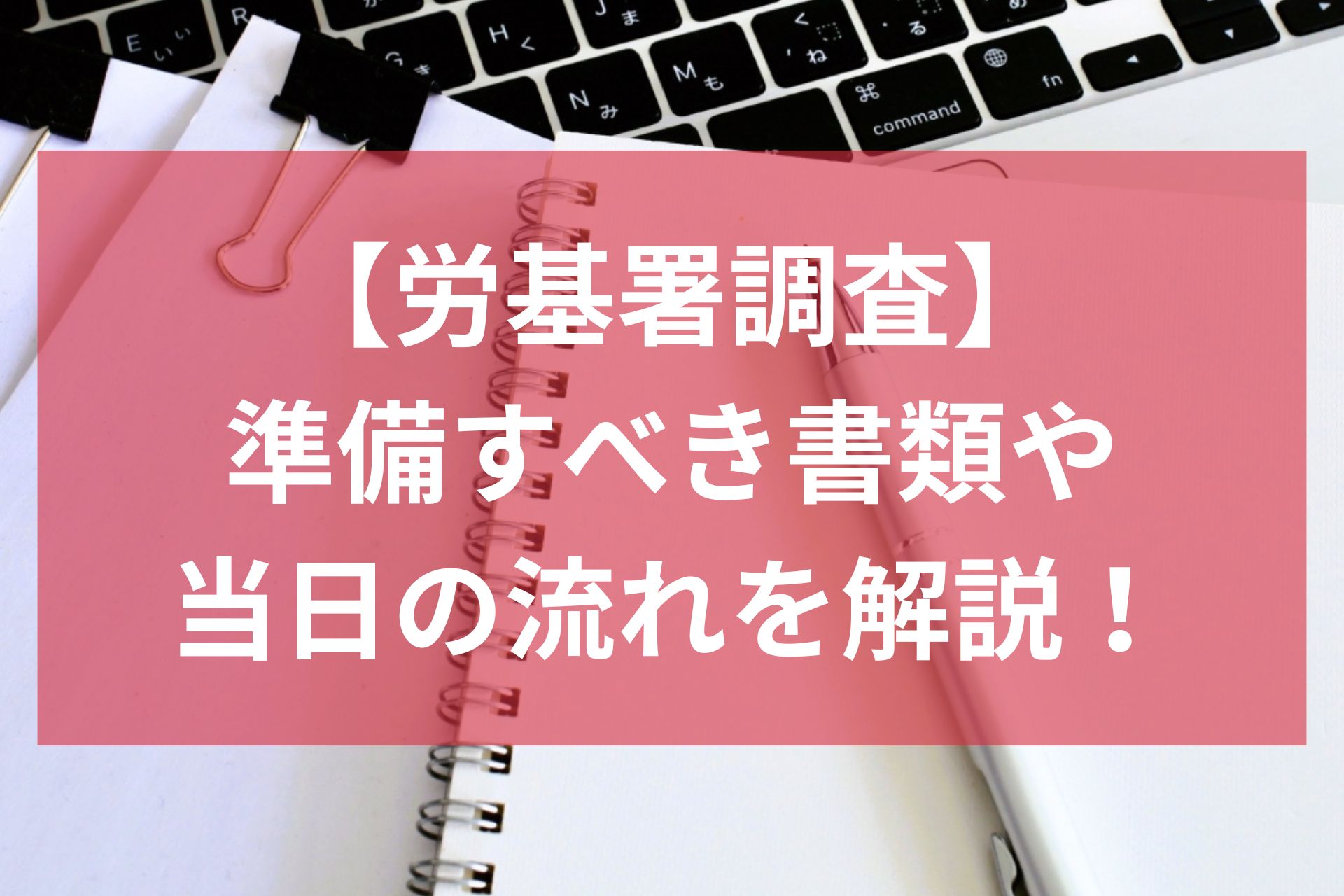
今回は労基署調査で準備すべき書類や調査当日の流れについて解説していきます。
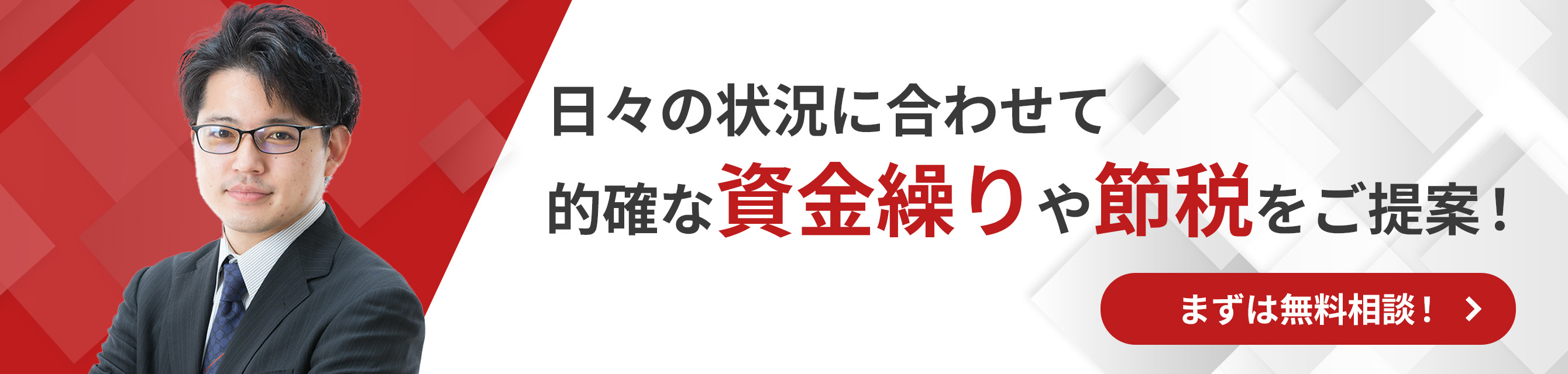
労基署調査前に準備すべき書類
労基署調査で予告がある場合は、「このような書類を準備してください」といった事前要請があることが多いです。定期監督なのか、申告監督なのか、災害時調査なのかによって準備すべき書類は異なります。
例えば、労働者からの申告を受けて行われる申告監督であれば、その申告内容に関連する書類が重点的に確認されます。一般的な定期監督の場合は、基本的には労働条件や労働時間、安全衛生関係、社会保険、労働保険関係の内容を確認できる書類一式を求められる形となります。
事前連絡がある場合は調査の対象期間やこういった書類を用意してくださいという案内が来ますし、これは呼び出しの場合も同様です。
それぞれの場合で準備すべき書類は以下となります。
【労働条件関係】
・労働者名簿
・雇用契約書または労働条件通知書
・就業規則および各種規定
(賃金規定)
(退職金規定)
(育児・介護休業規定)など
・常時10人以上の労働者がいる場合はそれを届出しているかという届出の控え
・派遣労働者や有期契約社員がいる場合はその契約書
【賃金・労働時間関係】
・賃金台帳
・タイムカードや勤怠管理記録
・残業申請書や36協定届
・有給休暇の管理簿
・変形労働時間制や裁量労働制を採用している場合はその協定届や制度概要
賃金台帳は基本給や手当、残業代の算定根拠がわかる形のものが必要であり、労働基準法では過去3年分保管する義務があります。(2020年4月の労働基準法改正により保存期間が5年間に延長されましたが、当面の間は経過措置として3年間とされています。)ただし、税法上は所得税や法人税など対象となる税目によりますが、原則7年、法人で赤字があった場合などは10年とされています。このように同じ賃金台帳ですが法律によって保管義務が異なるため注意しましょう。
【安全衛生関係】
・安全衛生管理体制の組織図や選任届
(安全管理者、衛生管理者、産業医の選任届)
・定期健康診断の実施記録
・労働者死傷病報告書
・作業場ごとのリスクアセスメント記録
・特定業務(高所作業や有機溶剤等)の作業環境測定記録
【労働保険・労災関係】
・労働保険(労災・雇用保険)関係書類
(保険関係成立届、年度更新申告書)
・社会保険加入状況の確認書類
・労災事故発生時の休業補償記録
労基署調査は個人事業主が対象になることもある?
個人事業主も従業員を雇っていれば調査の対象になります。個人事業主の方が労基法などの知識や意識が低い場合が多いのではないかと思います。従業員が1人でもいて残業がある場合は、労基署に36協定を出さなければいけません。しかし、個人事業主の方は提出が漏れてしまっているケースが多いようです。1人でも従業員を雇ったら労働保険の保険関係成立届を労基署に出しますが、そもそもその届出さえ出しておらず従業員が結果的に労災に未加入ということになってしまっている場合もあります。個人事業であっても、人を1人でも雇う経営者は従業員が保護されている労働基準法や労働関係の法律に関して知識を持っていないと問題が起きるリスクがあります。
労基署調査当日の流れ
調査の内容や事業規模によって1時間程度で終わる場合もあれば、半日や丸1日、1日以上かかる場合もあります。そのためタイムスケジュールは一概には言えないのですが、丸1日の場合(従業員が数十名いるような規模の会社の場合)でお伝えしていきます。
10:00〜10:15 調査員到着・挨拶
10:15〜10:45 会社概要・労務体制ヒアリング
10:45〜12:00 書類確認①(労働条件関連)
12:00〜13:00 休憩
13:00〜14:30 書類確認②(賃金・労働時間関連)
14:30〜15:00 現場確認(必要な場合)
15:00〜15:30 指摘事項の口頭説明
15:30〜16:00 終了・今後の対応説明
現場確認は業種にもよりますが、例えば保護具や機械の安全装置の確認などが行われます。また、有機溶剤を使う場合は、その使うスペースが法律で定められている構造になっているか、換気がきちんとされているかなどが確認されます。
飛び込みの調査の場合は1〜2時間で終わる場合が多いです。
お気軽にお問い合わせください
今回は労基署調査に関して、準備すべき書類や調査当日の流れについて解説いたしました。
少しでもご不明点やご不安をお持ちの場合は是非、弊社までご相談ください。
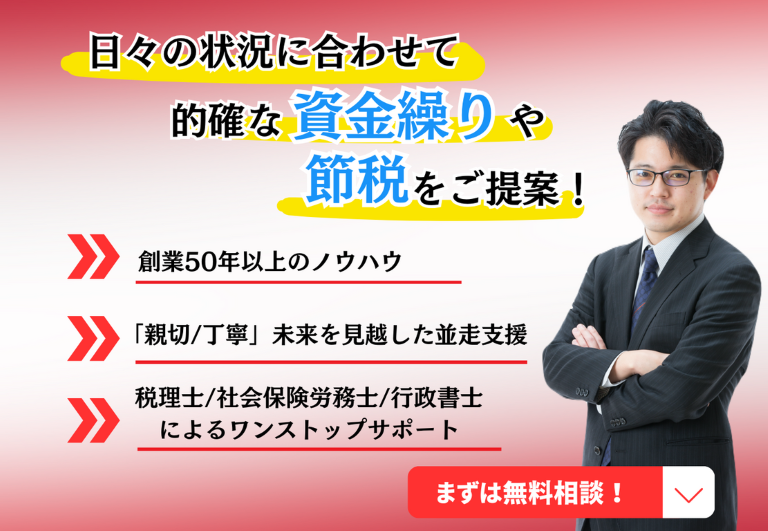
関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説!
関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説!
関連記事:【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
投稿日: 2025年11月10日 11:07 am
更新日: 2025年11月17日 11:14 am