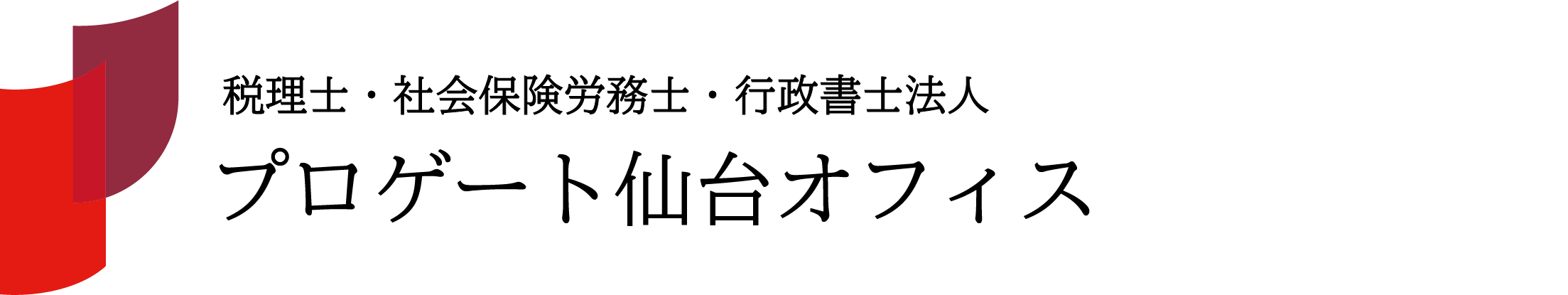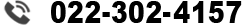- 社会保険関連
【労基署調査】調査の際に注意すべき言動やトラブルにならない企業の共通点を解説!
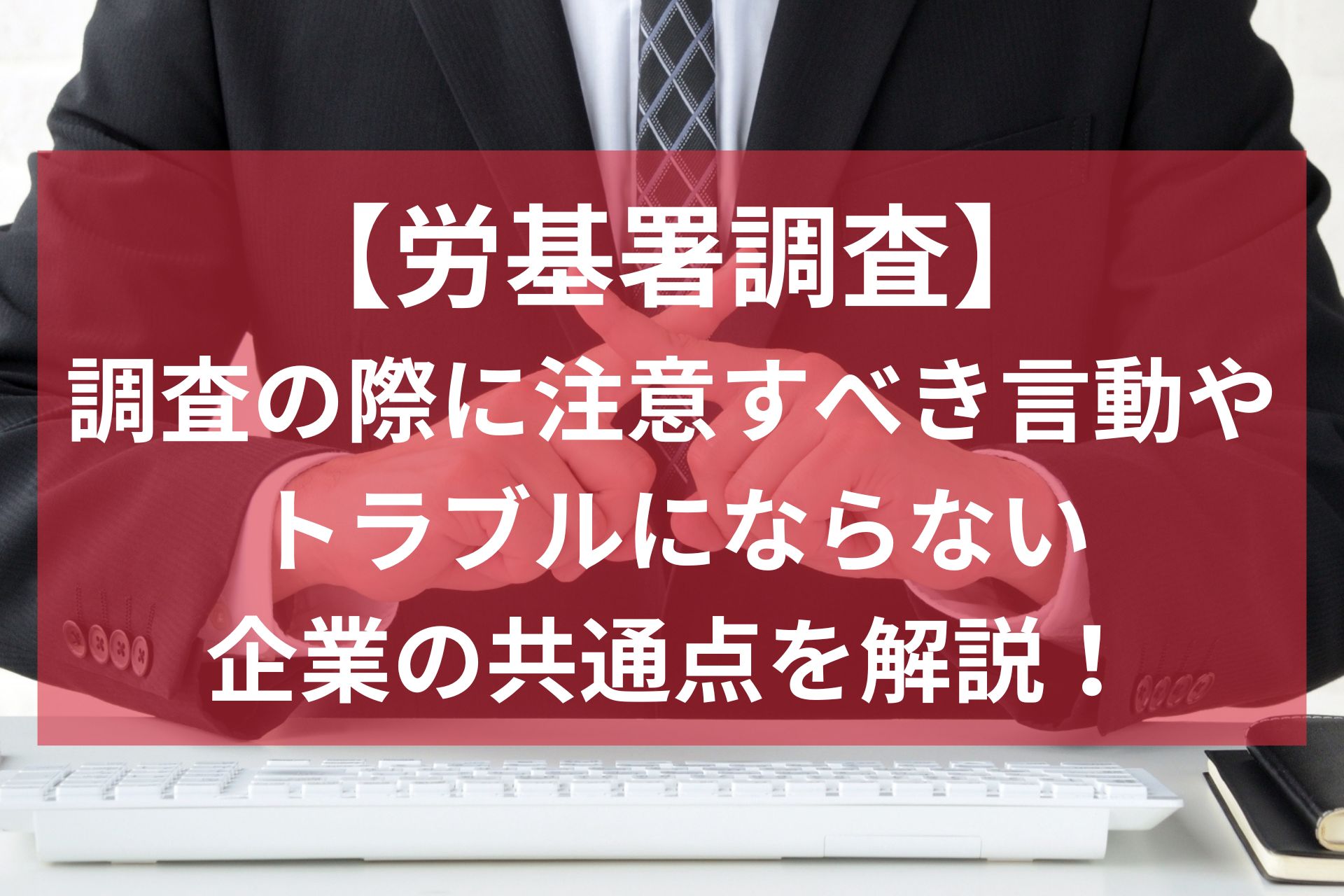
今回は労基署調査の際に注意すべき言動や調査結果の通知方法、労基署調査でトラブルにならない企業の共通点などについて解説していきます。
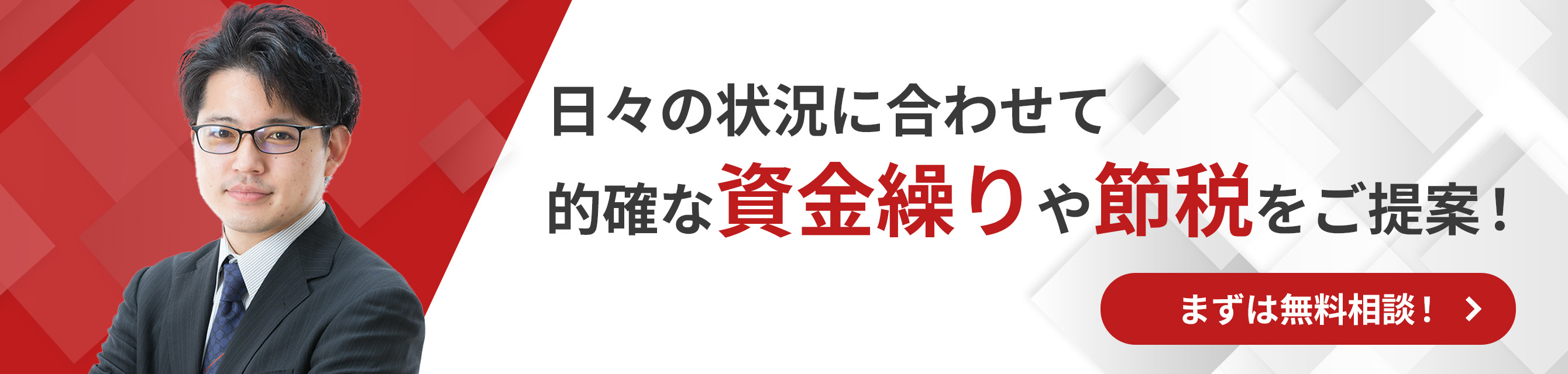
Contents
労基署調査時に注意すべき言動
税務調査と同様ですが、聞かれていないことを話さないということはとても重要です。
例えば、経営者が労務管理の実務などを総務部長などに全て任せていて労働法などをあまり分かっていないような状況で「昔はサービス残業が当たり前だった」「最近は有休を取るやつが多い」などと口走ってしまうと労働法に関するリテラシーが低い経営者だと思われてしまいます。必要なこと以上の話をしないということは重要です。
また、労基署の監督官も人です。そのため最初の印象でその後の調査の深さが変わることもあります。敵対的、防御的な態度をとってしまうとマイナスになることが多いため、冷静で協力的な姿勢を見せることが大切です。
さらに、監督官からの質問に対して即答しないことも重要です。例えば「給与計算は正しくされていますか?」と質問があり、「もちろんしています。残業代もきちんと払っています」と答えたとしても計算方法が法律に従っておらず間違っているケースもあります。そのため、即答するのではなく、記録や書類などで裏付けて答えるということが非常に重要です。口頭で不用意に答えてしまうことで後から書類と違うと指摘されてしまう原因にもなるため、「分かりません」ではなく「確認してお答えします」という形で対応するようにしましょう。
労基署調査の立ち会い依頼はできる?
労基署調査の場合は無予告が多いため、労基署調査の立ち会いをきっかけにではなく、是正勧告書が出されてその対応方法が分からないということでご依頼いただくことが多いです。
ただ、もし事前に通知があり、労基署調査に立ち会って欲しいということであれば立ち会うことは可能ですが、あまりそのようなご連絡をいただいたことはありません。
税務調査のように税法の解釈に違いがでやすいといったこととは異なり、労基署調査の場合は書類の整備や残業代の計算方法など法律を遵守しているかどうかが問題となります。そのため、調査に立ち会うというニーズは税務調査と比べると少ないです。
調査結果の通知方法
労基署調査の場合は違反があれば基本的に書類で届き、違反がなければ口頭で終わることが一般的です。違反や改善指導がある場合は、是正勧告書または指導表を渡されます。
是正勧告書は、違反の条文、具体的な是正内容や是正期限が記載されて、期限までに是正報告書を証拠書類を添付して労基署に提出します。指摘内容としては未払い残業の支払いや有給管理簿の未整備、36協定の届出について、健康診断未実施など多岐にわたります。もし間に合わない場合は、「間に合わないので〇〇までに変更してください」と連絡をすればよほどのことがなければ期限を変更してもらえたりもします。
指導表は、明らかな法律違反とまではいかないけれど改善が望ましいような軽微な場合に渡される可能性があります。ただ内容的にも改善が必要なものについては是正報告と同様に期限が定められて報告することもあり、逆に報告が必要とならない指導の場合もあります。
また、安全面で重大な危険がある場合には使用停止命令や作業停止命令が書面で交付される場合もあり、これは即時対応しなければいけません。業務の一部を停止して対応すべきケースもあります。悪質だったり重大な労働法違反があったりする場合は、是正勧告に加えて司法処分、書類送検をされることがあり、最終的には裁判や罰金となってしまう恐れもあります。
再調査の実施頻度
再調査は、調査の結果と事務所の対応次第で大きく変わってきます。結論から言うと、再調査はあまり頻繁に行われるわけではありませんが、是正勧告が未完了だったり、不十分な場合は高確率で行われる印象です。弊社が対応した範囲では、是正勧告書が出た事業所の2〜3割ほどが再調査を受けているように思います。
労基署調査でトラブルにならない企業の共通点
当日の取り繕いだけではなく、日頃の労務管理の積み重ねが重要です。これは書類を準備することだけではなく、書類と実態が一致しているかどうかです。雇用契約書や就業規則、賃金台帳、勤怠の記録などの内容がどれを見ても矛盾がないことが大切です。例えば、契約書上の労働時間と実際のタイムカードの打刻時間が一致していることなどです。規定は立派でも現場で全然守られていない状況だといけません。また、勤怠と給与計算が同じ担当者で1人の裁量だけで処理されていないか、きちんと2重チェックされているかなども大切です。
さらに、有給休暇の管理がきちんとされているかも重要です。時間外労働に関しては36協定を出して毎年更新届出済であることが必要になります。それと加えて有給休暇の管理簿が全員分揃っているか、年5日間の付与義務を満たしていない場合だと30万円の罰金のリスクもあるため注意が必要です。
あとは必ず労基署調査でも確認される安全衛生で、年1回の定期健康診断を全員に実施していることや漏れがないかなどのチェックをきちんとできているか、安全衛生管理者や衛生委員会などの選任と記録が残っているか、労災事故が起きた場合に死傷病報告書をきちんと作って提出しているかなども重要です。
日頃から労務管理をきちんと行いましょう
これらのことは書類の準備だけではどうにもなりません。労務管理は年間に1回のことが多いため、社内カレンダーでスケジュールを管理するということも大切です。
労基署調査に関して相談したいという方は、是非お問い合わせください。
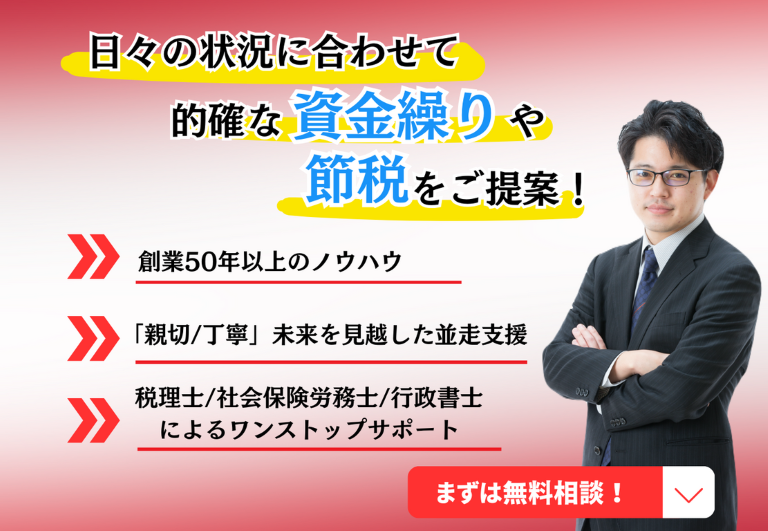
関連記事:「労基署調査」って何?調査の種類や対象になる理由を解説!
関連記事:労基署調査が入るタイミングとは?傾向やすべき対応を解説!
投稿日: 2025年11月17日 11:11 am