お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
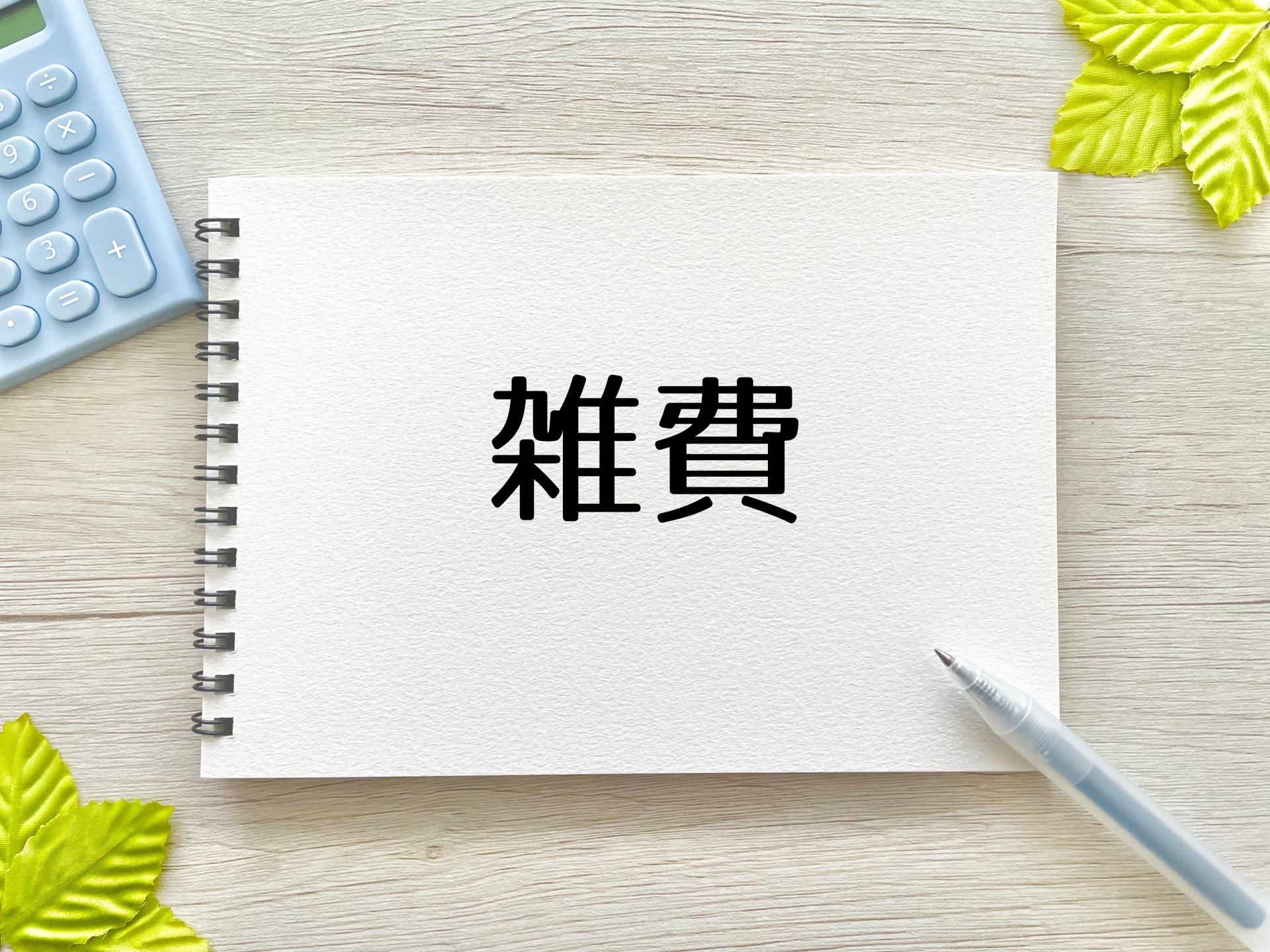
勘定科目の雑費とは?経費にできる金額や注意点などを解説!
勘定科目のひとつである「雑費」とは、ほかの勘定科目にどれも該当しない経費のことを言います。はっきりとした定義のない「雑費」ですが、「とりあえず雑費として計上しておこう」という判断は非常に危険なので注意しましょう。 自分で記帳業務を行っている経営者の方は、なんとなく「雑費」に仕訳をしている方は意外に多いように思います。 本記事では、会計業務を自分で行っている経営者の方に向け、勘定科目の「雑費」について詳しく解説していきます。 具体例なども交えて記帳の方法を紹介していきますので、会計や経理業務、確定申告を行う方は是非参考にしてみてください。会計ソフトを利用されている方は、領収証などを自動で読み取って勘定科目を推測してくれますが、これも100%正確というわけではないので、知識として身につけておきましょう。 雑費=どの科目の対象ではない勘定科目 雑費とは、損益計算書の販売費および一般管理費(以下、販管費)に含まれている費用科目のひとつです。 一言に、販管費と言っても様々な科目が存在しますが、なかでも「雑費」は、「どの科目の対象ではない勘定科目」のことを言います。 他の費用と比較して少ない支出で、臨時的・一時的に発生し、わざわざ勘定科目として別途設定するまでもない場合に「雑費」として計上されることがあります。 雑費に当てはまる経費とは? 実際に「雑費」として計上される場合によく見かける項目は、以下のような内容が挙げられます。 ・キャンセル料等の手数料 ・一時的な機材等のレンタル費用 ・ごみの処分にかかった費用 ・事業所、オフィスなどの引っ越しにかかった費用 ・振込手数料 ・クレジットカードの年会費 ・掃除やクリーニング等の手数料 ・サービスの解約違約金(但し、少額に限る)など 上記のように、経営上の重要度や優先度が低く、少額で一時的な支出であれば、「雑費」として計上することができます。また、中には「雑費」以外の勘定科目で仕訳できる費用も存在するので、必要経費を何の目的で使用したのかをはっきりとさせるために適切な勘定科目を設定するようにしましょう。 これといった決まりがないので分かりにくいかもしれませんが、雑費以外の勘定科目で仕訳できる内容であればそちらで仕訳を行い、どれにも該当しないということであれば雑費で仕訳するようにすると良いかと思います。 「消耗品費」との違いは? また、雑費とよく似た勘定科目として「消耗品費」が挙げられます。では、消耗品費とはどのような勘定科目なのでしょうか。 消耗品費=日用品など消耗する物品を購入した場合の勘定科目 消耗品費とは、日常の業務や事業を行っていく場合に使用する物品を購入した際に計上する勘定科目のことを言います。 例えば、コピー用紙や文房具、切手など、使用することで消耗・消費してくような物品を購入した場合の費用は、「消耗品費」として計上されます。 具体的な条件として以下のどちらかに該当すれば、「消耗品費」として計上することが可能となります。 購入金額が10万円未満である 使用可能期間が1年未満である 国税庁|「帳簿の記帳のしかた」 一つ目の「購入金額が10万円未満」という条件は分かりやすい基準ですが、「使用可能期間が1年未満」という基準は判断が難しく感じる方もいるでしょう。例えば、仕事に使う洋服だと上記の条件を満たす場合もあるかもしれませんが、そもそも経費計上できるかどうか。という判断も必要なため、個別の内容については税理士など専門家に相談するようにしましょう。 「雑費」と「消耗品費」の使い分けはどのようにするのか? 「雑費」と「消耗品費」は、具体的な定義のない勘定科目です。事業主や経理担当者の判断で比較的自由に経費計上が可能である反面、「雑費」と「消耗品費」の線引きの判断に迷う方も少なくないでしょう。 「雑費」は、臨時的・一時的に発生した費用のうち、ほかの勘定科目にも該当がないものに適用されます。消耗品費との明確な違いは、以下が挙げられます。 使用することによって消耗してくものかどうか 頻繁に発生するのか、それとも臨時的に発生するのか 物なのかサービスなのか 以上のポイントをふまえて「雑費」と「消耗品費」を使い分けるようにしましょう。 「雑損失」との違いは? 「消耗品費」と同じように、「雑費」と似ている勘定科目に「雑損失」というものがあります。「雑損失」は、事業の売上とは直接関係のない「営業外費用」に区分される経費の中のでも、ごく少額のために勘定科目を設定するほど重要性がなく、発生頻度もほとんどないといえる支出に対して使われる勘定科目のことです。 「雑費」と「雑損失」を区別するポイントは、本来の事業の売り上げに関わる支出かどうかという点です。 ここで紹介した「雑損失」も日々の仕訳業務ではほとんど使わない項目なので「雑費」との違いを理解するようにしましょう。 「交際費」との違いは? 「雑費」と明確に線引きしておくべき勘定科目なのが「交際費」です。「交際費」とは、取引先との関係性を維持するためや、よりよい経営を実現するための交渉をする際に発生した経費のことを言います。 例えば、取引先との交渉の際に食事を伴った場合の飲食代は「交際費」として仕訳します。またその際、取引先へ物品の贈与をした場合にかかった代金は金額によってですが、「雑費」として仕訳される場合もあります。 雑費にできるのはいくらまで? 「雑費」として計上できる金額の上限ですが、特に定められていません。事業を行う上で必要な経費はいくら使っても問題はありません。しかし、「雑費」は実際にどのようなものに支払った費用なのか把握しづらい勘定科目です。決算書は、事業の状況を正確に判断するためのものなので、雑費が多すぎる決算書は「事業の状況がよく分からない企業」として判断され、税務調査を実施される恐れがあります。税務調査には実地調査に1~2日間かかるため、その間の事業がストップしてしまい売り上げにも影響を及ぼす可能性があります。 また、実地調査後も税務署が必要に応じて書類を持ち帰り、税務署内で引き続き調査を進められるので1~2か月ほどの調査対応をしなくてはなりません。 調査の結果、申告内容に誤りがあった場合、「不足分の税金+加算税+延滞税」を徴収されるので、事業活動に支障が出ること以外に追加納税という支出まで生じてしまいます。 では、「雑費」として計上して問題ない金額はいくらぐらいなのでしょうか?望むなら限りなく「0円」に近い方がいいのですが、一般的には、かかった経費の5%~10%程度が目安かと思います。 雑費が多くなってしまった場合 まずは「雑費」が多くなりすぎないような工夫をすることですが、どうしても多くなりそうなときは、新しく適切な勘定科目として仕訳しましょう。また、内訳をしっかりと把握できるよう、摘要欄に「何にかかった費用」なのかを記載しておくことも重要です。 雑費として計上するときの注意点 「雑費」として用いる場合、ほかのどの勘定科目にも当てはまらない費用を仕訳けするときです。勘定科目に迷ってしまったときに「わからないからとりあえず雑費にしておこう」と安易に計上してしまっている方も多いかと思いますが、それは得策とは言えません。「雑費」を計上する際は注意しなければならないことがいくつかあるので以下でご紹介します。 ①他の勘定科目として計上できないか検討する 【雑費に当てはまる経費とは?】という部分でご紹介した、「雑費」によく使われている項目は、実は他の勘定科目として設定することが可能です。では、実際にどのような勘定科目で計上できるのかを一覧で解説していきますので、雑費が多くなってしまった場合は参考にしてみてください。 キャンセル料などの手数料 会議室を利用するために予約を取っていたが、どうしても都合が悪くなり急遽日程を変更しなければならなくなった際、キャンセル料が発生してしまいます。その時に発生してしまったキャンセル料は、「支払手数料」として処理することが可能です。 一時的な機材などのレンタル費用 事業運営の際に必要な機器や機材などの一時的なレンタル費用は、「賃借料」という勘定科目で仕訳することが可能です。会議などで会議室やレンタルオフィスを利用し発生した費用については、「会議費」として仕訳することが可能です。 ごみの処分にかかった費用 事業を進める際に発生したごみの処分にかかる費用は、「雑費」のほか「支払手数料」や「設備維持費」と言った勘定科目を設定できます。設備のメンテナンスの際に不用品を処分した際は「設備維持費」、自治体が発行するごみ処理券を購入した時は「支払手数料」と言うように計上することができます。 事業所、オフィスなどの引っ越しにかかった費用 事務所やオフィスを移転する際に発生する費用は「荷造運賃」でも処理が可能です。また、従業員が転勤を伴う引っ越し費用を会社で負担する場合、「福利厚生費」で処理をすることが可能です。 振込手数料 銀行での振り込みをした際に発生する振込手数料や代引き手数料は「雑費」以外にも勘定科目の「支払手数料」という項目で仕訳することができます。そのほかに、税理士などの報酬費用も「支払手数料」として処理をすることができます。 クレジットカードの年会費 法人用のクレジットカードの年会費も「支払手数料」や「諸会費」として処理することができます。クレジットカードの年会費以外にも、商工会議所や自治会、各業界の組合など、業務に関連する団体への会費も「諸会費」で仕訳することが可能です。 ②摘要欄に詳細を記載し、わかりやすくする 仕訳の際、帳簿の摘要欄に何のための費用として支出があったのかの詳細を記載することで、帳簿を分かりやすい状態にしておきましょう。摘要欄とは、伝票や各種帳簿にあるメモ欄のような役割となる部分です。 ボールペンを購入した場合、「文房具代として」だけ記載するのではなく、購入店舗や本数、購入するにあたっての目的など具体的に記載することで、ほかに購入したものとの区別がつきやすいというメリットがあります。 ③消費税区分をひとくくりにしない 「雑費」として支出の計上をする場合、消費税区分を間違えることの無いように注意することが重要です。取引には、消費税がかかる「課税取引」、消費税のかからない、または免除される「不課税取引「非課税取引」「免税取引」の3つがあります。「雑費」で計上するほとんどは「課税取引」に分類されますが、「不課税取引」や「非課税取引」に分類されるものも存在しているので注意しましょう。 「非課税取引」の例は、クレジットカードの分割払い時に発生する金利手数料や決済手数料などが挙げられます。 ④固定資産は雑費として計上ができない 固定資産は「雑費」として計上することができません。固定資産に当てはまる条件は以下の通りです。 1つあたりの購入金額が10万円以上である 使用可能期間が1年以上である 長期にわたり事業に使うものを固定資産と言います。一時的に発生した費用や、年会費などの雑費とは性質が全く異なる勘定科目となります。 固定資産の勘定科目は「減価償却費」として仕訳することができます。個人事業主や中小企業であれば、2026年3月31日までに取得の30万円未満の減価償却資産は、1事業年あたり300万円までは全額を経費計上が可能です。計上可能な金額に限度額が設けられているため、注意しておきましょう。 雑費の仕訳例をケースごとに紹介 「雑費」の仕訳をするうえで、実際の具体例を紹介したいと思います。以下の例を仕訳する際の参考にしてみましょう。 ボールペンを100本購入した場合 取引先への粗品としてボールペンを100本購入し10,000円を支払った場合、本来文房具は「消耗品費」として仕訳されますが、今回のケースだと「雑費」として処理します。 借方 貸方 雑費 10,000円 現金 10,000円 摘要:粗品用ボールペン代(〇〇文房具店) 事務所の移転で引っ越しをした場合 事務所やオフィスを移転する際、引っ越しで発生する費用は、「雑費」として仕訳されます。 借方 貸方 雑費 500,000円 現金 500,000円 摘要:引っ越し費用(〇〇引っ越しセンター) 機材のレンタル費用をクレジットカードで支払った場合 一時的な機材のレンタル費用を、今回は「雑費」として仕訳します。 クレジットカードで支払いをした場合の仕訳ですが、「決済時」と「引き落とし時」の2回に分けて記載する必要があります。決済時は「未払金」、引き落とし時は「普通預金」と記載しましょう。 [決済時] 借方 貸方 雑費 30,000円 未払金 30,000円 摘要:機材レンタル代(〇〇商会)、クレジットカード決済 [引き落とし時] 借方 貸方 雑費 30,000円 普通預金 30,000円 摘要:機材レンタル代(〇〇商会)、クレジットカード引き落とし 経理・記帳代行はお任せください 本記事で紹介した「雑費」のメリットは、どこにも分類しない費用を計上する上で便利な勘定科目だということです。一方で、雑費が多くなりすぎると何に使用したかわからなくなったり、税務調査の対象になってしまう可能性があったりとデメリットも存在します。雑費の詳細を正確に記載し、帳簿の内容をしっかりと把握しておくことが重要です。 当社では経理・記帳代行も行っております。中小企業や個人事業主の方で、簿記や会計作業にお困りの方はお気軽にご相談ください。税の専門家として決算対策はもちろん、税務全般にわたりお客様に合った適切なアドバイスをいたします。 関連記事:青色申告の個人事業主がパソコンを経費計上する場合の勘定科目や仕訳例を解説 関連記事:経費はレシートでもいい?領収書との違いや活用するメリットなどを解説 関連記事:経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説 関連記事:領収書の宛名が間違っていた!そんな場合に経費計上できるの? 関連記事:宮城県仙台市で税理士に確定申告を依頼するなら誰にどのように相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説 関連記事:事業主貸が多いとどんな影響がある?問題点や注意するべきポイントを解説

青色申告の個人事業主がパソコンを経費計上する時の勘定科目や仕訳例を解説
ビジネスによっては高額なパソコンを購入する必要がありますが、それは経費としてどのように計上すれば良いでしょうか。 今回の記事では、青色申告をしている個人事業主がパソコンを経費で計上する場合の考え方や勘定科目、仕訳例について解説していきます。 関連記事:決算申告はいつまでに申告しなければいけないの?期限や流れを解説 個人事業主の青色申告とは? 開業している個人事業主は、青色申告か白色申告のいずれかの方法で確定申告を行うことになります。青色申告とは、個人事業者が正規の帳簿を備え、一定の要件を満たした上で確定申告を行うことを指します。 個人事業主が青色申告をするメリット 青色申告には以下のようなメリットが挙げられます。 1、 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる 青色申告最大のメリットは、「青色申告特別控除」が受けられることです。単式簿記の場合は10万円、複式簿記で決算書を作成し、指定された方法で申告を行うことで最大65万円の控除があるため、大きな節税効果を得ることができます。 2、赤字を最大3年間控除できる 青色申告を行うと、今期の赤字を次年度以降の所得から差し引ける制度があります(個人事業主は最長3年、法人は最長10年)。これを「青色申告の繰越控除」といいます。 白色申告の場合は今期が赤字でも、次の期が黒字なら税金の支払いが必要です。青色申告を行うと、次年度の黒字から今期の赤字を差し引き、税金を軽減できます。これが青色申告の繰越控除です。 例えば、1年目が300万円の赤字で、2~4年目がそれぞれ100万円の黒字なら、2~4年目の所得税は免除されます。特に個人事業主として事業開始当初は黒字を出しにくいため、将来的に黒字になったタイミングで節税の恩恵を得ることができます。 3、30万円未満の資産を一括で経費計上できる 業務で購入したパソコンや機材などの資産は、取得価額が10万円未満ならその年の経費として計上されます。しかし、10万円以上なら「減価償却資産」として、数年にわたって経費に計上しなければなりません。 ただし、青色申告を行う事業主は、30万円未満の少額減価償却資産を一括して経費計上できます。利益の多い年に30万円未満の資産を購入すれば、経費計上できるので税負担を軽減できます。ただし、上限は合計300万円までです。 青色申告特別控除を受けるための条件 青色申告特別控除には3つの種類があります。控除額は65万円、55万円、10万円です。控除額は帳簿の種類や記帳方法、申告方法によって変わります。 65万円の控除を受ける条件は以下の一覧の通りです。 事業所得または事業的規模の不動産所得がある。 複式簿記で記帳している。 貸借対照表と損益計算書を提出している。 期限内に青色申告を行っている。 現金主義の所得計算の特例を選択していない。 e-Taxで確定申告を行うか、優良な電子帳簿保存法に準拠して保存している。 この条件を全て満たすと65万円の控除が受けられますが、e-Taxや電子帳簿保存を行っていない場合の控除額は55万円です。 10万円の控除は、65万円または55万円の条件を満たさない場合に適用されます。青色申告特別控除の対象は、事業所得または事業的規模の不動産所得がある方です。ただし、10万円の控除の場合は、事業的規模ではない不動産所得や山林所得も対象となります。 青色申告特別控除を受けるためには「仕訳帳」と「総勘定元帳」が必要 「仕訳帳」とは 仕訳帳は、日々の取引を発生順に記録する帳簿です。1つの取引を借方と貸方の2つに分けて記載し、それをまとめたものが仕訳帳です。仕訳帳は、総勘定元帳の作成において重要な帳簿です。 「総勘定元帳」とは 総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引内容を日付順に記録した帳簿です。仕訳帳の内容をそれぞれの勘定科目に転記します。手書きの場合、取引が発生するたびに転記する必要がありますが、会計ソフトを使用している場合は、仕訳帳の内容を元に自動的に作成されます。 青色申告の方がパソコンを経費計上する方法 事業用にパソコンを購入したときの仕訳には、さまざまなパターンがあります。まず最初に確認しておきたいのは、パソコンの購入金額についてです。購入金額が一定の金額以上になるかどうかで、資産になるか、あるいは当期の費用になるかが異なってきます。 さらに、購入形態にも注意が必要です。現金一括で購入する以外にも、クレジットカードを利用して分割支払いで購入するパターンや、購入せずにリースを利用することも考えられます。クレジットカードやリースでパソコンを取得した場合、勘定科目も変わってきます。それぞれの経費計上方法について解説していきましょう。 取得価格は税抜か、それとも税込か 消費税の扱いは個々の会計方式により異なります。税込み方式では消費税を含めた金額、税抜き方式では消費税を含まない金額で計算されます。 取得価額別の処理方法 ・10万円未満の場合 取得価格が10万円未満であり、使用可能期間が1年未満の場合、経費処理が可能です。 ・10万円以上20万円未満の場合 取得価格が10万円を超える場合、資産計上が必要です。20万円未満の場合は、一括償却資産処理、少額減価償却資産の特例処理、または通常の減価償却処理のいずれかを行います。 ・20万円以上30万円未満の場合 同様に、取得価格が10万円を超えるため資産計上が必要です。その後、少額減価償却資産の特例処理、または通常の減価償却処理を行います。 ・30万円以上の場合 資産計上を行い、通常の減価償却処理を行います。 ※少額減価償却資産の特例処理は、青色申告の法人と個人事業主であることが条件です。 PCの取得金額が10万円未満の場合の計上 10万円未満のパソコンは、一括して経費計上できます。10万円未満か否かの判断は、税込経理をおこなっている課税事業者と免税事業者であれば税込で判断し、税抜経理をおこなっている課税事業者は税抜で判断します。10万円未満のパソコンを経費計上する場合には「消耗品費」として仕訳をするのが一般的です。 パソコンの取得価格が10万円未満の場合の仕訳方法 パソコンの取得価格が10万円未満の場合、全額を一括して「消耗品費」として計上されます。以下に、現金およびクレジットカードでの購入の仕訳例を示します。 現金での購入の場合 借方 貸方 消耗品費 80,000円 現金 80,000円 クレジットカードでの購入の場合 1、購入時の仕訳 借方 貸方 消耗品費 80,000円 未払金 80,000円 2、クレジットカード支払時の仕訳 借方 貸方 消耗品費 80,000円 預金 80,000円 パソコンの購入金額が10万円以上20万円未満の経費計上方法 10万円以上20万円未満のパソコンの経費計上には3つの方法があります。順に解説していきましょう。先ほどと同様に、10万円以上20万円未満か否かは、税込経理をおこなっている課税事業者と免税事業者であれば税込で判断し、税抜経理をおこなっている課税事業者は税抜で判断します。 1、パソコンを耐用年数で減価償却する 耐用年数とは、固定資産の使用可能な期間を指します。多くの場合、パソコンの耐用年数は4年とされています。この場合、耐用年数に応じて価額を分割して減価償却を行います。償却費用は勘定科目「備品」または「工具器具備品」で処理されます。 具体的な計算方法は、以下の通りです。 購入価格 × 償却率 × (使用月数 / 12) 例えば、15万円のパソコンを購入した場合、1年目の償却費用は以下のように計算されます。 1年目:15万円 × 0.25 × (12ヶ月 / 12=1) = 37,500円 このように、購入月によって償却期間を算出し、それに応じて償却費用を計算します。1年目から5年目までの償却費用を計上し、仕訳の際には「減価償却費」として記録します。 2、パソコンを一括償却資産として経費計上する パソコンの購入金額が10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産で処理できます。資産は耐用年数に基づき減価償却していきますが、一括償却資産は本来の耐用年数にかかわらず、3年にわたって1年あたりに3分の1ずつ減価償却をすることが認められます。 個人事業主の場合でも、10万円以上20万円未満のパソコンは一括償却資産として取り扱うことができます。通常4年かかる償却期間を3年に短縮することができるので、早期償却したい場合におすすめの方法です。 この方法では、1年あたりの償却費用が通常より多くなるため、年度ごとに経費として計上する額が増えます。また、一括償却資産として処理する場合は、償却資産税の対象外となる利点もあります。さらに、月割計算の手続きも不要です。購入時期に関わらず、その年度に3等分の費用を計上できます。 例えば、15万円のパソコンを現金で購入した場合、1年あたり5万円を3年間で処理します。仕訳の例は以下の通りです。 借方 貸方 一括償却資産 150,000円 現金 150,000円 個人事業主の場合、この経理処理に加えて、収支内訳書や青色申告決算書に必要事項を記入する必要があります。 3、青色申告の個人事業主なら少額減価償却資産の特例が利用可能 少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に適用され、費用を一括で経費に計上できる制度です。これまでと同様に30万円未満か否かは、税込経理をおこなっている課税事業者と免税事業者であれば税込で判断し、税抜経理をおこなっている課税事業者は税抜で判断します。 また、この特例は期間限定の制度であり、2年ごとに延長されています。現在は2026年3月31日までに取得し、使用を始めた資産が対象となります。 少額減価償却資産の特例が利用できる対象者 少額減価償却資産の特例は青色申告の特典ですので、青色申告の法人と個人事業主であることが条件です。具体的には、以下の条件を満たす事業者が対象となります。 常時使用する従業員数が500人以下 適用を受けたい事業年度の平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円以下 資本金または出資金の額が1億円以下であり、通算法人でない 資本金または出資金の額が1億円を超える法人やその100%子会社から、2分の1以上の出資を受ける法人ではない パソコンの購入金額が30万円以上の場合の経費計上方法 取得価額が30万円を超えるパソコンについては、資産の勘定科目である「工具器具備品」として計上する必要があります。30万円以上の資産については、「少額減価償却資産」などの特例措置は適用されません。 従って、そのパソコンの法定耐用年数に従い、定率法または定額法のいずれかの減価償却方法を選択し、経年による価値の減少分を適切に費用計上していく必要があります。定率法と定額法のどちらを採用するかは、事業主の判断に委ねられています。 取得時に「工具器具備品」勘定を借方記入し、減価償却費の計上に伴い同勘定の貸方に転記する会計処理が必要です。減価償却の仕訳は毎期継続的に行う必要があり、最終的にはパソコンの帳簿価額がゼロになるまで続けます。 このように、30万円を超える高額なパソコンの場合は資産計上が原則となり、定められた耐用年数に応じた適正な減価償却処理を行いましょう。 パソコン周辺機器の経費計上方法 ノートパソコンであれば、本体とモニター、キーボードが一体となっていますが、デスクトップパソコンを購入する際には、別途モニターを購入したり、その他の付属品を購入する必要がある場合もあります。 このような場合、減価償却の対象であるかどうかや、取得価額の範囲はどうかが気になる場合もあります。基本的には、本体と合わせてモニターやキーボードが一体として機能するかどうかによって資産かどうかが判断されます。 例えば、モニター、キーボード、ハードディスクを別々に購入した場合でも、それらを一体として使用することを前提としている場合、それらの合計額を取得価額として扱います。しかし、パソコンを5台購入した場合は、それぞれが単独で機能するため、1台ずつに分けて取得価額を考えます。 また、既にパソコンが1台ある状態でモニターを別途購入した場合は、モニターを別の資産として考えることもできます。これは、すでに機能しているパソコンにモニターを追加するだけであり、モニターが単独で機能する資産と見なすからです。 外部ストレージやケースなども個別の資産として扱うことができます。 なお、パソコンの運送料や購入手数料は付随費用として考えられ、これらは取得価額に含める必要がありますので、注意が必要です。また、取得価額に消費税を含めるかどうかも重要なポイントです。税抜経理方式を採用している場合は、取得価額に含めませんが、税込経理方式の場合は含める必要があります。 パソコンをリースする場合の経費計上方法 最後に、パソコンを購入ではなくリースによって取得する場合の経費計上方法を解説していきます。パソコンのリースに伴う経費処理は、リース期間や契約の内容に応じて3つのケースが考えられます。それぞれ解説していきます。 所有権移転ファイナンス・リース取引の経費処理 所有権移転ファイナンス・リース取引は、通常の購入と同様の売買処理が行われます。このリースはリース期間中に解約できず、フルペイアウトが必要な取引を指します。期間終了後にはリース資産の所有権が借手に移ります。例えば40万円のパソコンをリースした場合の仕訳は以下の通りです。 借方 貸方 リース資産 400,000円 リース債務 400,000円 摘要:ノートパソコン 所有権移転外ファイナンス・リース取引の経費処理 所有権移転外ファイナンス・リース取引も、購入時の処理は基本的に所有権移転ファイナンス・リース取引と同様ですが、減価償却費の計算方法が異なり、「リース期間定額法」によって計算されます。所有権が移転しないため、減価償却費はリース期間に応じて計算されます。 オペレーティング・リース取引の経費処理 オペレーティング・リース取引は「リース料」として経費処理されます。口座からリース料が引き落とされた場合の仕訳は以下の通りです。 借方 貸方 リース資産 400,000円 リース債務 400,000円 摘要:リース料の支払い 個人事業主がパソコンをリースした場合は、所有権移転ファイナンス・リース取引が売買処理、オペレーティング・リース取引が賃貸借処理となります。ただし、仕事用とプライベート用の併用時は、家事按分が必要で、購入することに比べるとメリットばかりではなくデメリットや手間があることも意識しておきましょう。 適切な仕訳処理を把握しよう 個人事業主がパソコンを経費計上する際の勘定科目と仕訳方法は、パソコンの取得金額によって異なります。 10万円未満の場合は全額を当期の経費(雑費や消耗品費等)に計上します。10万円以上20万円未満では、原則的に資産の備品勘定で計上し減価償却します。一括償却資産扱いも可能で、この場合は3年で全額償却します。また青色申告の中小企業や個人事業主は少額減価償却制度を活用し全額即時償却することもできます。 30万円未満の場合も同様に、原則は資産計上と減価償却ですが、青色申告の中小企業や個人事業主であれば少額減価償却資産の特例で全額即時償却が認められています。また、クレジットカード支払いやリースなど分割払いをしている場合には異なる仕訳が必要になります。 このように、パソコン購入時の経費計上は金額によって方法が変わるため、適切な勘定科目と仕訳処理を把握する必要があります。また制度の適用要件を把握するなどの注意点があります。適切に経費計上をしなければ税務調査の際に問題になる可能性があるため、税理士に依頼し、正しく経費計上を行うのが安全で確実です。 税理士法人プロゲートでは、個人の青色申告や経費計上に関するアドバイス、領収証の仕訳などの実務にも対応しております。まずはお気軽にご相談ください。 関連記事:経費はレシートでもいい?手書き領収書との違いや活用するメリットなど詳しく解説! 関連記事:経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説 関連記事:個人事業主の融資はいくらまで受けられるのか? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説

経費はレシートでもいい?領収書との違いや活用するメリットなどを解説
事業を行うえで発生した費用は、経費として処理されますが、経営者や個人事業主などの事業者だけでなく、多くのビジネスパーソンがその費用を立て替えた経験があるでしょう。多くの場合、経費だと証明するためには領収書が必要になり、領収書がないまま経費精算することは基本的に認められていません。 経費を立て替えた際に「領収書を貰い忘れてしまった」「レシートで代用したい」というケースもあると思います。 そこで今回の記事では、経費はレシートでも有効なのか、レシートと領収書の違い、そして領収書の代わりにレシートを活用するメリットとデメリットについて解説します。 この記事を読んで「レシートで代用できるなら活用したい」と思う方の参考になればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。 経費精算はレシートでも可能です 経費精算には領収書が必須だと思われていますが、実際にはレシートでも経費精算は可能です。その理由は、支払い先や領収書が発行された日付や支払い金額が表記されていれば、領収書はもちろん、レシートも有効とされています。 領収書の本来の目的はお金を支払ったことの証明です。税法上において、領収書は「金銭や有価証券の受理を証明する書類」とされています。また、消費税法の関係する条文の中にある仕入れに係る消費税額の控除には、「事業者に交付する請求書、納付書やこれに類する書類」との記載があるため、必ずしも領収書である筆等はありません。領収書やレシートは「これに類する書類」に該当するので、法的には領収書もレシートも同等の効力を持つ書類という扱いになります。但しインボイス制度の導入後は、レシートや領収書という区別ではなく、インボイスとなる書類の保存が必要となります。 会社はなぜ領収書を活用するの? 同じ金額を証明するものであれば、領収書ではなくレシートで良いのではないかと思う方もいるでしょう。そこで、レシートと領収書の違いや会社が領収書を重視している理由、レシートや領収書を保存する期間を解説します。 レシートと領収書の違い レシートと領収書の最も大きな違いは、記載されている内容です。レシートには日付・商品名やサービスの品目・単価・支払い方法・発行者などが印字されます。一方の領収書にはレシートに印字される情報に加えて、購入者が誰なのかを表す「宛名」が記載されます。 一般的には領収書の方が正式なものというイメージを持つ人が多いですが、税務上は違いがありません。 会社がレシートより領収書を重視する理由 経理上は領収書でもレシートでも問題ありませんが、多くの会社では領収書の提出を重視します。その理由は、これまでのビジネス習慣の延長だからです。 レジから出力されるレシートは「感熱紙」という、熱を利用して印字する方法を採用しています。この方法だとインクの交換の必要がないため、スペースの限られたレジの印字方法として普及しました。 しかし、昔のレシートは感熱紙の性能が低かったため、レシートの文字は1年もすると消えてしまうので財務関係の保管資料として役に立ちませんでした。近年の感熱紙は性能が上がっており、消えにくくなっていますが、それでも「熱に当てると文字が読めなくなる」というリスクが完全に無くなったわけではありません。 一方の領収書は手書きやインクによる印刷で記入されるため、10年の保管にも対応できます。 このことから「レシートは文字が消えるから、財務書類として使えない」という認識を持つビジネスパーソンは、特に年齢が高いと一定数存在するため、「経費精算する場合はレシートを認めない」というルールがある会社は現在でも数多く存在します。 レシートと領収書の保存期間 法人の場合は会社の規模に関わらず、7年間保管する必要があります。特に領収書は取引を証明する書類といわれる証憑書類とされ、一定期間の保管が義務付けられているので、勝手に破棄できません。 7年間というのはレシートや領収書が発行されてからではなく、決算日の翌日から2か月後の法人税申告期限からです。 また、個人事業主の場合は青色申告の方だと法人と同様に7年間、白色申告の方は5年間、青色申告の方でも前々年の所得が300万円以下の場合は白色申告と同様に5年間となります。青色申告・白色申告いずれの場合も確定申告の期日を起点に保管しないといけないので注意しましょう。 過去の領収書を電子保存する場合は、事前に申告が必要 過去に作成した領収書は、電子帳簿保存法により紙で受領した領収書も電子化し、スキャナ保存できます。以前は事前に申請書を提出しなければ保存できず、スキャンできる期限も短かったため紙媒体での管理が一般的でした。しかし、近年は法改正によりスキャナ保存が認められ、電子データで保存するハードルが下がりました。 関連記事:領収書の宛名が間違っていた!そんな場合に経費計上できるの? レシートは経理上有効なのか? 経理上は、領収書を使用してもレシートを使用しても問題ありません。消費税法では、経費精算に必要な証拠書類には以下の必要事項が定められています。 書類作成者の氏名または店名などの名称(店名) 取引年月日 取引内容 取引金額 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名) レシートは宛名はありませんが、店名・日付・品目・単価といった取引を証明するために必要な項目が印字されています。人の手による改ざんの可能性がないことから、宛名が「上様」と記載されている領収書や、詳細が「お品代」と記載されており、取引の内容が不明な領収書よりも、レシートの方が税務調査では疑われません。 領収書やレシートの保管方法 続いて、領収書やレシートの保管方法について解説していきましょう。 スクラップブックやコピー用紙に貼る 最初に、最もポピュラーなのは、のりで貼る方法です。これは、昔から経理の現場で行われてきた方法です。スクラップブックに貼ることが一般的ですが、個人的にはコピー用紙に貼ることをおすすめします。コピー用紙はスクラップブックと比べて、安価であること、常に事務所にあるページを追加・交換することができることなど、手軽さと自由度が高いのが特長です。 領収書やレシートは日付順に、まっすぐに、重ねないようにと、非常に細かい注意が払われがちですが、実際にはそこまで丁寧に貼る必要はありません。最低限、月ごとに分けていれば、少し歪んだり重なっていても問題ありません。 保管を効率化するポイント 領収書の数が増えると、従来の方法では追いつかなくなることがあります。そんなときは、以下の方法で工夫すると効果的です。 分類方法を工夫する 企業が大きくなると、月ごとの分類だけでは不十分な場合があります。レシートの量も増え、複数人で共有する機会も増えるからです。その際には、以下のような分類方法を考えてみてください。 支払い方法別(現金、クレジットカード、振込など) 従業員別(立替払い) 部門別 勘定科目別 取引先別 これらを参考に、会社の業態に応じて、わかりやすい分類方法を採用しましょう。 個人事業主の場合は、月ごとにざっくりと分けるだけで十分です。 入力→保管の順序を取る 一般的には、レシートや領収書を保管してから入力する方法が一般的ですが、オススメは逆に「入力→保管」の順序で対応することです。 「保管→入力」の順番で処理をすると、入力したかどうかの確認に手間がかかり、重複や抜けが生じやすいこと、また丁寧に貼らないと入力が難しいといったデメリットがあるうえに非効率的です。 その点、「入力→保管」の順序であれば、未保管のものは全て入力すれば良く、適当に貼っても問題ないがなく、保管したものは見直す必要がないなどのメリットがあるので効率的です。 この方法を採用すると、レシートが溜まらずに入力を行うようになります。また、入力するまで保管できないため、机がレシートで埋まる前に入力を済ませたくなります。 レシート活用時のメリットとデメリット 続いて、領収書の代わりにレシートを活用するときのメリットとデメリットを2つずつ紹介します。 レシートを活用する2つのメリット レシートを活用するメリットは次の2つです。それぞれの内容について紹介していきましょう。 買い物の内訳が詳細に分かる 最初のメリットは、レシートには買い物の内訳が表示されていることです。例えば、「11月22日にコピー用紙などの事務用品を現金で7,344円払った」と書かれていたとします。 領収書を発行した場合、基本的には金額のみが書かれています。ですから、その領収書を貰った取引でどんな買い物をしたか、細かい内訳がわからなくなってしまいます。一方、レシートは購入品目が詳しく書かれているので、買い物の内訳を把握するのは領収書よりもレシートの方が優れています。 日付や金額が正確 もう一つのメリットは、レシートに表示される日付や金額が正確なことです。手書きの領収書の場合、手書きなので日付が抜けていたり金額が間違っていたりという場合があります。不備があった場合、日付であれば訂正できますが、金額の間違いは訂正できません。 お店にもう一度行って訂正してもらうか、その領収書を経費に入れるのを諦めることになります。その分レシートは機械が読み込んでくれるので、間違いが手書きの領収書よりも遥かに少なくなります。 レシートを活用する2つのデメリット レシートを活用する上では、デメリットも把握しておく必要があります。レシートを活用する場合のデメリットは次の2つです。 宛名の記載がない 一つ目のデメリットは、レシートには宛名の記載がないことです。宛名がないということは、実際に誰がその買い物を行ったかをレシートだけを見ても分からないということになります。私用のレシートを事業の経費として計上して、税務調査で不正が発覚することは実際に起こっています。一切の不正がなかったとしても、本当に事業の経費として使ったのか判断しづらくなり、税務署から疑われるきっかけになりやすいです。 要件を満たさない領収書が発行されるリスクも 個人事業のお店では店名と代金しか書かれていない簡易的なレシートを用いている場合があります。例えば、店名と代金しか書かれていないと領収書の記載要件を満たしているとはいえないので、経費に計上できません。領収書を作成するのが会計に精通していない店員が作成した場合、「正しい領収書を作ってほしい」と頼んでも、その店員がそもそも正しい領収書の記載事項を知らないので、正しい領収書が発行されないリスクもあります。 レシートを使うときのチェックポイント ここでは、領収書の代わりにレシートを使うときにチェックすることを3つ紹介します。 記載内容をチェックする 領収書と同じようにレシートを証明書として使うには、次の8つが明記されているか確認しましょう。 取引年月日 支払金額 商品・サービスの明細 レシートの発行元 宛名 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 税率ごとに区分した消費税額等 税率ごとに区分して合計した対価の額 不足している情報があれば、レシートの余白や裏に手書きで不足情報を記入しておきましょう。また、インボイスとして保存する場合は、買手側は情報を追記できないので注意してください。 公私混同していないか確認 レシートで経費精算する前に内訳をチェックし、仕事で必要な商品やサービスのみのレシートであるか確認しておきます。もしプライベートで利用した商品のレシートが混ざっている場合は、レシートを一覧し、仕事用の商品を丸で囲んだりマーカーで印をつけておいたりして、仕事用で使っているレシートの金額のみを経費として計上しましょう。プライベートで購入した商品のレシートが混ざっていても、区別して経費として認められる項目のみ計上すれば問題ありません。 関連記事:事業主貸の上限は?事業主貸の概要、仕訳の方法やポイントを解説 5万円以上の買い物は収入印紙の有無をチェックする 税抜5万円以上の買い物をした場合は、売上金額に応じて収入印紙が必要になります。レシートも領収書と同様に必要になるため、レシートを受け取る際には収入印紙が貼付されているかチェックしておきましょう。 会計ソフトを使い、様々な経理業務を行う 領収書を用いた経費計上などのさまざまな経理業務をスムーズに行うために、会計ソフトを選ぶのもおすすめです。会計ソフトの中には、初めて導入する方でも簡単に使えるクラウド会計ソフトが多くあり、初年度無料でたくさんの機能が使用できるなど初心者向けのものもあります。 また、日々入力したデータは顧問の税理士や会計事務所とクラウド上で共有できるものもあるので、経理業務がわからない個人事業主におすすめです。 領収書とレシートに関するよくある質問 ここでは、領収書とレシートに関するよくある質問を紹介します。 領収書とレシートの両方は貰えない? 領収書とレシートの両方は貰えません。なぜなら、領収書とレシートは双方が同じ取引に対する支払証明であるからです。一般的にレシートは購入時に自動的に発行されるもので、領収書は購入後に発行される公式な証拠書類です。 領収書とレシートの両方の証明書類を発行すると、二重精算となりトラブルのもととなります。しかし、勤務先によっては「宛名なしの領収書は経費精算に使用できない」といった独自のルールが決まっている場合があります。 その場合は、飲食店などに事情を説明して手書きの領収書を発行してもらい、レシートは発行者側に返却しましょう。 レシート以外に領収書代わりに経費になるものは? レシート以外にも代用できる書類は次の通りです クレジットカードの利用明細書 銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳 オンライン販売の確認メール・取引画面のキャプチャー画像 ご祝儀袋の表書きコピー・香典返しの挨拶状など クレジットカードの利用明細書とは、クレジットカードを使ったときにレシートと一緒に渡されるクレジット売上票と表記された書類です。レシートと同様に、取引年月日や支払金額などが記載されている必要があります。 しかし、クレジットカード会社からの請求明細書等は、商品やサービスの提供元が作成した書類ではないため、代用できないので注意しましょう。 銀行振込の取引の際に振込金受取書(振込明細書)が発行されます。振込金受取書は銀行が発行するものなので厳密には領収書ではありませんが、支払の証憑として代用できます。 オンライン通販やダウンロード販売などのオンラインで取引した場合は、確認メールや取引画面のチャプチャー画像が支払いの証明になりますが、納品書は領収書の代用品にはならないので、注意しましょう。 お祝い金を支払ったときはご祝儀袋の表書きのコピー、香典を支払ったときは香典返しの際の挨拶状(お礼状)などが支払いの証明になります。冠婚葬祭の会費については、招待状や告知メールを保存して代用しましょう。 経費に関するお悩みはお任せください 今回は、経費は領収書の代わりにレシートで代用できるのか、レシートを活用するメリットとデメリットなどをまとめました。会社や個人事業主にかかわらず、金銭に関することは知識がない素人が間違えたことをすると人生を左右します。 そのため、適切な対応を行うには、状況に応じた方法を理解して必要に応じて顧問税理士に相談しましょう。 税理士法人プロゲートでは、法人及び個人事業主様の会計業務をサポートしておりますので、経費清算に関連するお悩みがあればお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。 関連記事:経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説 関連記事:宮城県仙台市で税理士に確定申告を依頼するなら誰にどのように相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説 関連記事:事業主貸が多いとどんな影響がある?問題点や注意するべきポイントを解説

経費計上のタイミングはいつがベスト?考え方を解説
起業直後の会計業務をよく分からないまま進めていませんか? 事業活動で発生した経費を計上し、帳簿に記載することは事業者の義務として定められていますが、そのタイミングはいつがベストなのでしょうか。中には会計業務を進めるものの経費計上の方法がわからず、決算が迫ってから相談に来る方もいます。 そこで今回の記事では、経営者および経理担当者の方に向けて、経費を適切に計上するタイミングや方法について解説します。経営者をされるなら知っておきたい内容ですので参考にしてください。 経費計上できる項目について まずは経費計上できる項目について紹介していきます。 「経費」の考え方 経費とは、事業を運営する上で必要な支出や費用のことを指します。 経費は、事業の利益を算出する際に、収入から差し引くことで算出し、正確な利益の計算や健全な経営判断に欠かせない要素です。具体的には以下のような項目が挙げられます。 事業運営に必要な消耗品や備品の購入費用 従業員の給与や賞与 事業用の通信費や郵送費 事務所や施設の賃料 事業用の交通費や旅費 広告宣伝費用 事業関連の講習や研修の費用 事業に関連する雑費やその他の一般管理費用 経費計上できる主な科目(1)消耗品費 経費計上できる代表的な科目として挙げられるのが消耗品費です。事業運営に必要な消耗品や備品の購入費用を指します。消耗品とは、一度使用するとその価値が減少し、次第に価値を失っていくものを指します。これらの消耗品は業務や生産活動に不可欠であり、日常的な支出として発生します。 そのため、毎期の業務に必要な消耗品の購入は、企業活動における常識的な経費です。 具体的には、オフィス用品や清掃用品、ドライバーや工具、機器の消耗品、事業で使用する文房具や消耗品などが該当します。これらの費用は、事業の日常的な運営に必要不可欠なものであり、経費として計上されます。 経費計上できる主な科目(2)旅費・交通費 こちらも一般的な科目ですが、旅費・交通費も経費計上が可能です。業務目的の移動や出張に必要な経費であり、企業の業務活動に直接関連しています。これらの費用は、従業員が業務目的で外部に移動する際に発生するため、経費精算の対象となります。 具体的には、交通機関の運賃やレンタカーの料金、宿泊費、食事代などが該当します。また、出張や移動に関連するその他の費用も含まれます。これらの費用は、事業の拡大や顧客との交流を目的とした活動において発生するものであり、事業運営の一環として経費として計上します。 経費計上できる主な項目(3)交際費 経費計上できる主な項目の3つ目は交際費です。交際費は、業務上の人間関係を築き、ビジネスの円滑な進行や取引の促進に寄与するための費用です。取引先や顧客との信頼関係を深め、ビジネスの機会を広げることを目的としています。 具体的には、飲食代や娯楽費、プレゼント代などが該当します。交際費は、ビジネス関係の構築や維持に必要な費用であり、顧客や取引先との信頼関係を築くために支出されることが一般的です。したがって、これらの費用は事業運営上必要な経費として計上されます。 経費計上できる主な項目(4)従業員の給与・賞与 経費計上できる項目として給与・賞与も挙げられます。給与は、従業員が企業で提供する労働や役割に対して受け取る定期的な報酬です。給与は通常、月給や時給として支払われ、従業員の働いた時間や提供した役割に応じて計算されます。また、賞与は従業員が企業での業績や成果に対して受け取る追加の報酬です。通常は年末賞与や利益に応じた賞与として支払われます。 賞与は従業員が企業の業績向上や目標達成に貢献したことを評価し、励ますために支給されます。従業員のモチベーション向上や企業の業績向上に寄与します。これらの費用は、従業員を雇用し、事業運営に不可欠な役割を果たすために発生するものであり、経費として計上可能です。 発生主義か現金主義かで異なる 経費計上する場合、発生主義と現金主義の2つの方法があり、計上のタイミングが異なります。それぞれの考え方について紹介していきます。 発生主義とは 発生主義は、会計処理の原則の一つであり、収益や費用を収入や支出が発生した時点で計上する考え方です。つまり、取引が実際に行われた日付ではなく、契約や請求など、取引が発生した時点で収益や費用を帳簿に記載するという考え方です。 発生主義の場合、収益は商品やサービスが提供された時点で計上されます。例えば、商品が販売された時点でその売上が計上され、役務が提供された時点でそのサービス料が計上されます。同様に、費用もその費用が発生した時点で計上されます。例えば、商品の仕入れやサービス提供のための経費が発生した時点で、その仕入れ費用や経費が計上されます。 発生主義の利点は、取引の発生と実際の現金のやり取りが同じ時期でない場合でも、会計上の記録が正確に収益や費用を反映することができることです。これにより、会社の業績や財務状況を正確に把握することができます。 一方で、発生主義の欠点は、収益や費用の計上が現金のやり取りとは独立して行われるため、キャッシュフローと利益が一致しない場合があることです。 企業会計の場合は原則「取引が発生した時点」で計上する 企業会計においては、原則として発生主義が採用されます。企業は事業を行う過程で収益を生み出し、費用を支出します。発生主義は、この収益と費用が経済的な事象が発生した時点で計上されるべきだという考え方です。発生主義での会計処理を行うと、商品やサービスの提供、仕入れ、サービスの受け取りなどの経済的な事象が発生した時点で、それに関連する収益や費用を計上することで、企業の業績や財務状況を正確に反映することができます。 また、発生主義は収益と費用の対応原則を重視しています。収益が発生した際にそれに関連する費用も同時に計上することで、企業の利益を正確に把握することができます。これにより、企業の経営者や投資家などが企業の業績や財務状況を適切に評価し、意思決定を行うことが可能となります。 現金主義とは 現金主義は、会計処理において収益や費用を現金の受け渡しや支払いの発生時点で計上する原則です。つまり、収益は現金が実際に入金された時点で計上し、費用は現金が実際に支払われた時点で計上する処理方法です。 発生主義では、取引が発生しても現金の授受がない限り、収益や費用を計上しません。そのため、売掛金や買掛金などの未収入金や未支払金は会計上の収益や費用として計上されません。 現金主義は取引が確定しているかどうかに関わらず、現金の受け渡しや支払いが行われた時点で計上されるため、現金の出入りが簿記上の記録に直接反映されます。これにより、企業のキャッシュフローや現金の流れを正確に把握することができます。 現金主義を採用する場合には条件がある 現金主義で帳簿作成を行うためにはいくつか条件があります。まずは「青色申告」の事業者であることです。青色申告を行うためには、事業者は所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。提出期限は申告を行う年の3月15日までですが、新規に開業した場合は、開業日から2か月以内に提出しなければなりません。その上で、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出します。 ※手続きについては下記の国税庁HPよりご確認ください。 国税庁HP:現金主義による所得計算の特例を受けるための手続 また、現金主義の帳簿付けを行う条件として、小規模事業者であることも挙げられます。小規模事業者の定義は、「その年の前々年分の事業所得の金額および不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300万円以下であること」とされています。この条件に該当する場合にのみ、現金主義の帳簿付けが認められます。 経費計上するタイミング 発生主義と現金主義の違いを経費計上するタイミングごとに見ていきましょう。 発生主義の場合 これまでご紹介したように、発生主義に基づく経費計上のタイミングは、費用が実際に発生した時点で計上されます。具体的には以下のような例が挙げられます。 商品やサービスの提供が完了したタイミング 請求書を発行したタイミング 領収書を発行したタイミング どちらのタイミングで経費計上するかは企業によって異なりますが、多くの場合は請求書や領収書といった会計上必要な書類に記載されている日付をタイミングとしています。 現金主義の場合 現金主義に基づく経費計上のタイミングは、支払いが行われたタイミングです。非常にシンプルではありますが、先述したように現金主義を採用する場合には条件があることや、ビジネスが成長していくと現金主義の帳簿付の条件から外れる可能性もあります。 面倒な会計業務はお任せください 今回は経費計上のタイミングについてまとめました。経費計上のタイミングは発生主義と現金主義で異なりますが、今回紹介したポイントや注意点を正しく抑えておけば問題ありません。ですが、経費計上できる科目や、現金主義でクレジットカード決済を行った場合の帳簿記載のタイミングなど、個別に相談したい事柄もあるかと思います。 そんな場合にはお気軽に私たち税理士法人プロゲートへご相談ください。法人及び個人事業主様の会計業務をサポートしておりますので、税務・会計に関するお悩みを解決致します! 関連記事:経費はレシートでもいい?手書き領収書との違いや活用するメリットなど詳しく解説! 関連記事:事業主貸の上限は?事業主貸の概要、仕訳の方法やポイントを解説 関連記事:領収書の宛名が間違っていた!そんな場合に経費計上できるの? 関連記事:宮城県仙台市で税理士に確定申告を依頼するなら誰にどのように相談すればいい? 関連記事:確定申告が必要なのはどんな人?申告義務やペナルティ・対処方について解説 関連記事:事業主貸が多いとどんな影響がある?問題点や注意するべきポイントを解説

フリーランスの開業届の書き方と出すメリットとは?
これまで会社員など組織で働いていた人が独立して、フリーランスとして活動する場合に気になるのが「開業届を出すべきかどうか」です。開業届の提出にはどんな意味があり、どんなメリットがあるのでしょうか。また、開業届を作成する際にはどんな注意点があるのでしょうか。 今回の記事では、そんなフリーランスの開業届の書き方について解説し、提出方法や開業届と一緒に提出すべき書類や注意点についても紹介していきます。ぜひ、参考にしてください。 フリーランスは開業届を提出するべき? 結論からいうと、開業届の提出は必須ではないです。しかし、メリットが多いのも事実なので開業届を提出する場合とそうでない場合の違いなど知っておくと良いでしょう。 では、フリーランスが開業届けを提出する理由と、そのメリットについて解説していきます。 開業届とは? 働き方が多様化した現在、独立や副業で何か新しい仕事を始めることは珍しいことではありません。職業の幅も広がり、オンラインで仕事をしている方も多いでしょう。 例えば、趣味を活かしてそば屋を開業したり、子育てが一段落してからネイルサロンを自宅で営んだり、海外での経験を生かして翻訳業務を始めたりする人がいます。このように自分でビジネスを始める際や、ビジネスを辞める際に税務署に提出する書類が「開業届」です。この書類は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。 開業届を提出することにより、個人事業主として税務署に登録され、確定申告の時期になると申告書類が郵送されます。開業届は、事業開始から1か月以内に提出することが所得税法で定められていますが、出さなくても罰則はありません。開業届を提出しなくても、その年の事業収支をまとめて確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。 しかし、対外的に「独立開業しました」と宣言するためには正式な手続きを踏むことが重要ですので、ビジネスを始めるタイミングで開業届を提出すると良いでしょう。フリーランスや副業で継続的に収入を得ている場合も、事業として認められる場合は開業届を提出することで、様々なメリットを享受できます。 フリーランスが開業届を提出することで得られるメリット フリーランスが開業届けを提出するメリットは「青色申告」を行えることにあります。開業の際には「白色申告」「青色申告」という2種類の選択肢がありますが、青色申告を選択することによる最大65万円の税控除を得られるメリットがあります。 青色申告をすることで受けられる最大65万円の控除は、複式簿記に基づく記帳やe-Taxを通じた申告など特定の要件を満たす必要があります。また青色申告は家族への給与支払いを経費として計上できたり、損失を3年間繰り越したりすることが可能です。また、30万円未満の備品を一括で経費計上することもできるなど、様々なメリットがあります。 青色申告を行うためには、原則として「所得税の青色申告承認申請書」を事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。開業初年度から青色申告を希望する場合は、開業届とともにこの申請書を提出しましょう。 他にも、開業届けに屋号を記載して提出することで、事業用の銀行口座を屋号名で開設することができます。これにより、個人の資金と事業の資金を区別しやすくなり、経理処理や資金管理が容易になります。また、屋号があることで事業の正式性が高まり、取引先からの信頼を得やすくなります。 また、個人事業主として事業を営んでいることの公式な証明書となります。これは、オフィスや店舗の賃貸契約、融資の申込み、保育園の入園申込みなど、様々な場面で必要とされます。 小規模企業共済への加入は、退職金制度の一種で、個人事業主や小規模企業の経営者が対象です。退職後の生活のための積立として機能し、掛金は全額所得控除の対象となります。事業開始後すぐに確定申告を行っていない場合は、開業届の控えが加入の際に必要となります。 総じて、開業届を提出することは、手間と感じるかもしれませんが、その後の事業運営や税務処理において多くの利点があります。 フリーランスの開業届の書き方 続いて、開業届の書き方を紹介していきましょう。 税務署かインターネットで開業届を入手する まずは開業届を入手しましょう。開業届は最寄りの税務署で入手するか、検索して国税庁webサイトからダウンロードして、印刷する二通りの方法で入手可能です。 開業届を入手したら、ボールペンなどで必要事項を記載していきます。 所得税の青色申告承認申請手続き 提出先と納税地 提出する税務署の名前と提出する日付を記載します。 所属する税務署は、国税庁のwebサイトで確認できます。 住所(現住所)、居所地(一時的住所)、事業所の中から納税地を選び、住所と電話番号を記入します。納税地をどこにするかは任意ですが、基本的には事務所がある場所の住所を納税地としましょう。 創業者の個人情報 氏名、任意、マイナンバー: 氏名、任意と12桁のマイナンバーを記載します。使用する印鑑は個人名でも屋号でもどちらでも可能です。屋号の印鑑を用意していない場合には、個人の印鑑で対応しましょう。 屋号と事業の概要 屋号がある場合は屋号名を記入します。屋号を記載すると、その屋号の名義で銀行口座を開設できるようになります。個人のお金と事業用のお金を分けて管理するのは事業の透明性の確保や、確定申告や決算時に便利ですので、屋号を登録しておくことをおすすめします。 また事業の概要の項目では、主として取り組む事業内容を具体的に書きます。事業内容がわからない場合には産業分類から近いものを見つけ、事業内容を記載しておくのが良いでしょう。 従業員と給与について 従業員情報欄は、従業員が存在しない場合は記入不要です。ただし、家族など青色事業専従者を雇っている場合は「専従者」欄に人数を、その他の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入してください。 給与の源泉徴収義務に関する項目では、従業員に給与を支払う場合、源泉徴収して所得税を納税する必要があるため、「有」を選択します。この項目は、従業員に給与を支払う際に源泉徴収を行う必要があるかどうかを確認するためのものです。 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内とされています。開業日は任意ですので、自分の希望とする日を開業日にして記載すれば問題ありません。多くの場合「大安」や「一粒万倍」など日柄が良い日が選ばれたり、自分や家族の誕生日などの記念日を選択します。 フリーランスの開業届の提出方法 開業届が完成したらいよいよ提出です。続いて開業届の提出方法について紹介していきます。 フリーランスの開業届は税務署に提出 作成した開業届は、作成時に記載した管轄の税務署に提出します。開業届の提出方法は税務署の開庁時間に窓口で提出するか、税務署に設置されている時間外収受箱への投函、郵送での提出、e-Taxでの提出などの方法があるので、任意の方法で提出します。 提出時に準備するもの 開業届を提出する前に、すべての必要書類が揃っているかをチェックしましょう。提出方法によって準備する書類が異なるため、以下の項目を確認しておきましょう。 1、直接提出する場合に必要な書類 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と開業届のコピー マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認書類 直接税務署へ提出する際は、マイナンバーカードを忘れずにご持参ください。また、開業届の控えは自分で用意する必要があるので、事前にコピーを準備しておくと良いでしょう。開業届の提出が完了するとコピーに受付印が押されます。この受付印があることで開業届の控えが公的な書類として認められるため、注意しておきましょう。 2、郵送または時間外収納箱を利用する場合に必要な書類 開業届と開業届のコピー マイナンバーカードのコピー 返信用封筒(自分の住所記載、必要切手貼付) 郵送や時間外収納箱で提出する場合、マイナンバー確認書類のコピーと返信用封筒が必要になります。 郵便用封筒には自宅や事務所などの住所を記載し、正しい切手を貼ってください。 税務署への書類送付は、書留郵便やレターパックなど追跡可能な方法で行うことをお勧めします。 開業届以外にも提出するべき書類がある 開業届を作成して提出するのであれば、一緒に提出しておくと良い書類がいくつかあります。何度も税務署に足を運ぶのは手間なので、事業形態にあわせた書類を作成し、一緒に提出しましょう。書類の種類については次章で解説していきます。 開業届と一緒に提出するべき書類 開業届の作成と提出に併せて提出すると良い書類がいくつかあります。一緒に提出すべき書類がある場合には、そちらも作成して提出しましょう。 青色申告承認申請書 青色申告承認申請書は正式には「所得税の青色申告承認申請書」といいます。フリーランスが開業届を提出する最も大きなメリットが冒頭に紹介した青色申告での確定申告です。 確定申告を青色申告の方式で行う際には、その年の3月15日までに、開業届と合わせて所属する税務署へ提出する必要があります。この申請書を提出しないと、自動的に白色申告として扱われるので、忘れずに提出しましょう。 青色事業専従者給与に関する届出書 事業主が家族に給与を支出することは一般的に認められていませんが、青色申告で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するとことで家族への給与を経費として計上することが可能になる「青色事業専従者給与の特例」が利用できます。 青色事業専従者給与を適用する条件には、 給与徴収家族が事業主と居住している配偶者や親族であること その年の12月31日時点で15歳以上であること 専従者事業として6か月以上従事していること 支払われる給与がその従業員に対する適切な金額であること が含まれます。これらの条件を全て満たした上で、「青色事業専従者給与に関する届出」 を税務署に提出することで家族への給与を経費計上できます。 ただし給与の金額設定に際しては、労務の対価としての考慮性を考慮し、他の従業員との比較や業務内容の価値を適正に評価することが求められますので、極端に高い給与を家族に支払うことはできません。 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 フリーランスが従業員を雇用している場合、雇用主として従業員の源泉徴収し、翌月10日までに支払う義務があります。毎月、手続きを行うことは大変なので、「源泉所得税の納期の特例」によって年間の納税回数を12回から2回に軽減されます。この特例の申請資格は、従業員数が10人未満の小規模事業者に限定されています。 この特例を利用すると、源泉徴収税の納税は年2回、前期(1月から6月)の税金を7月10日まで、後期(7月から12月)の税金を翌年の1月20日までに納税することで源泉徴収の手間を省くことができます。従業員を雇用している場合には「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」も忘れずに提出しましょう。 個人事業開始申告書 個人事業開始申告書は、自分が事業を立ち上げたことを都道府県や市町村へ報告する際に必要とされる文書です。これを提出することで、地方税に関わる手続きを進めることができます。開業届は事業開始を国税局へ報告するためのもので、主に所得税の申告に使われます。 これに対して「個人事業開始申告書」は地方税である個人事業税に関する報告用です。個人事業開始申告書は税務署ではなく都道府県事務所と市町村役場の税務関連部署で入手し、その場で提出します。この時に開業届の控えを見せる必要があるので、開業届を提出してから個人事業開始申告書を提出しましょう。 結論:開業届は提出しよう 今回は、フリーランスの開業届の書き方や提出方法についてご紹介してきました。 フリーランスとして開業するのであれば、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することで様々なメリットがありますので、一緒に提出しておきましょう。また、他にも開業届と同時に提出すると良い書類がありますので、ご自身のビジネスで必要な書類があれば作成しましょう。 開業届を提出するデメリットを挙げるとすれば「手間がかかる」ことくらいですので、提出すべき書類がよく分からないという方はいつでもご連絡ください。 税理士法人プロゲートでは、フリーランスや個人事業主の方々のサポートを提供しており、開業届の提出だけでなく税務全般の支援を通して事業主様が本業に専念できるようサポートしています。もし起業に関するお悩みや不安があれば、お気軽にご相談ください。