お役立ち情報
お役立ち情報を掲載しております
税理士法人プロゲートです。会計、税金、相続、経営計画、給与計算、社会保険等なんでもご相談ください。
お役立ち情報を掲載しております
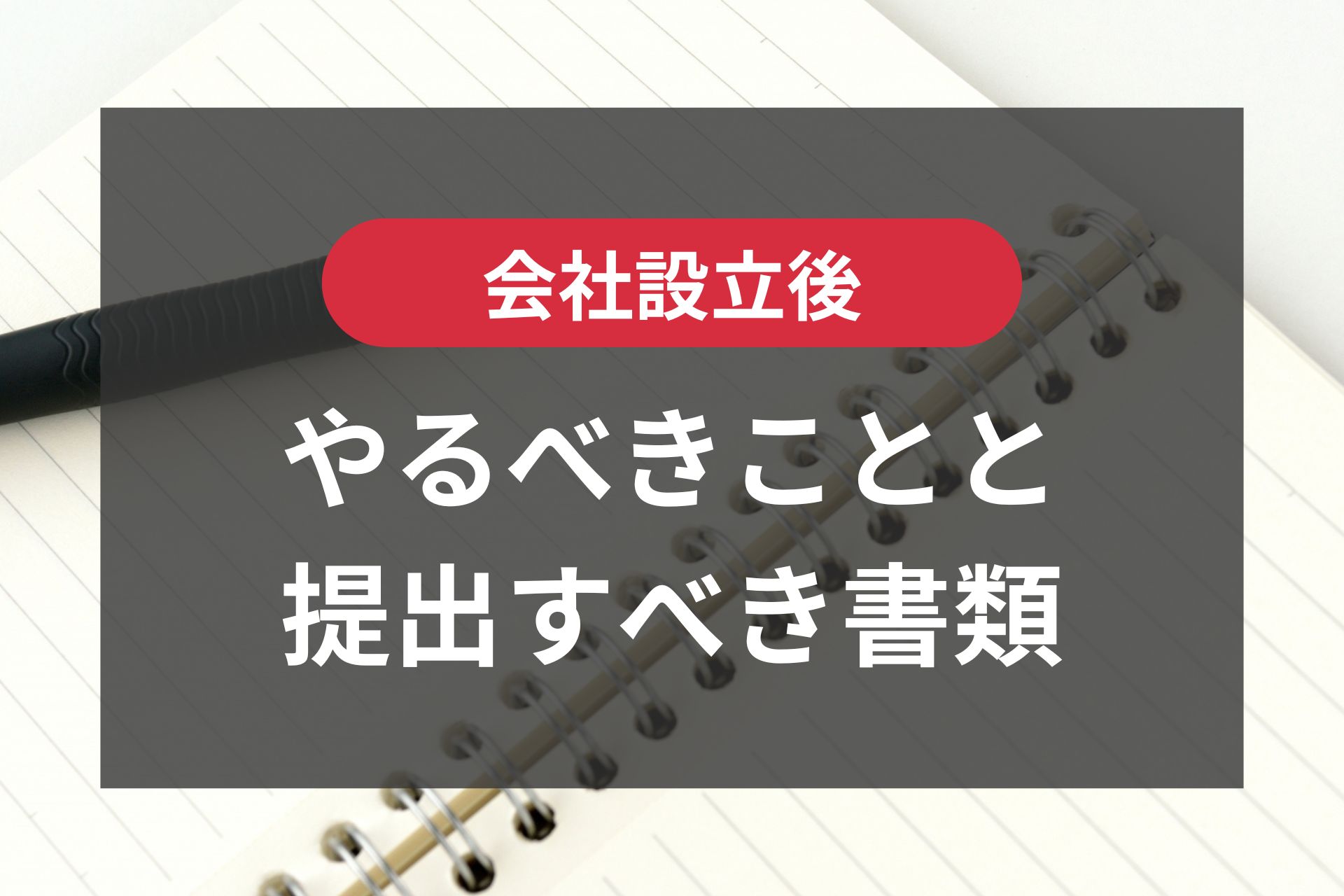
会社設立後にやるべきことと提出すべき書類
今回は会社を設立した後にやるべきことと提出する書類についてお伝えしていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=QmCW7SlEYcE 会社設立後にやるべきこと 会社設立後にやるべきことは大きく分けて2つあります。まずは銀行口座の開設、そしてもう1つは税務署や年金事務所など公の機関への届出です。 あとは会社によっては何か許可が必要な場合は、行政の許認可を担当している部署に申請を行うなどの手続きが必要となります。 銀行口座の開設 銀行も最近では口座を作るのが厳しくなっており、事業の実態などをきちんと確認して口座を作成するという流れになっています。登記事項証明書や定款などの書類はもちろん持っていきますが、その他に事業内容が分かる書類などを用意しなければならないケースもあります。 届出書類について 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場 会社設立後に税務署や各都道府県税事務所、市区町村役場に提出する書類について以下にまとめています。 税務署法人設立届出書青色申告の承認申請書給与支払事務所等の開設届出書源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書各都道府県税事務所市区町村役場法人設立届出書定款のコピー登記事項証明書 まずは税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に「会社を設立しました」という届出である法人設立届出書を提出します。電子申告をすることもできますが、そうでない場合はご自身が設立した会社の管轄の税務署や県税事務所、市区町村役場などに直接届出を行います。 また、青色申告を行う場合には青色申告の承認申請書を提出する必要があります。こちらは設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日の前日までに提出しなければなりません。例えば1月や2月に設立をして3月が決算という場合には、3月までに届出をしないといけません。会社を設立した際に多くの経費がかかった場合、青色申告でなければ赤字を2期目に繰り越すことができないため、提出遅れになってしまうと損失を繰り越せずに損をしてしまうケースもあるので注意しましょう。 給与の支払いがある場合には、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出します。こちらは従業員だけではなく、役員にも給与を支払うのであれば提出する必要があります。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書とは、給与を会社から払う際に天引きした税金の納付ですが、通常毎月行うものを半年まとめてにできるというものです。こちらは給与を支払う人数が10人未満の場合に使うことができます。設立当初は何かとバタバタしており、なかなか毎月納付することがままならない場合にはこちらを提出しておいて、半年に1回の納付にするというのが一般的かと思います。 年金事務所 年金事務所に提出する書類は以下となります。 年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届健康保険被扶養者(異動)届 健康保険・厚生年金保険新規適用届は、会社設立から5日以内に提出となっています。また役員や従業員など人単位での届出は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届となります。扶養の方がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届も合わせて届出をしましょう。 ハローワーク・労働基準監督署 従業員を雇用する場合には、ハローワークと労働基準監督署に以下の書類を提出します。 ハローワーク雇用保険適用事業所設置届雇用保険被保険者資格届労働基準監督署労働保険の保険関係成立届労働保険の概算保険料申告書就業規則(変更)届適用事業報告書 従業員を雇用する場合には、雇用保険と労働保険に入る必要があり、その届出もしなければなりません。ただ、1人社長の場合は必要ありません。 まずはハローワークで雇用保険の手続きを行います。労働保険に関しては、労働基準監督署が管轄となります。 これらの他に会社の状況によって、提出すべきものが異なりますのでしっかり確認をするようにしましょう。 手続きに関してご相談ください! 今までお伝えしてきた手続きを一人で行うことは手間はかかりますが、できないことはないと思います。ただ、どうしても会社設立後、特に忙しく、これら手続きを全て一人で行うのが難しい場合もあるかもしれません。そのため、専門家に依頼できるのであればその方が間違いはないかと思います。 もちろん会社設立後の手続きだけを依頼することも可能です。ただ期限があるものがあるため、出来るだけ設立前から手続きの代行などできる税理士や社労士を見つけることをおすすめします。 弊社でも会社設立のサポートをさせていただいておりますので、「時間がなかなか取れない」「手間だ」ということであれば、是非一度ご相談ください。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて

株式会社と合同会社って何が違う?メリット・デメリットを比較
仙台市にはさまざまな創業支援があり、それらを利用し、会社設立を考えている人も多いと思います。会社設立を考えているなら必ず迷うと思うのは、どの会社形態(種類)で設立するかということです。 いくつか会社形態はありますが、この記事では株式会社と合同会社について比較、紹介していきます。それぞれの異なる特徴、メリット・デメリットがありますので、注意点をよく理解した選び方をしないと、後になって後悔するかもしれません。 迷っている方はこの記事を参考にしてみてください。 https://www.youtube.com/watch?v=G8pFz_jM6Mg 株式会社と合同会社って何が違うの? 株式会社と合同会社の根本的な違いは「所有と経営が分離しているかどうか」という点です。ここでは、それぞれの違いの詳しい説明をしていきます。 株式会社とは? 株式会社とは、会社が株式を発行し、その株の売買によって集めた出資金を基に事業を運営していく会社形態のことです。また、株式会社の最も大きな特徴として「会社の所有と経営の分離」していることにあります。 会社を設立・運営していくには資金調達が欠かせません。株式会社は設立の際に、株式を発行しています。お金と引き換えに出資金額に応じた株式を出資者に渡すことによって、出資者は会社の「株主」となり、会社が事業運営で得た利益分配を受けるなどの権利を得られるのです。 出資者(株主)は同時に、会社の経営に携わる権利もあります。これは株式会社の経営者(創立者)が所有者なのではなく、より多くの株を保有している「株主」が会社の所有者だからです。ただし、取締役などの実際の経営者は株主総会によって選ばれ、その委任を受けないと実際の経営に携わることができません。 また、株主は会社の所有者ですが、会社の債務に関しては自身の持つ株式の引受額以上の責任は負いません。これを有限責任といいます。これにより、いくぶん安心して会社への出資が行えるようになってるのです。 先ほど株式会社の特徴として「会社の所有と経営が分離している」とは言いましたが、中小・中規模の株式会社の場合、総じては経営者と所有者が一致しています。株式は必ずしも第三者に募集をかける必要はなく、設立者が発行株式を全て引き受けてもよいのです。会社の規模が大きくないなら全株式を所有した設立者が、形式上株主総会を開き、自身を経営者として選任しても問題はありません。 合同会社とは? 一方、合同会社とは、経営者と出資者が名実共に一致している形態の会社です。出資者の全てが業務執行権を持っています。合同会社は有限会社に代わる会社形態として、2006年の会社法改正時に誕生しました。一番新しい会社組織で「持分会社」とも呼ばれてます。 もし、設立者が100%出資するのであれば、総会を開くことなくそのまま経営者になれますが、複数の出資者がいた場合は、その全員が経営者になります。この場合、出資金額に関係なく同一の一票を保有しているため、会社の方針や意思決定は原則として社員全員の同意でおこないます。 なお、合同会社の出資者の事を「株主」ではなく「社員」と呼びます。 また、株式会社と同様に、出資者は出資額以上の責任を問われない有限責任です。 関連記事:合同会社から株式会社に組織変更するには?費用や手順を紹介! それぞれのメリット・デメリット 税理士法人プロゲート仙台オフィスにご相談してこられる方の中には、「株式会社と合同会社ってどっちを選べばいいの?」というご質問も多くいただきます。中には「取り合えず株式会社でいいよね」と内容をわからずに決めていらっしゃる方も・・・ 会社形態は、どんな規模の事業を考えているのかや、将来的な展望によって選択することが必要です。そのためにも、ここでは双方のメリット・デメリットを解説していきます。 株式会社のメリット 〇社会的な認知度、信用度が高い 株式会社は合同会社よりも社会的な認知度が高く、また、合同会社などの持分会社と比べると守らなければならない法律や規制が多く、その分会社としての信用度も高いです。 人材採用の求人の募集や各金融機関からの融資など、多角的な面で合同会社や個人事業主より有利に進めることができます。 〇株式発行による新たな資金調達がしやすく、大規模な事業展開も可能 株式を発行することで、配当金などを目的とする投資家を含め、幅広い方面に出資を募ることができます。また、出資者は間接有限責任となるため、出資金額を超えて損失を負うことはありません。そういった意味でも投資しやすいメリットがあります。 〇万が一の際にも有限責任にできる 有限責任とは、会社の債権者に対し、出資額を限度として責任を負うことを指します。例として、会社が倒産したときに出資したお金は失ってしまいますが、それ以上の損失の支払義務は発生しないということです。これは、株式会社の株主は債権者に直接責任を負うのではなく、出資した会社に出資した額だけの責任を負う、間接有限責任となります。 〇経営が混乱しにくい 株式会社は、合同会社よりも経営が混乱しにくいという特徴があります。 これは、経営に口出しできる権利が保有している株式の数に応じて付与される仕組みになっているからです。 例えば株式保有者が6人いて、6人とも意見がバラバラだった場合、その中のひとりが70%の株式を持っていれば「過半数の賛成」がとれるため、良くも悪くも何らかの結論は出ます。 株式会社の場合は、株の保有比率に応じて経営上の意思決定を行うことにより、「全員の意見が一致しない」「意見がまとまらず経営が混乱する」「派閥同士の争いになり結論が出ない」などの理由から事業が進まなくなるような事態を防ぐことができます。 〇権利譲渡・相続・事業継承の手続きがしやすい 株式会社の場合は、株式の権利譲渡、相続、事業承継などの手続きがしやすいというメリットもあります。 会社の経営に参加できる権利は、どれだけの株式を保有しているのかに応じて決まりますが、上場企業の場合は市場で自由に株取引が可能なため、その権利を誰に譲渡しようと自由です。 また、家族経営を行っている会社の社長が突然死した場合も、後継者となる相続人(配偶者や子供・兄弟など)が社長の保有していた株式を相続することによって、会社の経営に参加する権利も同時に受け取れることになるため、スムーズに事業承継が行われます。 株式会社は、経営に参加できる権利である「株式」の権利譲渡が比較的簡単に行えるため、相続や事業承継なども行いやすい点も特徴といえるでしょう。 株式会社デメリット 〇会社設立・ランニングコストは共に合同会社より高くかかる 株式会社と合同会社では会社設立にかかる費用や手続きがそれぞれ異なります。 例えば、法務局で登記申請する際に納める登録免許税は株式会社・合同会社共に「資本金額×0.7%」ですが、合同会社が算出される金額が6万円に満たない場合は6万円です。一方で株式会社は算出される金額が15万円に満たないときは15万円かかります。また、株式会社は定款を作成した後、公証役場で認証を受けなければいけません。この認証手数料が資本金額に応じて1.5万円〜5万円程かかります。一方で、合同会社は定款の認証を受けなくてもいいため、公証役場での手続きや手数料は発生しません。 〇決算公告が必要 決算公告とは、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に明らかにし、取引の安全性や公正を保つために行われます。合同会社には決算公告の義務がありませんが、株式会社には毎年必ず決算公告を行う義務があります。一般的に、株式会社の決算公告は官報に掲載しますが、7万円程度の費用がかかり、電子公告の場合であっても1万円程度の費用が必要です。 〇株式上場には、もの言う株主や敵対的買収などのリスクがある 株式上場することによって大きな出資が見込まれる一方で、経営に積極的に提案を行う「もの言う株主」もいます。アクティビストが企業に成長戦略を提案し、企業が応じられれば企業価値向上に繋がります。しかし、経営者が気に入らなければ「売却」という強硬手段をとる場合もあるため、注意が必要です。 また、買収対象会社の取締役会の同意を得ない、強引な買収を仕掛けてくる「敵対的買収」のリスクも高まります。基本的には対象会社の経営権を得られるように、総株主の議決権の過半数の取得を目指すことが一般的です。 〇役員任期がある・変更登記などの手間がかかる 株式会社の役員の任期は最長10年と決まっており、同じ人が役員に再任される場合でも、再び登記の手続きが必要で、その度に登録免許税がかかります。登記変更の手続きや費用がかかりますが、この制度を利用して定期的に役員の見直しができるため、メリット・デメリットの両法の側面があるといえるでしょう。 合同会社のメリット 〇設立コストが株式会社より安い 合同会社の大きなメリットのひとつとして、株式会社よりも設立費用を安く抑えることができる点は魅力的です。会社設立の際に最低限かかるコストは、株式会社の場合は約17〜24万円掛かるのに比べ、合同会社の場合なら約6〜10万円程と低いです。これは株式会社で必要な定款認証が不要など、コストだけでなく設立手続きの面でも負担が少ないです。 少しでも支出を抑えたいと考えているなら、創業時の負担が軽減されることは大きなメリットですね。 また定款認証が不要なため、株式会社に比べて設立にかかる時間が短いという観点からも、合同会社のメリットと言えます。 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 〇ランニングコストが抑えられる 株式会社とは異なり、合同会社には決算申告義務がありません。そのため毎年の官報掲載費が発生しないため費用が抑えられます。また、役員の任期を設ける必要もないことから、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる登録免許税も掛かりません。 〇経営の意思決定がしやすく自由度が高い 株式会社の場合、会社の運営方針や重要事項を決定する際には、必ず株主総会を開催し採決をとる必要があります。一方で合同会社の場合は、出資者(社員)それぞれが経営者なので、迅速な意思決定が可能です。そのため、経営の采配や自由度が高くなります。また、合同会社の場合、第三者からの出資を想定していないため、会社経営や方針に社員以外の第三者の意思が介入しづらいというメリットもあります。 〇利益配分を自由に決めることができる 合同会社は出資比率に関係なく利益配分ができることも、経営の自由度の高いメリットの一つです。 会社の利益は、配当という形で出資者(株主)に分配されます。株式会社では、出資比率に応じて出資者への利益配分が決まっているので、出資金が多い人がより多くの利益を受け取る仕組みになっています。対して合同会社では、出資比率にかかわらず、定款に利益配分を自由に定めることができます。例えば、優秀な成績の社員には、その利益配分比率を高く設定するということも可能です。 また、定款内容は株式会社よりも自由度が高いため、会社の事情や性質・特色に応じた定款を作成できます。社員それぞれの技術力や業績などの個人のスキルを基に、出資額だけではない要素で利益配分を決められるのは、合同会社の特徴といえるでしょう。 合同会社のデメリット 〇社会的な認知度・信用度の低さ 比較的新しい形態のため、株式会社に比べると合同会社の認知度は低くなります。ご相談者様にも「会社といえば株式会社」と考えられている人が多く、実際数も多いことから、「株式会社」と銘打っている方が社会的な信用度についても高くなるでしょう。求人についても、まだまだ株式会社より集まりにくい傾向にあります。 〇新たな資金調達がしづらい 株式会社の場合は新たに株式を発行し、新規の出資者を募ることができますが、合同会社ではその方法がとれないため、資金調達に苦労するかもしれません。合同会社が「外部から資金調達をしたい」と思ったときにとれる方法は、社債や融資などが中心となります。しかし社債は株式と異なり負債という扱いになり、一定期間後に元本をまとめて返済しなければなりません。返済の際には多額の現金がなくなるため、十分に耐えられるように資金繰りを綿密に行っていく必要があるでしょう。 また、金融機関からの融資も、信用がなければ受けられません。会社の利益や実績を着実に積み上げ、それを基に金融機関からの信用・信頼を得られることが必要です。 〇社員同士が対立する可能性がある 合同会社は誰がどれだけの出資をしたか(出資比率)に関係なく、原則として全社員(出資者)ごとに平等に経営権と一人一票の議決権を持っています。「社員の考えや思いを重視する組織体」ため、意思決定を行う際、出資者の社員同士で意見の対立が起こってしまうと、経営や業務に大きな影響を及ぼす恐れがあります。代表社員の継承、事業継承、出資者の権利譲渡については社員全員の同意が必要です。経営に関する事項では社員の過半数、業務執行社員を選出している場合には業務執行社員の過半数の同意が必要になります。そのため、意思決定の採決がとりやすいよう社員の人数を奇数にしたり、何らかの対策が必要です。また、利益配分が自由であるからこそ社員同士が対立する可能性も考えられます。利益配分についての社員同士の対立を防ぐためにも、定款に「出資額に準じた利益配分とする」などの記載をしておくことがトラブル回避に役立つでしょう。 〇上場できない 株式会社の場合、上場して更なる事業拡大や店舗増設を目指すことができますが、合同会社の場合は株の発行ができないため、そもそも上場できません。将来より大きな事業展開や上場を目指しているのであれば、株式会社を選んでおくことをおすすめします。 〇権利譲渡・相続・事業継続の手続きがやりにくい 合同会社の場合、会社経営に関与する権利は「持分」と呼ばれており「各自の意思で勝手に誰かに譲る」ということが認められていません。 原則として合同会社で持分を他者に譲渡する場合は、必ず他の社員全員の同意が必要と定められているためです。 例えば、合同会社の代表者が「自分の子供に代表の座を継がせたい」と思っていても、他の社員の同意を得られなければそれを実行することはできません。 また、合同会社では社員が死亡=「退職扱い」となり、亡くなられた社員の持分が自動的に相続者に渡るということはありません。もし持分を相続者が欲しいなら、会社にそのことを伝え、請求を認められる必要があります。あらかじめ定款に「出資者が死亡した場合」についての条項をケース別に追記しておくことで、事業の継承問題を回避できます。 株式会社と合同会社、向いているのは? ここまでメリット・デメリットを解説してきましたが、それぞれの強みを理解できたのではないでしょうか。それを踏まえて、どちらがご自身の会社に向いていますか? ここからはそれぞれに向いている人の特徴についてお伝えします。 株式会社に向いている人 株式会社に向いている人は以下の通りです。 将来的に事業展開を見据えているため、多角的に資金調達できるようにしたい 研究・開発・広告宣伝費などに多額の費用をかけたいと考えている場合には、金融機関だけでなく投資会社やベンチャーキャピタルなど、幅広く資金調達が見込める株式会社を選びましょう。 株式上場をし、信用度を得て取引先の開拓や優秀な人材の採用などをしたい 株式上場には、会社としての信用・信頼度の高まりや、事業拡大に向けて進みやすさ、創業者利益を享受できるなどのメリットがあります。将来的に株式上場を考えている人や、事業内容がB to B(法人向けの)ビジネスの場合は株式会社が適しているでしょう。 「代表取締役」という肩書が欲しい 「代表取締役」という肩書は株式会社の場合のみ使用できます。合同会社では「代表社員」という肩書になってしまうので、肩書にこだわるのなら株式会社を選ぶのが良いでしょう。 合同会社に向いている人 合同会社に向いている人は以下の通りです。 できるだけコストを抑えたい 先でも述べたように、株式会社に比べると合同会社は予算的にも時間的にもコストを抑えて会社設立が可能です。そのため起業したくても十分な資金が準備できていない人や、将来的に事業拡大は考えていない人、小規模、一人社長で節税のために会社を作りたい方には合理的で向いています。 経営や自社業務を対等な関係で行いたい 「役員同士を対等な関係にしたい」という場合には、社員全員が平等であることが原則の合同会社が向いています。例えば、「町おこしのために地域住民で温泉経営の会社を立ち上げたい」「リサイクル業界の企業同士、対等な関係のまま環境配慮にした環境整備を目的に活動する会社を設立したい」というようなケースが該当します。 事業内容がB to C(個人向けの)ビジネスの場合 飲食店や美容院、介護老人福祉施設などメイン顧客が故人に向けての場合や、スキルやノウハウでなど無形の資産によって契約を獲得できるような場合も、合同会社をおすすめします。これは顧客が「株式会社ではないから信用できない」という考えを持ちにくいためです。 会社設立なら弊社へお任せください 会社を設立するなら株式会社・合同会社どちらを選んでも後悔のない選択をしたいですが、自分だけでは判断ができないこともあるでしょう。 そんな時は税理士法人プロゲート仙台オフィスへご相談ください。創立支援が充実している弊社では、創業50年以上の実績と経験を基に、お客様にとって最適なサポートを行っています。 税理士法人プロゲート仙台オフィスは創業支援が充実 会社を設立するためには、各種手続きを行う必要があります。 もちろん、ご自身で行うことも可能ですが、書類の作成や提出、役所へ行く時間などを考えると、とても煩雑化します。 そのような作業は全て専門家にお任せください。 弊社は、これまでに200社以上の会社設立サポートをさせていただきました。その中で得られた経験やノウハウを、惜しみなく全て提供させていただきます。 会社設立に必要なことや、設立後に必要になることまで万全のバックアップ体制で安心したスタートできるようサポートさせていただきます。 仙台創業融資支援センター プロに依頼するメリット 創業50年以上の経験と実績 弊社グループでは50年以上にわたって、経営者様のサポートを行ってきました。積み重ねてきた経験や知識、ノウハウを、コミュニケーションを通してお客様に提供させていただきます。 また、若手からベテランまで一人一人のスタッフが、きめ細かに支援しますので、安心してお任せください。 創業支援から経営アドバイスまで幅広くサポート 弊社グループには税理士を始め、社会労務士、行政書士と多くの専門家が在籍しております。そのため、創業支援はもちろん、税務・会計、資金調達や給与計算、人事労務管理など、幅広いサービスをワンストップでの対応が可能です。 また、経験豊富なスタッフが多く在籍していますので、「こんなこと聞いてもいいのかな?」という状況でも悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 関連記事:仙台市で創業融資を考えている方は「仙台創業融資支援センター」を活用しよう! 若手起業家と同じ目線で未来を見越した並走支援 初めての起業はわからないことが多いです。若い起業家の人も「いくら起業したいといっても何をどうすればいいの?」と疑問に思うことや専門知識の不足を、プロに依頼することで解決できます。また、難しい専門用語は使用せず、お客様と同じ目線に立ち、分かりやすい言葉で説明することを心掛けております。 「親切・丁寧」を大切に、未来を見据えた創業支援・経営支援をさせていただきます! 自分の専門外のことは、他の人の力を適切に借りることが重要です。失敗せずに会社の設立を完了し、理想の事業をスムーズに進められる環境を整えていきましょう。 仙台市の会社設立|お気軽にご相談下さい 会社を設立する上で、ご自身の事業内容や将来的な展望を見据えて、株式会社と合同会社のどちらの会社形態を選択するのかを考えましょう。 株式会社と合同会社では、所有と経営の関係に大きな違いがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、会社の規模や事業内容、将来的な展望などによっても重視するポイントは変わってくるはずです。会社を設立しようとするときには、一般的には、株式会社と合同会社のどちらにするかを選ぶことが多いですが、両方の特徴を把握したうえで、事業内容や目的に合った形態を選択するようにしましょう。 弊社へご相談にいらした方も、メリットやデメリットを知らずに「会社なら株式会社じゃないの?」という方も少なくありません。 それぞれの違いを知ることで、設立時のリスクを減らすことができます。 一人、または少人数での会社立ち上げを考えているのなら合同会社のメリットを十分活用できるでしょう。 「会社を立ち上げたい、でも設立のためのお金はあまりかけられない」と尻込みしているのなら、まずは合同会社を立ち上げてから株式会社に移行することも可能です。合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、手続きと費用が必要となりますので、その点についても事前に把握した上で検討する必要があります。 そうはいっても、自分で判断するのはなかなか難しいので、その場合は、専門家である税理士にご相談ください。 プロによるアドバイスを受けることによって、ご自身に合った無理のない会社形態を選択することができます。弊社には経験豊富なスタッフが多く在籍しており、創業支援から営業支援・アドバイスまで、徹底した幅広いバックアップ体制を整えております。 不安や疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料にてお答え致します。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:会社設立の際の費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説

個人事業主が法人化するベストなタイミングとは?
現在、仙台市で個人事業主として事業されている人の中には「法人化(法人成り)」を考えている人もいるのではないでしょうか。 事業が波に乗り、利益が増えることによって、この先、より大きな事業展開への挑戦や、それに伴う資金調達の観点からも、法人化することに魅力を感じる人もいることでしょう。 しかし、個人事業主から法人化するならタイミングが重要です。もちろん法人化によって得られる社会的信用や節税の効果はメリットと言えますが、ただ法人化するだけでは支払う税金が増えてしまうこともあるのです。 また、個人では知識が不足していると理由から、どんな流れで法人化すればよいのかわからない方もいるでしょう。そんな時は、税理士法人プロゲート仙台オフィスへご相談ください。法人化するために必要なプロセスも、専門家である私たち税理士にご相談いただければ、最適なタイミングで不利益なく実行することが可能です。 関連記事:仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて この記事では、個人事業主から法人化することのメリット・デメリットや、最適なタイミング、法人化するまでの流れについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=ZaA5QS16YXo 法人化とは?分かりやすく解説 法人化は、個人事業主が合同会社や株式会社などの法人を設立し、これまで個人で行っていた事業をそのまま継続することです。個人事業主から法人化(法人成)することで得られるメリットは多く、節税や大手企業からの信頼性の向上などが挙げられ、資金調達の面でもより多くの支援金・資金を集めることができるようになります。 ただし、個人事業主から法人化すると、税負担の種類が変わるため、法人税や登記、登録免許税などもかかるので、必要な手続きを行うことが必要です。 また、法人化する際に余計な支出をさけるために、適切なタイミングを見極める必要があります。 個人事業主から法人化するメリット 個人事業主から法人化することで得られるメリットにはいくつかありますが、ここでは4つのメリットについて解説していきます。 メリット①社会的な信用度が高まる 法人化するためには、まずは法人を設立することが必要です。法人を設立するためには商号(社名)・住所・資本金などを法務局に提出し、登記登録を行う必要があります。登記した内容は、誰でもアクセスし見ることが可能なので、法人としての責任が発生することを理解しておきましょう。そして、社会的な責任を負うことで、会社自体の信用度も向上するため、個人事業主だったときは契約できなかった企業とも、取引の可能性が広がります。事業の拡大を考えている場合には、法人化は大きなメリットと言えるでしょう。 メリット②節税対策がしやすい 個人事業主と法人は、それぞれ課税される税金の仕組みが異なっており、個人事業主は所得税、法人は法人税がかかります。 個人事業主の所得税は累進課税で、所得が増えると税率が段階的に上がる仕組みです。また、最大の税率は45%になります。 一方で法人の法人税は、資本金1億円以下で所得が800万円を超える場合は23.2%、所得が800万円以下なら15%となるため、所得が多いほど法人化したことによる節税効果が高くなることがメリットです。 ほかにも法人化による節税対策として、下記のようなメリットがあります。 <役員報酬を損金計上することが可能> 個人事業主の場合は、事業所得(売上から経費や控除などを引いた金額)がすべて課税対象となるため、事業主本人には給与という概念はありません。しかし法人化すると、法人の資産と個人の資産は別に扱われます。そのため、経営者は役員報酬という形で給与を受け取ります。また、役員報酬は損金計上することが可能ですが、一定の要件を満たすことが必要なので、専門家である私たち税理士にご相談ください。 <退職金を損金計上することが可能> 個人事業主の場合、事業主への退職金は経費として認められません。一方法人の場合は、役員でも退職金の損金計上は可能です。法人税は、法人所得を基に算出されるため、「法人所得を減らす=節税」となります。 <消費税の納付が最大で2年免除> 個人事業主・法人共に、2期前(これを「基準期間」と言います。)の年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が発生します。ただし、個人事業主として2年前の年間売上が1,000万円を超えている場合でも、法人化することで課税事業者になるタイミングを2年間遅らせることができます。これは、法人化することで法人設立の1期目と2期目の「2年前の売上」は存在しないことになるため、原則として消費税の納税義務から免除されるからです。 ここで気を付けるポイントとして、消費税の納税義務が免除されるためには、資本金が1,000万円未満で法人化する必要があります。また、1期目の前半6カ月(これを「特定期間」と言います。)の売上が1,000万円を超え、役員報酬を含む人件費が1,000万円を超える場合には、2期目から消費税の納税義務が発生するため注意しましょう。 但し、インボイス制度の導入により、新設法人でもインボイスの登録が必要な場合には消費税の納税義務者となる必要があります。 <赤字は10年間繰り越せる> 個人事業主の場合でも青色申告をすれば、3年間は赤字を繰り越すことが可能です。しかし、法人化すれば、最大10年間まで赤字を繰り越すことができます。繰越控除期間の10年間は、利益が出た年に赤字を黒字で相殺するため、利益が出た年の課税所得を減らすことで法人税の節税に繋がるのです。 <生命保険料は経費にできる> 個人事業主の場合は、生命保険料を経費にすることができないため、確定申告ではわずかな控除しか受けることができない一方で、法人化していれば、契約者と受取人を法人契約で生命保険に加入することで、保険料の一部又は全部を経費にすることも可能です。ただし、保険の種類によってできないものもあるので、間違わないよう私たち税理士へご相談ください。 メリット③法人化すると有限責任 個人事業主の場合は無限責任のため、事業の責任はすべて事業主が負います。事業上の金融機関からの借入はもちろん、仕入れ・取引先との未払金、税金の滞納料金なども、すべて個人の負債となるためリスクが高いです。 法人の場合は有限責任となるため、すべての負債を背負う必要はありません。有限責任は出資額以上の支払い義務が発生しないため、万が一でもリスクを最小限に抑えることができ、個人の資産は守られます。 法人化することで、もしものときのリスクを減らすことは大きなメリットと言えるでしょう。 メリット④決算月を自由に決められる 個人事業主の場合は、法律によって事業年度が1月〜12月、決算月も12月ときめられています。一方で法人の場合は、事業年度の決算月はいつでも自由に設定することが可能です。法人の繁忙期と決算月が重ならないように時期を調整することで、負担を分散することができます。 個人事業主から法人化するデメリット 法人化をすることで得られるのはメリットだけではありません。 個人事業主だったときにはないコストや税負担があるので、場合によってはデメリットになるリスクも知っておきましょう。ここからは法人化をすることで生じるデメリットを3つ紹介していきます。 デメリットを①法人を設立するには費用がかかる 当然ですが、法人を設立するためにはさまざまな申請や費用がかかります。設立費用は法人形態によって異なるため、まずは合同会社と株式会社、どちらを選択するのか決めましょう。 また、法人設立には資本金が欠かせません。法律上、1円からでも法人設立は可能ですが、資本金は対外的に会社を精査する基準にもなるため、出来るだけ多く準備しておくことが望ましいです。一般的には、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は、最低でも準備しておくと良いでしょう。余裕をもって資金を準備できていれば、思わぬ問題が発生した時にも、余裕をもって対処できますよ。 デメリット②社会保険への加入が必要 法人化することで、健康保険・厚生年金といった社会保険への加入が必要で、法律によって義務付けられています。また、社会保険料の半分を負担する必要があるので、法定福利費や手続きが増えることで、事務負担が増えてしまうこともデメリットです。 デメリット③赤字でも税金がかかる 個人事業主は、決算でもし赤字になってしまった場合、所得税と住民税は0円です。一方で法人の場合には、赤字でも法人住民税の均等割を納付する必要があります。 法人住民税とは、県や市町村などの地方自治体に支払う税金のことで、法人税割と均等割の2つに分かれています。 法人税割の場合は、法人の税額をベースに算出するため、赤字だと税額は0円です。 一方、均等割の場合は、資本金や従業員の数によって金額が定められています。赤字であっても税金の納税義務が生じるため、利益がない場合にはデメリットといえるでしょう。 法人化する最適なタイミング 法人化をすることでメリットを生むためには、最適なタイミングを見極める必要があります。タイミングを間違えると、場合によってはリスクを負うことになりかねません。ここでは「利益」「売上」「節税」の3つの観点から法人化へのポイントを紹介していきます。 利益から見た場合|所得額が800万円〜900万円程のタイミング 利益の観点から見た法人化のポイントは、所得額が800万円〜900万円程のタイミングが良いとされています。 以下の表をご覧になってもわかる通り、個人事業主の場合、所得税率は5%〜45%(7段階)に区分されて、所得が増えるほど税率も上がっていく仕組みです。 国税庁|所得税の税率 一方、法人の法人税率は、利益が800万円以下なら15%、800万円を超える場合には23.2%に設定されています。 国税庁|法人税の税率 以上のことを踏まえると、利益の観点から見た法人化のタイミングは、800万円を超えたあたりから考えると良いでしょう。ただし、法人化をする判断は難しいため、専門家である税理士の私たちにご相談ください。金額を踏まえた上で、さまざまな概要を含めて総合的に適切なタイミングを導き出します。 売上から見た場合|年間の売上が1,000万円超え 売上の観点から見た場合は、年間の売上が1,000万円を超えてくることが、一つの目安となります。また、個人事業主・法人に関わらず、売上が1,000万円を超えるとその2年後から消費税課税事業者として消費税の支払い義務が生じることを理解しておきましょう。 ただし、消費税課税業者となるタイミングで法人化をすることで、売上の基準がリセットされるため、2年間の免責期間を作ることができます。 消費税については前述の通り、様々な注意点がありますので、我々税理士への相談をするようにしましょう。 節税から見た場合|所得額800万円を大幅に超える時 法人化する大きなメリットの一つとして、節税効果の高さが挙げられます。個人事業主は所得額が増えるごとに税率が上がる累進課税制度が適用されていますが、法人の場合は所得額800万円を基準にほぼ一定です。 そのため、所得額が800万円よりも大幅に増える場合だと、個人事業主のままでいるより法人化することが節税に繋がります。 また、法人化することで給与所得控除や退職金を損金計上ができたりと、法人化したからこその節税メリットがあります。 ただし、会社の状況によっては節税に繋がらないこともあるため、利益・売上・節税の3つのバランスがとれているかどうかを含めて、法人化の最適なタイミングを考慮しましょう。 法人化する時の注意点とは? ここまで、法人化をすることによって得られるメリット・デメリットについて解説してきましたが、いかがでしょうか。タイミングさえ間違えなければ、もたらされるメリットも大きいため、事業拡大を考えているなら法人化は魅力的でしょう。ただし、法人化するなら気を付けるべき注意点がいくつかありますので、紹介していきます。 法人の設立費用の負担 法人の設立には費用がかかります。 株式会社の設立については、主に以下の項目が必要な内訳と費用です。 法人設立(株式会社)にかかる内訳と費用 ・登録免許税:15万円~(または資本金の0.7%の金額) ・定款認証手数料:5万円 ・定款の謄本請求手数料:約2千円~(1ページに付き250円) ・収入印紙代:4万円 収入印紙代は、紙で定款作成する場合に必要ですが、電子定款を利用すれば費用を節約できます。 また定款は一般的に8枚程度あるため、約2千円と記載しました。 なお、登録免許税は資本金の0.7%と定められていますが、その金額を下回ることもあるでしょう。その場合には一律15万円と定められていますので注意しましょう。 株主総会や取締役会の設置が必須 法人を設立した場合、自由度が高かった個人事業主よりも意思決定に制限・制約が生まれます。なぜなら法人としての重要な意思決定は、必ず取締役会や株主総会などで決めなければならないからです。取締役も株主も自分一人だけであっても、原則、最低株主総会は開かねばならないため、招集通知や議事録などを作成して保管する必要があります。そのためスムーズでスピーディーな意思決定や運営、対応ができなくなってしまう可能性も考えておきましょう。 会計財務が複雑化する 法人化すると、個人事業主のときにはなかった経理作業が増え、より複雑化します。それは1人会社だったとしても同じです。増えた作業を補うために、税やお金のプロである税理士に依頼することで、かかる負担を軽減することも視野に入れておくことをおすすめします。 法人住民税の均等割が常に課税される 上記でも触れましたが、法人化すると法人住民税の均等割額7万円は、たとえ法人が赤字だったとしても課税されるため注意が必要です。 これは、住民税は地域社会の一員として支払う会費であるからです。これまで自分が受けてきた行政サービスの費用は、住民税を通して地域に提供されているため、その地域に住まう個人や法人に課税されているのでに課税されているのです。 社会保険への加入が必要 個人事業主の場合にも、国民年金と国民健康保険の負担がありますが、会社を設立したならば、たとえ一人会社だったとしても社会保険と厚生年金保険への加入と費用の負担が必要になります。 法人化するまでの流れ・必要な手続き 法人化にはメリット・デメリット・注意点をよく理解した上でタイミングを見極めることが重要だと理解できたところで、法人化するための流れや手続きを簡単に紹介します。 個人事業主から法人化するまでの流れ 個人事業主から法人化する流れは、以下のとおりです。 ①会社の基本事項を決める ②会社用の印鑑を購入する ③定款を作成する ④株式会社の場合は定款の認証を受ける ⑤資本金の払い込みを行う ⑥法務局で登記申請する ⑦登記申請後に法務局で確認・手続きをする このように、法人化するまでには多くの手続きが必要になるため、時間や資金に余裕を持って進めることが重要です。また、法人化以外にも個人事業主の廃業手続きなどが必要になるため、事前に行うべき手続きの内容を理解しておきましょう。 法人化するために必要な手続き 法人化が起業による法人設立と異なるところは、個人事業主として行っていた事業をそのまま引き継ぐという点です。ここからは、法人化するための手順を紹介します。 法人化の手順 ①法人の設立 法人化には、法人設立に関する手続きを行います。具体的には、定款の作成、定款の認証、資本金の払い込み、設立登記の申請といった手続きが必要です。株式会社や合同会社など会社の種類によって多少手続きには違いがあるため、設立する法人に必要な手続き内容を確認しておきましょう。 ②個人事業の廃業手続き 法人の設立ができたら、個人事業の廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を管轄の税務署に提出し、廃業手続きを行います。青色申告をしていた場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書を、また、従業員を雇っていた場合は給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を提出する必要があります。 また、個人事業を廃業しても、最後の年の確定申告は必要です。廃業した翌年に確定申告を忘れずに行いましょう。なお、法人化1年目は、前述の個人事業主の事業所得の他、法人化した後の役員報酬をもとにした給与所得も申告が必要です。 ③資産や負債の引継ぎ 設立した法人に対し、事業に関わる資産や負債の引き継ぎを行います。資産の移行には、売買契約・現物出資・賃貸契約の3つの方法があり、それぞれ手続きや税法上の取り扱いが必要です。 また、法人に債務を移行する方法として、設立した法人が個人事業主本人と共に債務引受する「重畳的債務引受」、法人が単独で債務を引受する「免責的債務引受」の2種類があります。 ④許認可手続きや各種契約の名義変更 許認可が必要な事業や、オフィスや店舗の賃貸契約を結んでいる場合などには、個人から法人への名義変更が必要です。取引に使用する銀行口座も、個人名義のものとは別に法人名義の口座を新たに開設しましょう。 法人化をするなら税理士に相談しよう! ここまで解説してきたように、個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なります。そのため、最大限メリットを得られるように法人化の最適なタイミングを見極めることは難しく、専門家に相談することを検討してみてください。 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 税理士に依頼するメリット 個人事業主が法人化すると、節税をはじめとするさまざまなメリットを得ることができます。しかし、事業の運営状態や売上規模によっては、法人化せずに個人事業主のままの方がトータルの支出額を抑えられる場合もあります。法人化のタイミングは、知識だけでなく、経験による予測も重要なため、迷った場合は税務の専門家である税理士に相談し、アドバイスを受けるといいでしょう。プロである税理士は、必要な知識と経験を兼ね備えているため、お客様の事業にとって、最も良いタイミングで法人化を進めることができます。 法人化についての無料相談は税理士法人プロゲート仙台オフィスまで 私たち税理士法人プロゲート仙台オフィスは、創業50年以上の実績があり、仙台市で起業・開業を考えている人に寄り添った創業支援を提供しています。確実かつスピーディーな会社設立ができるだけでなく、将来の事業の展望などを踏まえ、融資や助成金、節税などのアドバイスも行っております。本記事でご紹介したような新規法人設立をご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説

会社設立の際の費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説
弊社、税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社設立のご相談を受ける際、費用面でのご相談も多いです。 特に「会社設立にかかる費用は経費なの?」という疑問は多く聞かれますし、これから会社設立を考えているなら気になる方も多いのではないでしょうか。 今回は会社設立の際にかかった費用が経費となるかや、費用の仕訳方法について解説していきます。また、会社設立を税理士に依頼するメリットについても合わせて紹介しますので、参考にしてください。 関連記事:仙台市|会社設立をするなら専門家に依頼するべき?失敗しない方法や創業サポートについて 経費とはどのようなもの? 経費とは、個人事業主や法人が事業を行って収益を上げるために、または、管理を行うために必要な費用のことです。社会人をしていると「経費で落とせるから大丈夫」という言葉を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。 例えば、取引先の方と食事を交えて仕事の話をする場合は接待交際費として経費を計上できます。ただし、ここで間違ってはいけないのは「経費で落ちる=お金はかからない」わけではないということです。あくまでも会社の運営に必要な経費として「経費で落ちる=会社の資金から落ちている」という認識を持ちましょう。 なお、経費として計上できるのは次の通りです。 ・接待交際費:取引先との会食や贈呈品などに必要な費用 ・福利厚生費:従業員の福利厚生のために必要な費用 ・旅費交通費:仕事のための移動にかかる費用 ・出張費:出張にかかる宿泊費などを含めた費用 ・研修費:社員の研修やスキルアップのために必要な費用 以上の他にも分類されない費用がありますが、基本的な経費の知識を理解しておくことで、より効果的で無駄のない経費管理が可能となります。 経費にするメリット 会社で経費として計上することのメリットは、経費が増えると納める税金が少なくなることです。新しく事業を立ち上げたり、事業を運営する場合には、発生した利益に応じた金額を税金として納める必要があります。 会社の営業活動による成果は収益と呼ばれ、収益から経費を差し引いた金額が会社の利益となる仕組みです。そして、利益が大きいほど支払う税金が高くなるため、収益から経費を多く引くことができれば納税額が少なくて済みます。 何が経費で計上できるかの範囲を理解しておくことは、会社の運営を適切に行うためにも節税のためにも重要です。 経費にならないのは? では、経費で計上できないものとはどんなものでしょうか。 経費として計上できるのは、会社の売り上げに直接または間接的にかかる費用です。そのため、個人的な費用の支払いは経費に計上できません。 例えば、個人の飲食代や私生活に必要な日用品などです。このような会社の売り上げと関係ないものまで経費として計上してしまうと、税務調査において指摘され、調査結果によってはペナルティを課せられてしまうため注意しましょう。 会社設立でかかる費用の区分 会社を設立するにあたってかかる費用は「創立費」と「開業費」の2つに分けられます。 創立費は起業の準備から会社設立までにかかった費用、開業費は会社設立から実際に営業開始までにかかった費用のことです。それぞれのどのような特徴があるか解説していきます。 会社設立の準備から設立までにかかる創立費 先でも述べたように、創立費は起業するための準備期間から会社設立までにかかった費用のことです。創立費は経費として計上できるため、うまく使えば大幅な節税効果が期待できるでしょう。 以下、創立費として計上できる費用をご紹介します。 ●発起人報酬や使用人への給与用 ●設立登記を依頼した司法書士や行政書士への報酬 ●定款認証費用 ●創立事務所の賃貸料 ●登録免許税 ●金融機関への取引手数料 上記以外での会社設立に必要な費用なら経費として計上できる場合もあります。例えば会社設立のための会議を喫茶店でおこなった場合、その時にかかった飲食代や交通費は創立費として計上しましょう。 会社設立後から営業開始までにかかる開業費 開業費は会社を設立した後、実際に営業を開始するまでにかかる費用です。開業費も経費として計上できます。 以下、開業費として計上できる費用は以下をご紹介します。 ●営業開始にまつわる研修費 ●接待交際費 ●広告宣伝費 ●市場調査費 ●印鑑や名刺の制作費用 上記以外にも、会社の営業を開始するために必要であれば、開業費として計上することができます。ただし、会社設立日から営業開始までの期間に限定されるため、注意が必要です。開業費として計上できないものには、土地や建物の賃貸料、水道・光熱費、社員の給与などの継続的に発生する費用は含まれません。 繰延資産をうまく活用する 創立費と開業費の勘定項目は「繰延資産(くりのべしさん)」と呼ばれる資産です。繰延資産は任意の期間に費用として計上できるので、会社設立や開業準備を行った年に計上する必要がありません。このような理由から、多くの利益を得ることができた年に経理処理をすることができ、創業初期の節税対策としても非常に有効な仕組みです。ここからは繰延資産について解説していきます。 繰延資産とは? 繰延資産とは、支出の効果が来年以降も継続する場合に、費用を資産として計上できる仕組みです。先でお伝えしたように、会社の創立費と開業費は経費として計上できます。ただし、経理処理をするときはいったん繰延資産に計上した後、任意のタイミングで償却していきます。これは、会社設立の初年度にすべての経費を計上してしまうと、赤字になってしまう可能性があるからです。創立費と開業費を一度繰延資産にすれば、複数の年度で分散することもできますし、会社の運営がうまくいき、利益が多く出たタイミングで一気に経費化することも可能です。この仕組みを利用することで、経費の計上を分散したり、税金面で有利になる状況を作り出すことができるのです。 繰延資産の償却方法 償却とは、繰延資産に計上した金額を費用化する処理のことで、創立費と開業費を償却するには2つのルールがあります。 ・会計ルール 会計ルールでは、繰延資産にした創立費と開業費の償却期間は5年以内です。また、償却方法は毎期同額を償却する定額法を用いることが会計ルールとして決められています。 ・税務ルール 税務ルールでは、焼却する金額や償却期間を納税者がその都度変更できます。もし税務ルールで繰延資産を償却するなら、会社の経営状経営状態に応じて消化することが可能です。 流れに沿った費用の仕訳方法 経費がどんなもので、会社設立にはいろいろな費用がかかることが分かったと思います。 ここまでの内容を基に、会社を設立する際のそれぞれの費用の仕訳方法について簡単に解説していきます。 開業準備のとき 借方貸方現金(資産)資本金(純資産) 会社の経理処理は、まずは資本金の払い込みからスタートします。 会社設立の登録免許税を支払ったとき 借方貸方創立費(資産)現金(資産) 登録免許税や定款認証費用などは費用計上しがちですが、創立費として資産計上します。 開業準備の市場調査費を支払ったとき 借方貸方開業費(資産)現金(資産) 市場調査費や広告宣伝費なども費用計上しがちですが、開業費として資産計上します。 決算処理で繰延資産を償却したとき 借方貸方創立費償却(費用)開業費償却(費用)創立費(資産)開業費(資産) 会計上では繰延資産とした創立費と開業費の償却は、償却期間が5年間と決まっています。ただし、税務上では任意となるので、もし赤字の場合は償却処理をせず、利益が上がった段階で償却処理をすることも可能です。会社の経営の状況を確認しながら、無理なく確実に償却していきましょう。 税理士に依頼するメリット ここまで費用や経費、償却方法などについて解説してきましたが、ややこしいですし難しい内容ですよね。実際に会計処理を行う場合、専門的な知識がないと損をしてしまうかもしれません。そんな時は、弊社、仙台オフィスにも在籍している専門家「税理士」に依頼することがおすすめです。ここでは税理士に依頼するメリットについて4つ紹介します。 税理士に依頼するメリット①余計な税金を払わずに済む 会社設立の際に気を付けたいのが税金の管理です。特に創業初期は何かとお金が掛かるだけでなく、会社の経営がうまくいくかもまだわからない時期なので、出来るだけ無駄な税金は払いたくありませんよね。しかし、専門的な知識が不足していると、「もっと節税できたのに」という事態になりかねません。 私たち税理士はお金のスペシャリストで、会計から税金のことまで知識が豊富です。会社設立や運営における適切な税務のアドバイスや、経費として計上できる項目、節税対策などのサポートをします。税理士の専門知識を活用することで、円滑な資金繰りや事業運営を進められるでしょう。 税理士に依頼するメリット②補助金や助成金、融資のアドバイスがもらえる 税理士に相談するメリットとして、補助金や助成金、融資についての知識が豊富で、適切なアドバイスを受けることができます。 利用可能な補助金や助成金があっても、知識不足から見逃してしまいがちですが、税理士に依頼すれば、どんな制度が利用可能で一番節税できるか、経営する事業に合わせたアドバイスを受けることが可能です。 例として仙台市では、新規事業者向けの補助金として「仙台市中小企業チャレンジ補助金」「仙台地域企業スケールアップ補助金」などが用意されています。 また、創業時には有利な条件で受けられる「創業融資」があり、この融資をうまく活用できれば、倒産のリスクを避けつつ安定した安定した経営を行うことも可能でしょう。弊社、仙台オフィスでも多くのご相談を受けており、融資成功率は毎年90%以上あります。 税理士に依頼するメリット③本業に集中できる 会社設立はしたけれど、事務作業や手続きに追われて「本業に集中できない」という事業者様が多いのではないでしょうか。 銀行口座の開設、クレジットカードの発行、記帳業務、従業員の給与計算、各種届出書類の作成・提出、役員報酬の準備など、やらなければいけないことが多く存在します。慣れていない人が作業しようとすると、大幅な時間ロスや書類のミスが考えられ、大きな負担となることでしょう。 税理士に依頼すれば、面倒な記帳業務や手続きを支援してくれるため、本業に集中して取り組むことが可能になります。 税理士に依頼するメリット④会社設立の失敗を未然に防ぐ 会社設立には定款や登記など、あとから変更することが難しい書類があります。この内容は重要なことで、会社名・本店所在地・役員氏名・資本金などを登記事項として法務局へ登録する必要があるのです。 専門家に相談することで、不用意な記載を避け、慎重に検討し最適な決定を行うことができます。 関連記事:会社設立は自分でする?専門家に依頼?費用と手続きについて解説 無料にてご相談お受けしています 今回の記事では、会社設立にかかる費用は経費になるのかや、仕訳方法などについて解説してきましたがいかがでしょうか。 会社設立には多くの費用がかかりますが、中には経費として計上できるものがあり、うまく処理すれば節税にもつながります。しかし、それには専門的な知識が不可欠です。また、各種書類の作成や手続きが多いので、税理士に相談しアドバイスをもらうことが重要です。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、会社設立における創業支援が充実しており、会社をスタートさせるために必要な業務を、すべてサポートいたします。 これまで200社以上の会社設立に携わってきた実績があり、得られたノウハウをすべて提供させていただくことが可能です。また、会社設立から設立後に必要な手続きまで万全のバックアップ体制を整えていますので、ご安心してお任せください。 会社設立にかかる費用や経費について疑問や不安がある方は、まずは弊社に相談してみてください。ご連絡お待ちしております。 関連記事:会社設立時に発生する税金は?設立後についても解説 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:合同会社の設立には、代表社員が2名でも大丈夫?
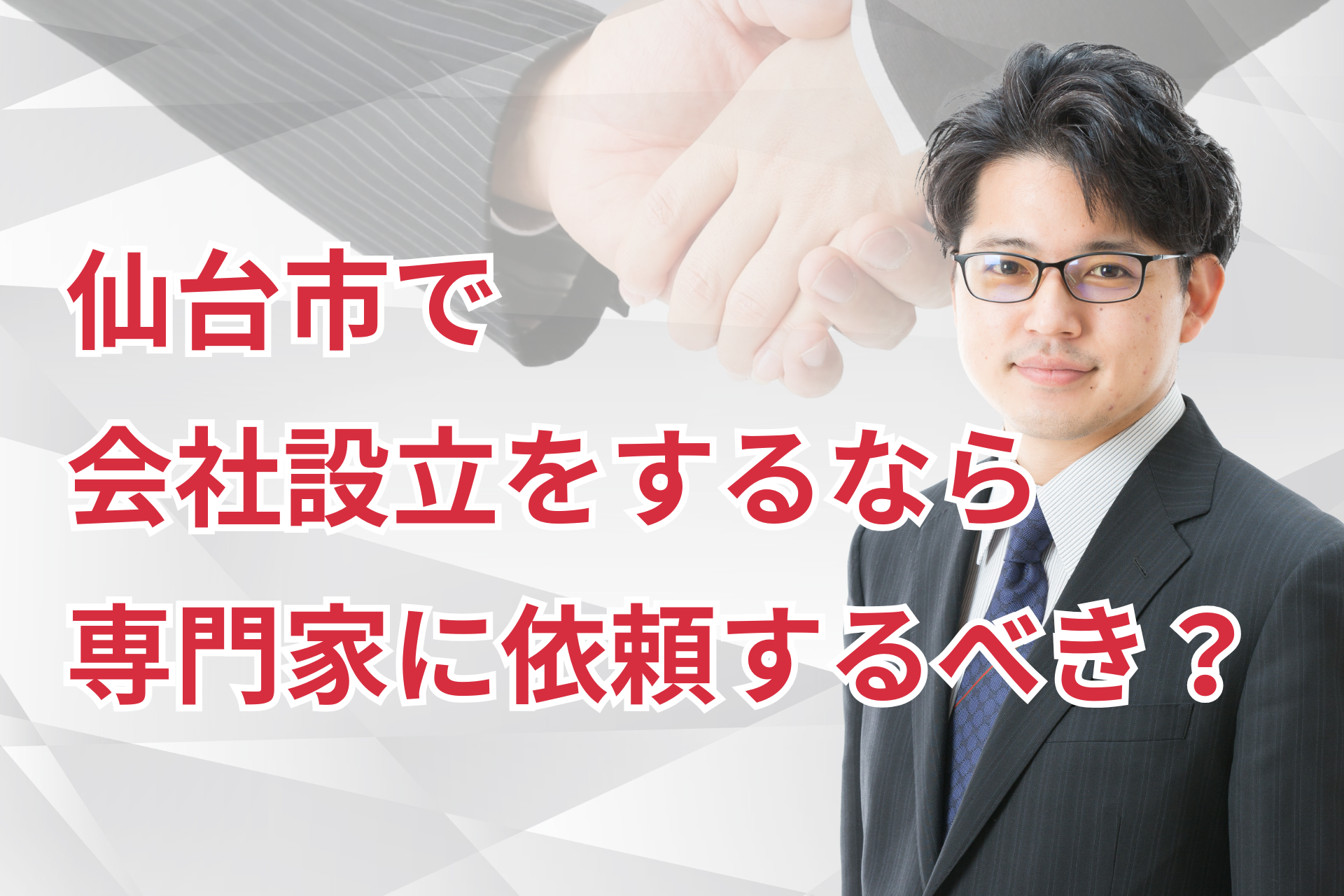
仙台市|会社設立は専門家に依頼?失敗しない方法や創業サポートについて
仙台市で会社設立をする場合、どうしたらよいでしょうか。 できれば費用を抑えてお得に会社設立できたらいいですよね。もちろん自分で設立することで費用を抑えることも可能です。しかし、専門的な知識がないと会社設立の書類作成や申請手続きはややこしく、ミスをしてしまうかもしれません。慣れない作業に手間取り、時間がかかってしまうことや、ミスによって書類を作り直すことによる時間のロスは、大きな損失になるため、失敗は避けたいですよね。 この記事では、会社設立支援実績200社以上ある税理士法人プロゲートが、仙台市で会社設立をする場合のお得な方法や失敗しない会社設立、仙台市で受けられる創業サポートについて紹介していきます。是非、参考にしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=qHnHzbQm35Y 仙台市で会社設立をする魅力 近年、会社設立の地として注目されている仙台市。仙台市がどうして会社設立の地として選ばれているのか知っていますか。 ここでは、仙台市で起業する魅力について4つ紹介していきます。 仙台市で会社設立する魅力①国の政令指定都市 東北地方で最大の都市として知られている仙台市は、「国の政令指定都市」です。 事業者が活動しやすい様に規制を緩和したり、手続きを簡略化したりすることで、より事業活動や経済活動が活発に行えます。仙台市を「日本一、起業しやすい街」にするため、仙台市ではさまざまな地域で「国家戦略特区」の制度を活用し、起業を目指す方にとっては踏み出しやすい環境が整っていると言えるでしょう。 仙台市で会社設立する魅力②周辺地域へのアクセスの良さ 仙台から東京までは、新幹線で約1時間35分で行くことができ、飛行機では国内線だと北海道から沖縄までの11の空港へ、国際線ではソウル・上海・北京・台北の4つの空港へ行くことが可能です。 仙台市内は車移動が必要な所もありますが、街の中心部なら地下鉄・JR・路面バスなどの公共機関を利用することで十分生活することもできます。このような周辺地域へのアクセスの良さもビジネスの拠点として仙台市に会社設立をおすすめする理由の一つです。 仙台市で会社設立する魅力③バランスの取れた産業と教育 仙台市は商業、製造業、特に電子機器と食品加工業が盛んです。比較的低い産業コストと質の高い労働力も魅力の一つで、起業家にとってはうれしい条件が揃っています。また、東北大学をはじめとする経済の教育・研究機関も集積しており、学術的な視点から経済の見直しのアドバイスがもらえたり、市や大学などの研究機関と連携して経済発展に活発な行動ができる仕組みも魅力的です。また、後ほどご紹介しますが、仙台市では会社設立のサポートも充実しており、新規事業者は起業から運営まで、さまざまな支援を受けることができます。 仙台市で会社設立する魅力④さまざまな創業サポート ①〜③の内容に加え、仙台市では起業家に向けた創業サポートが充実しています。公的機関の相談窓口も多く準備されているので、 といった気軽な相談から、 といった具体的な内容も、さまざまな専門家の力を借りられる仕組みができているのです。 仙台市では無料の電話相談窓口で専門家が対応してくれる場合が多く、起業家にとって嬉しい創業サポートが充実しています。初めての会社設立でも一歩を踏み出しやすい環境が整ってるだけでなく、創業サポートをうまく利用すればお得に起業できることも魅力的ですね。 ここまで仙台市で会社設立をする魅力について紹介しましたが、どうすれば会社設立の費用を抑え、よりお得に起業することができるのでしょうか。 会社設立を自分で行うメリットデメリット 会社設立は自分で行うことが可能です。その場合、どんなメリットとデメリットがあるのか十分に理解しておく必要があるので解説していきます。 自分で会社設立を行うメリット|費用が抑えられる 一番のメリットは、外注費用が抑えられることです。また、会社設立に関するための知識を勉強するため、結果的に会社法や税金などの知識を身につけることができ、会社を設立するという経験も得られます。 自分で会社設立をデメリット|面倒くさい&ミスが起きる 一方、会社設立には多くの提出書類を用意する必要があり、手順も複雑です。慣れない作業だと時間も掛かり、ミスをしてしまうリスクが高まってしまうというデメリットがあります。また、手続きと準備に時間をとられてしまい、肝心の会社の事業が圧迫されてしまうかもしれません。 会社を設立するという経験は得難いものですが、十分な時間が確保できない人や、専門知識に不安がある方は一度専門家に相談してください。弊社でも初回相談は無料でお受けしております。 会社設立を依頼する場合のメリットデメリット 会社設立を自分で行う場合のメリット・デメリットを解説してきましたが、専門家に依頼した場合はどうでしょうか。ここからは専門家に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説していきます。 専門家に依頼するメリット|時間と手間がかからない! 専門家に依頼した場合、一番のメリットは何と言っても正確な書類作成とスムーズな申請手続きによる時間の短縮化でしょう。必要書類や手続きのミスをなくし、正確に用意できることは専門的な知識があればこそ可能といえます。必要な書類もスムーズに準備することや申請代行によって大幅に時間を短縮することができれば、他のことに時間を使うことができ、会社設立を進めながら本業にも集中して取り組むことが可能になります。 外注費用が掛かるとはいっても、自分で会社設立を一から行うよりもはるかに早くスムーズに設立することができるので、結果的に費用が抑えられます。合わせて必要なときにアドバイスを得られることを考えれば、必要な出費ではないでしょうか。 専門家に依頼するデメリット|費用がかかる 専門的に依頼した場合のデメリットとしては外注費用がかかることです。概算費用としては、下記のとおりです。 株式会社:約245,800円~ 合同会社:約103,500円~ 費用についての詳細はこちらの記事をご覧ください。 また、どこに相談をすればいいか分からない人も多いでしょう。せっかく依頼したとしても、相性が悪いとうまく連携が取れず、計画通り進まない可能性も考えられます。 人と人なので相性はありますが、コミュニケーションをとり、関係性を築ける専門家を選べるように、無料相談・面談などを活用して事前に相性を確認することも必要です。 会社設立で失敗しないためには専門家に依頼! ここまでご説明した通り、会社設立で失敗したくないという方は、専門家に依頼しましょう。デメリットとしては外注費用が掛かることぐらいで、正確な書類作成や申請代行、必要なアドバイスなど、依頼した方が受けられるサポートやメリットが大きいです。 ここからは会社設立を進める上で関係する専門家について紹介していきます。 税理士|登記業務は専門外 税理士は財務の専門家です。主に税金や決算に関する会計業務の専門知識を持っており、会社設立や経営・財務相談などを依頼できます。会社設立に特化しているわけではありませんが、必要な知識は最低限有していることや、税金などの節税に関して強いので、会社設立後も長期的なサポートを受けられるよう顧問契約を結ぶこともよいでしょう。ただし書類作成支援はできますが、登記業務や許可申請は専門外です。 税理士は他の専門家と提携している場合が多いので、必要に応じて他の専門家を紹介することが可能です。 司法書士|実際に登記申請を行う 司法書士は登記の専門家で、会社設立で必要な登記関連の手続きの代行が可能です。他の士業とは異なり独占業務のため、司法書士だけが登記申請や登記の関連業務を行う資格を有しています。登記申請は細かい内容や申請が複雑でミスが起こりやすいため、専門家である司法書士に依頼すればスムーズに申請を進めることが可能です。 しかしながら、設立時の決算期の設定の仕方により、消費税メリットが受けられないケースも想定されますので、最初の相談は税理士に行った方がいいケースがあります。 行政書士|定款作成や許認可に関してサポート 行政書士は行政手続きに強く、届出の代行申請、許認可申請・公文書作成の支援などが得意です。また、定款の作成や承認業務のサポートも行います。 許認可が必要な業種は、介護サービス・飲食店・建設業・物品販売業・不動産業など多岐にわたるため、まずは自分の設立する会社には行政機関からの許可が必要なのか調べましょう。その上で必要なら行政書士への依頼を検討してください。 社会保険労務士|雇用関連のプロフェッショナル 社会保険労務士は、会社設立と合わせて社員を雇用する場合に労務関係の書類作成や相談ができます。人事に関しての専門家でもあり、労働保険・社会保険・年金・給与計算・帳簿作成など労務に関するアドバイスを受けることが可能です。また、雇用の助成金や補助金を申請する場合にも社会保険労務士がいると申請がスムーズに進めることができます。 創業50年以上の信頼「税理士法人プロゲート」 前項でご紹介したように、会社設立には多くの専門家が関わってきます。特定の専門家に依頼するというより、それぞれ役割をこなし、サポートし合いながらチームとして会社設立に向けて進んでいくのが理想的ですね。 弊社は税理士業務だけでなく、社会保険労務士業務、行政書士業務、経営コンサルティング業務も行っております。創業時から経営まで幅広くご相談やサポートが受けられる体制が整っていますので、安心してお任せください。 必要に応じて提携司法書士をはじめとした専門家をご紹介いたしますので、まず最初に税理士法人プロゲートにご相談ください。 200社以上の会社設立支援実績! 税理士法人プロゲートは創業1973年と歴史ある税理士事務所です。50年以上に渡り、経営者様や資産家様のサポートをしてきました。日本政策金融庫や民間金融機関との融資実績も豊富で、それらの経験から得られたノウハウを提供することができます。 また、冒頭でも記載した通り、弊社はこれまで200社以上の会社設立をサポートさせていただきました。その積み重ねてきた信頼を軸とし、お客様の目線に立ち、得られた経験やノウハウを分かりやすく提供しております。また、会社設立だけでなく、会社設立後に必要な手続きも含めた万全のバックアップ体制を準備していますので、安心してスタートを切ることができます。 税理士法人プロゲート仙台オフィスでは、税理士だけでなく、社会保険労務士、行政書士、など多くの専門家が在籍しており、さまざまな問題に応対可能です。会社設立だけでなく、財務会計、資金調達、給与計算、人事労務管理、相続相談、就業規則作成など総合的かつきめ細やかなサポートをご用意しております。 さらに、弊社ではベテランから若手まで幅広く人材が揃っていますので、お客様との相性の良いパートナーを見つけることもできます。お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい専門用語などを使用せず、わかりやすい言葉で説明し、具体的なイメージを描けるよう意識しております。「話しやすさ」「相性」等は実際に面談してみないと分からないことなので、会社設立をお考えの方はまずはお気軽にお問合せください。 税理士法人プロゲートが選ばれている3つのポイント ・専門家たちによるワンストップの総合サポートが充実! 弊社では税理士・社会保険労務士・行政書士など、豊富な知識と十分な経験を積んだ専門家が多く在籍しています。そのため、会社設立をする上でワンストップで対応可能です。会社設立時によくあるご相談が「創業融資」です。融資支援実績としては、毎年、融資実行率が90%以上ありますのでお任せください。 他にも税務・会計や資金調達、給与計算就業規則作成、人事労務管理、相続相談など幅広い問題に対応できます。 「こんなことを相談してもいいの?」と悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 ・創業50年以上の実績に裏打ちされたノウハウと専門家によるきめ細やかなサポート 弊社グループは50年以上に渡り、お客様創業や運営のサポートを行って参りました。 また、積み重ねてきたノウハウをお客様とのコミュニケーションを通して提供できるように心がけています。若手からベテランまで一人一人のスタッフが、きめ細やかに支援をいたしますのでご安心してお任せください。 ・若手起業家と同じ目線で未来を見据えた並行支援 専門用語は難しく、知識がないと理解に時間がかかってしまいますよね。 弊社では多くの専門家が在籍していますが、財務・会計などの難しい専門用語を使用せず、お客様の目線に立ち、わかりやすい言葉でご説明させていただきますのでご安心ください。平均年齢が60歳以上と言われる税理士ですが、当社では30代の若い税理士が親切・丁寧・誠実に未来を見据えた経営支援をさせていただきます。 税理士法人プロゲートで受けられるサービス案内 会社設立 税理士法人プロゲートでは、会社設立に関するための人材が豊富に揃っており、各種手続きに必要なサポートをご用意しております。 ご自分で行うことも可能ですが、不要なミスを事前に防ぎ、正確な書類作成や各機関への申請業務をスムーズに進めることができるので、私たちにお任せください。会社設立に伴う全ての相談・必要な業務をご支援いたします。 また、設立手続きを効率化するために、社内マニュアルを作成しております。これにより、低コストで間違いのない会社設立が可能となりました。 お客様に安心して会社をスタートできるように、ワンチームとなり全力でサポートいたします。 融資支援 これまでの実績を基に、申請前に独自の基準で融資の実行確率を判断することができます。その結果を受けて融資が可能と判断した場合には、成功率が90%以上ございますので、初めての方でも安心して融資を受けられます。 関連記事:日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合の流れをプロセスごとに解説 経理・記帳代行 「数字のミスは起きやすいけれど絶対に失敗したくない」 「自分で行うだけでは不安に感じる」 このようなお悩みをお持ちの方へ、税務・会計のプロである税理士が、複雑な税法に関してわかりやすく説明いたします。 労働保険・社会保険の手続き 新たに事業を立ち上げる場合や、社員・従業員の入退社に伴い、各種保険の手続きが必要です。税理士法人プロゲートでは、社会保険労務士も在籍しており、プロに依頼することでスムーズに手続きを進め、本業に専念していただけるようサポートします。 その他仙台市の起業家へ向けた創業サポート 仙台市では会社設立を考えている起業家の方に向けたサポートを積極的に行っています。ここからは仙台市独自のサポートについて紹介していきます。 仙台スタートアップスタジオ 仙台スタートアップスタジオでは仙台市と株式会社ATOMica、ReGACY Innovatio Group株式会社が中心となり、仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会参加団体とも連携して、起業家の皆様のさまざまなお悩みや相談に対応可能です。 各種セミナーを開催したり、仙台や東北にゆかりのある経営者や支援者の方からの意見やアドバイスを聞くことができ、革新的なアイデアや技術向上に繋がるきっかけになるよう支援や情報収集の場を提供しています。 仙台スタートアップスタジオ|公式HP 仙台市で会社設立の無料相談を実施の公的機関 初めての会社設立は、何から始めればいいのかわからず不安になってしまいますよね。そんな時には、仙台市で起業をする方のサポートを行ってくれる公共機関もあるので、まずは気軽に相談してみましょう。ここからは公共機関を中心に紹介していきます。 公益財団法人仙台市産業振興事業団「起業支援センターアシ☆スタ」 仙台市内にあり、仙台地域で起業を志す方のための起業支援センターです。 起業家や経営者に向けた各種セミナーの開催や、起業者同士の交流の場として開設されました。オープンスペースもあり、ビジネス書なども用意されているので、会社運営のノウハウや技術向上に向けたスキルアップのための勉強場所として利用されています。志を持った同業者との交流は良い刺激となり、新たなビジネスチャンスにつながる出会いもあるかもしれません。これから会社を設立する方だけでなく、起業間もない方、資金繰りについて相談したい方、事業資金計画、新しい販路開拓のアドバイスなどさまざまな相談にも対応可能です。起業に関するサポートから開業後のアドバイスまで、ワンストップで相談できますので気になる方はご確認ください。 仙台市起業支援センターアシ☆スタ|公式HP 所在地:仙台市青葉地区中央1-3-1 AER7階 連絡先:022-724-1124(平日9:00~17:00) 公益法人仙台市産業振興事業団「仙台市開業ワンストップセンター」 仙台市開業ワンストップセンターでは、仙台市内での会社設立のオンライン申請をサポートしております。 仙台市企業支援センター「アシ☆スタ」の交流サロン内にオープンしており、現在では会社設立に必要な定款の作成・認証、登記、許認可の申請手続きがオンラインで申請できるようになりました。オンラインを利用することで、書類の修正手続きや申請がスマート化するので、多忙な起業家には嬉しいサービスです。 仙台市は国家戦略特区に指定されており、行政手続きのオンライン化が積極的に推進されているので、利用してみてはいかがでしょうか。 行政書士、司法書士などの専門家が揃っているので、登記申請方法や電子定款の作成、会社設立のオンライン申請、許認可の申請、各種保険、労働相談についてのご相談も可能です。 仙台商工会議所「創業パワーアップサポート」 仙台市から「特定創業支援事業者」と認定されている仙台商工会議所では、経営支援員や連携する中小企業診断士、日本政策金融公庫、税理士、司法書士、などさまざまな分野のプロによるサポートが受けられます。 「創業パワーアップ」は、創業計画書の作成サポートから創業資金相談、許認可手続き、従業員の雇用と各種保険、販促や集客のアドバイス、創業後の搬送支援も充実しており、気軽な相談から未来のパートナー探しなど、起業に纏わる全てのサポートを準備しているので、初めての会社設立のでも安心して相談できます。 仙台商工会議所創業パワーアップサポート|公式HP 所在地:仙台市青葉区本町2-16-12 連絡先:022-265-8127(平日9:00~17:00) ビジネス相談起業家育成研究所 一般社団法人東北ニュービジネス協議会 一般社団法人東北ニュービジネス協議会は、東北地域の「出会い、ふれあい、つながり合い」をモットーに会社設立支援や起業家の育成、経営者などによるイベントやセミナー開催の支援などを行っています。全国各地に会員がおり、会員同士や各地域のニュービジネス協議会の交流の場としてイベントやセミナー、ビジネス相談会などを企画・開催し、新たなビジネスチャンスや相互研鑽の場を提供しています。 一般社団法人東北ニュービジネス協議会|公式HP 所在地:仙台市青葉区中央2-18-13 大和証券仙台ビル10階 連絡先:022-261-5817 仙台市で会社設立を検討中ならプロゲートへ! いかがでしたでしょうか。 仙台市は、大学や研究機関とも連携して経済発展を目指しており、国家戦略特区として起業家へのサポートも充実しております。まさに「日本一起業しやすい街」といえるのではないでしょうか。そんな魅力に溢れた仙台市で会社設立を考えている方は、まずは税理士法人プロゲートにご相談ください。 このようにお考えの皆さまと同じ目線に立ち、専門家の立場からご支援致します。 現在は、無料相談もお受けしておりますので、まずは気軽にご相談ください。メール、お電話でのお問い合せお待ちしております! 関連記事:会社設立は税理士に相談すべき?費用や相談するメリットなどを紹介! 関連記事:サラリーマンが在籍中に会社設立するメリットやリスクを解説 関連記事:合同会社の設立期間は?株式会社との比較や設立の手順も解説 関連記事:【まとめ】会社設立に必要なこと!手順や書類について解説 関連記事:融資を受けるなら税理士に相談した方がいい?依頼するメリットを紹介 関連記事:会社設立のときにかかる費用は経費にできるの?その流れや仕訳方法について解説 関連記事:個人事業主が法人化するベストタイミングは?メリット・デメリットについて解説 関連記事:仙台市青葉区で税理士をお探しなら税理士法人プロゲートへ